【中小企業の銀行対策】今更聞けない期限の利益の意味とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、今更聞けない期限の利益の意味について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 銀行と交わす契約書等はしっかりと熟読する
2 期限の利益を正しく理解しておく
どうぞ、ご一読下さい。
1 銀行と交わす契約書等はしっかりと熟読する
金融機関の特性として挙げられることの一つが、「書面主義」です。
取引の都度には必ず契約書を締結しますし、日々の打ち合わせ時には「打ち合わせメモ」を担当者が残しています。
金融機関につきものなのが、人事異動ですが、人事異動をスムーズに行えるのも、過去の取引状況や打ち合わせ内容が書面で残されているためでもあります。
「書面主義」の典型例が、中小企業や個人事業主が銀行取引を開始する際に締結する「銀行取引約定書」であり、長期借入金を実行する際に結ぶのが「金銭消費貸借契約証書」です。
ちなみに、通称「証書貸付」の「証書」は、この金銭消費貸借契約証書の「証書」に因んでいます。
この「銀行取引約定書」にせよ、「金銭消費貸借契約証書」にせよ、実にたくさんの条項が記載してあって、文字も比較的小さいので、メガネを外さないと読めない程ですが、この条項一つ一つが、極めて重要な内容となっています。
もっと言えば、条項の一つ一つが、基本的に債権者(金融機関)に有利な記載になっています。
保険の約款ほどではありませんが、ほとんどの中小企業経営者は、はなから条文に目を通す気力が失せてしまいがちですが、金融機関に有利な条項の内容となっている限り、金融機関担当者に断りを入れて、時間をかけてでも、一つ一つの条項に目を通すことが肝要です。
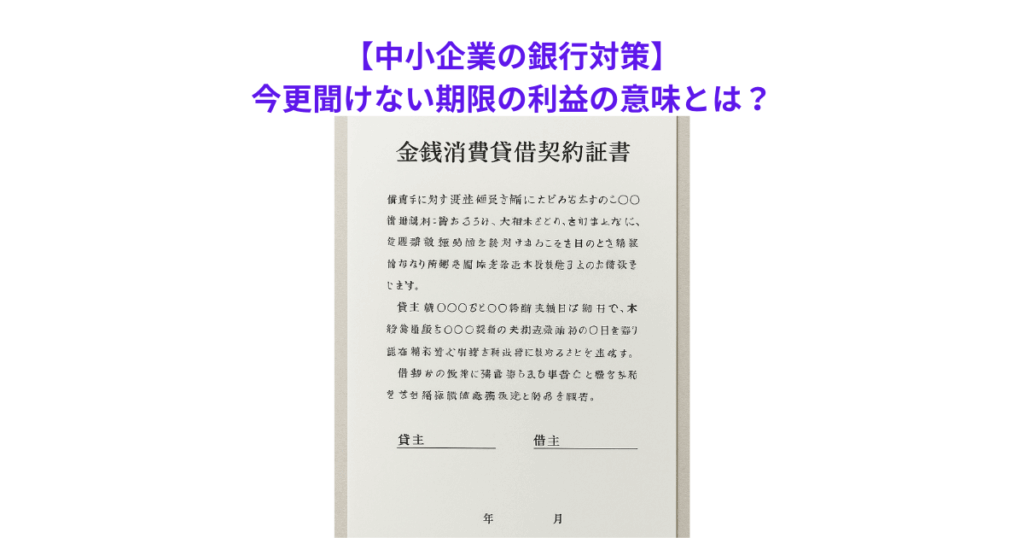
2 期限の利益を正しく理解しておく
金銭消費貸借契約証書の条文の中で、重要な条文の一つが、「期限の利益」に関することです。
「期限の利益」とは、長期の資金で、仮に毎月25日に返済する場合であれば、返済日を毎月25日と定めて、必ず毎月25日に返済することを言います。
毎月25日に返済しなければならないという意味ですが、裏を返すと、24日までは返済しなくても良いという意味でもあります。
期限の利益がある限り、債権者である金融機関が25日より前に返済を求めることはできないということです。
しかしながら、この期限の利益を失ってしまう場合について、しっかりと金銭消費貸借契約証書に記載されています。
例えば、債務者が破産手続きに入ったり、別の債権者が差押を行ったり、あるいは返済日に返済できない延滞状態となった場合などが期限の利益の喪失事項とされています。
期限の利益を喪失するとなると、金融機関は残債を一括返済することを求めることが可能になります。
なので、債務者は、大切な権利である期限の利益を何がなんでも死守しなければなりません。
条文によれば、わずか1日でも延滞すれば期限の利益喪失となるように読めますが、実務的には1日の延滞だからといってすぐに期限の利益喪失事項に該当するとして、一括返済を求めることはありません。
しかしながら、仮に1日の延滞でも「事故」になるので、延滞は絶対に避けなければなりません。
中小企業経営者は、今更「期限の利益って何だっけ?」とは聞けないものですが、今一度、期限の利益について正しく理解をして、間違っても、期限の利益を喪失するようなことがないよう、細心の注意を払わなければならないのです。


