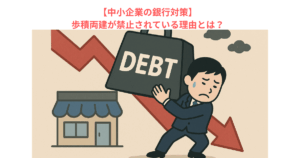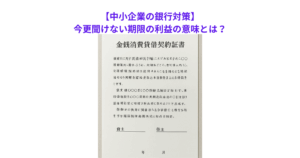【中小企業の銀行対策】取引金融機関担当者が気にする流動性預金の平残とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、取引金融機関担当者が気にする流動性預金の平残について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 金融機関営業店は独立採算制である
2 金融機関は仕入コストの低い流動性預金を好む
どうぞ、ご一読下さい。
1 金融機関営業店は独立採算制である
中小企業経営者にとっては、金融機関の組織というのはなかなかわかりにくい存在に映ってしまいがちです。
金融機関の組織特性を一言で片付けてしまうと「軍隊組織」ということになりますが、本部が方針を決めて、営業店(支店、支社、法人営業部等)が本部の方針に沿ってルーティンを回していくわけですが、中小企業経営者が押さえておくべきことが、金融機関営業店は独立採算制であることです。
融資(貸出金)から得られる貸出利息から預金者に支払う預金利息を差し引いた粗利益(業務粗利益)があって、業務粗利益から、営業店で発生する人件費、家賃、水道光熱費といった経費(販管費)を賄わなければなりません。
それだけではなく、本部は基本収益を産まない部門なので、本部経費も営業店が負担をした上で、営業店単独で利益を出さなければなりません。
つまり、部店長(支店長、支社長、法人営業部長等)は、いわば中小企業の経営者と同じような位置付けです。
部店長は雇われの身でありながら、本部経費を含めた諸経費を負担するという大きな役割を担っているのです。

2 金融機関は仕入コストの低い流動性預金を好む
金融機関営業店の部店長が、支店等の収益を上げようとすると、融資残高を増やして貸出金利息増やす(増収)、仕入コストの低い低コストの預金(仕入減)を集めるという2つの手が手っ取り早いことになります。
このため、長期安定した仕入となる固定性預金(定期預金等)は個人預金にシフトさせる一方、事業先に対しては、仕入コストの低い流動性預金(普通預金、当座預金等)の平残を上げることを支店長は外回りの部隊に指示します。
ここで、流動性預金の「平残」というのが重要です。
なぜかというと、月末1日だけ流動性預金が増えたとしても、末残(月末の残高のことを言う)は上がりますが、本部は営業店に対して、末残主義ではなく、平残主義を徹底しています。
平残とは、平均残高のことをいい、1ヶ月間の平均残高を増やすことによって、営業店の仕入コストを押し下げることができます。
このため、外回りの担当者も融資先に対して、流動性預金の平残を上げることを求めてきます。
中小企業経営者は、見た目の借入の利息だけではなく、メインバンクの流動性預金の平残を上げることによって、メインバンクの評価が上がることを認識する必要があるのです。