【中小企業の銀行対策】支払利息に経営者が関心を払わなければならない理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、支払利息に経営者が関心を払わなければならない理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 支払利息は増加するトレンドである
2 支払利息を固定費と捉える
どうぞ、ご一読下さい。
1 支払利息は増加するトレンドである
中小企業経営者が直近の試算表を手にした時、一番最初に見る項目が、損益計算書の売上高と営業利益です。
確かに、売上高が前月より増えたのか、前年同月実績との比較ではどうだったのかは経営者の最大の関心事ですし、仮に、経営改善計画を策定する場合でも、売上高が満足に立てることができなければ、ストーリーを展開することはできません。
また、営業利益についても、本業でどのくらい儲けられたのか(あるいは損をしたのか)も経営者にとっては無視できない重要な経営指標と言えます。
一方、損益計算書の営業利益の下部に記載される営業外費用の支払利息に関心を払う中小企業経営者はあまり多くないと言うのが北出の肌感覚です。
特に、お仕事をさせていただくようになる初期段階で、中小企業経営者に、「御社の銀行借入の適用レートは何%くらいですか?」とお尋ねすると、ほとんどの場合、経営者が言葉に詰まってしまうのです。
大切なことは、個々の借入金の適用レートがどの基準で決まっていて、スプレッド(上乗せ幅)がどのくらいかを把握することです。
例えば、メインバンクの短期プライムレートが2.575%で上乗せ幅が0.500%であれば、出来上がりの適用レートは3.075%になるという具合です。
昨年来、短期、長期共に、市場金利は上昇傾向です。
メガバンクや地方銀行の場合、中小企業向け融資の多くが自行短期プライムレートに連動しているため、昨年秋からの出来上がりの金利の上昇幅は0.400%に達します。
一部の信金・信組が基準金利として採用している長期プライムレートも過去1年間で0.400%上昇しています。
トランプ関税やドル円相場の変動の影響により急速な金利上昇は想定しにくいですが、長いトレンドでみれば、マイナス金利、ゼロ金利の局面は終息して、「金利のある世の中」に回帰しています。
長短の市場金利の上昇は、中小企業の営業外費用の支払利息が増加傾向にあります。
中小企業経営者は、金利上昇分を吸収できるよう、本業での儲けを増やす必要があるのです。
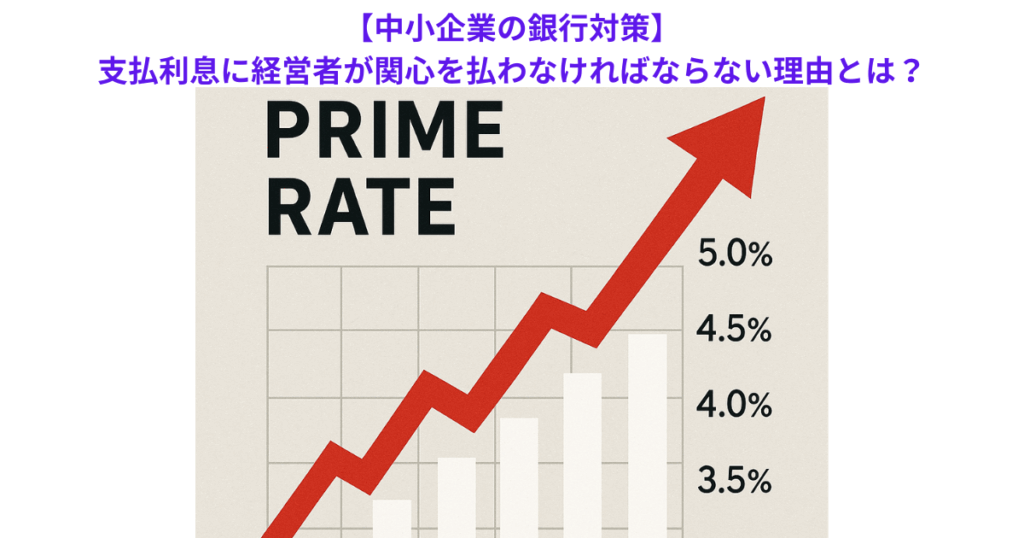
2 支払利息を固定費と捉える
失われた30年、35年があまりにも長く、その間、総じて金利は下降曲線を描いて、アベノミクス以降、マイナス金利の世界となったため、経営者が支払利息に関心を払わなくなったのはある意味当然と言えば当然のことかもしれません。
しかしながら、ゼロ金利、マイナス金利は終わりを告げて、いよいよ、支払利息がコストとして認識すべきフェイズに突入しています。
ましてや、リーマンショックや新型コロナウイルス感染症のような非常事態が起きない限り、緩やかながらも、市場金利は上昇していくことは想像に難くありません。
支払利息はもはや減ることはない歴然たる固定費そのものです。
支払利息の増加を抑制するためには、コロナ資金を含めた借入金の返済を約定通りに進めて、借入金の絶対残高を減少させていくことが必須です。
加えて、債務者区分を正常先として維持するのは当然のこととして、収益力を高め、借入金依存度を適正化することで、信用格付を引き上げて、出来上がりの適用レートが跳ね上がることを回避しなければなりません。
中小企業経営者は、「金利のある世界」が戻ってきたことをしっかりと認識して、過剰債務に陥らないよう適正な借入金の水準を確保しつつ、支払利息の増加分を吸収して余りあるような本業での儲けを創出していく必要があるのです。

