【中小企業の銀行対策】知ってそうで知らないメインバンクの定義とは?
今日は、中小企業経営者が知ってそうで知らないメインバンクの定義について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 借入残高だけがメインバンクの条件ではない
2 メインバンクとサブバンク以下とを明確に分別する
どうぞ、ご一読下さい。
1 借入残高だけがメインバンクの条件ではない
中小企業経営者に、「御社のメインバンクはどちらになりますか?」とお尋ねすると、ほとんどの経営者の方が「当社のメインバンクは○×銀行ですよ」と即答されます。
中小企業にとっては、メインバンクは資金調達の要で、極めて重要な存在です。
ところが、会社側が○×銀行をメインバンクと考えていても、必ずして○×銀行側が「当行が貴社のメインバンクであることは間違いありません」と認識してもらっているかは保証の限りではありません。
この際、メインバンクとは何なのか? メインバンクの定義とは何か?について掘り下げてみることにします。
メインバンクの定義として、一番分かりやすい条件が「借入残高が最も多い銀行」です。
これは分かりやすくて、単に借入残高だけではなく、信用保証協会の保証残高が最大であることや、不動産等の担保を入担していることなども併せて条件となります。
次に重要な論点が、流動性預金(当座預金や普通預金等のこと)の平残(平均残高)が最も多いことと、流動性預金にお客様からの入金が入っていること、そして総合振込や給与振込(キュウフリ)がなされていることが挙げられます。
流動性預金は、金融機関にとっては、調達コストの安い(当座預金の場合はゼロ)の美味しい預金なので、流動性預金の残高が大きくなればなるほど、営業店(支店等)の収益向上に直結します。
また、総合振込や給与振込が行われることによって、金融機関には手数料(「役務収益」と呼ばれます)が落ちるので、流動性預金の平残と併せて、二度美味しいことになります。
よくあるケースが、元々のメインバンクの融資を別の金融機関が肩代わりしたことによって、融資残高ベースではメインバンクになったものの、経理担当者としては、従来からの旧メインバンクのネットバンキングの方がなれていて使い勝手が良いと言うことで、総合振込や給与振込が旧メインバンクに残ったままとなっているケースが見受けられます。
これでは、旧メインバンクから融資を肩代わりした銀行からすれば、流動性預金には、返済用の資金しか滞留しないため、本部の与信所管部署からは稟議承認に際しては、総合振込、給与振込を当行に移して、流動性預金平残を引き上げることといった条件が付されることになります。
このように、メインバンクの条件は、必ずしも融資残高のみで決するものでは無いことを中小企業経営者は知っておく必要があるのです。
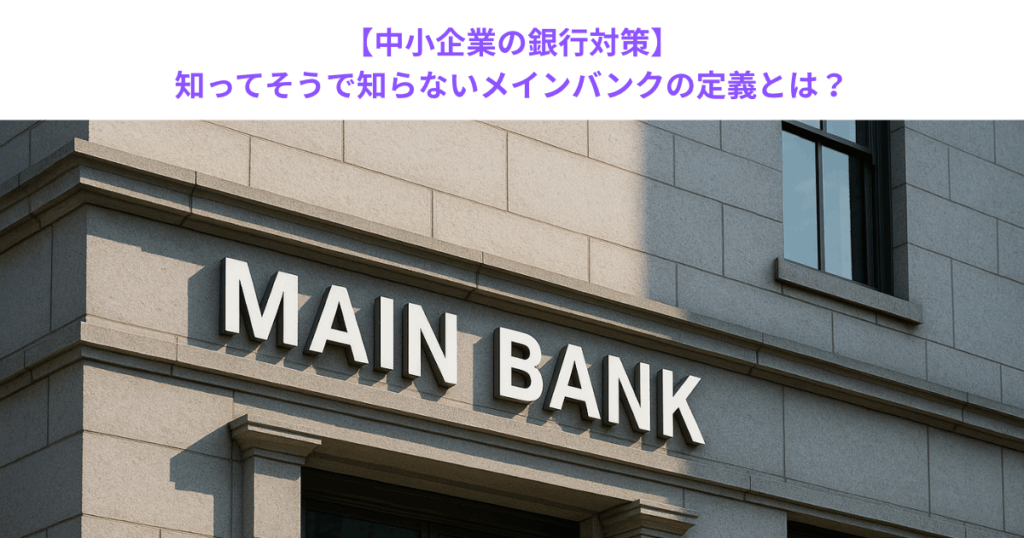
2 メインバンクとサブバンク以下とを明確に分別する
ここまでザクっとメインバンクの定義について触れてきました。
次に重要なことは、先ほど触れたように、メインバンクを取引上明確化して、サブ行以下にも、「メインバンクは○×銀行やな」と認識させることが重要です。
融資残高が最も多いことだけではなく、信用保証協会の保証付きはメインバンクで最優先で取り組むこと、不動産等の担保を入担するのはメインバンク、メインバンクの流動性預金を引き上げ、総合振込、給与振込をメインバンクで行うことで、メインバンクを明確化することが重要です。
そして、預金についても、できれば借入金の残高シェア見合いで置くことが理想的です。
そのようなことで、メインバンクとサブ行以下を序列化させることが大切です。
メインバンクは平時にはその重要性が曖昧になってしまいがちですが、コロナ禍やリーマンショックといった非常事態には、メインバンクの役割が極めて重要になります。
例えば、バンクミーティングの開催が必要になった際には、バンクミーティングの席上で、メインバンクが、サブ行以下に旗を振ってもらって、メインバンクに「当行がメインバンクとしてしっかり支えますので、他行さんも協調してもらえるよう、お願いします」と音頭をとって貰えば最高です。
中小企業経営者は、常日頃から、メインバンクを重要視し、サブ行以下よりもより丁寧な対応が必要となるのです。

