【中小企業の銀行対策】取引金融機関との対話が経営者の仕事であると断言できる理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、取引金融機関との対話が経営者の仕事であると断言できる理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 中小企業にとって金融機関は最大の資金の出し手である
2 経営者は金融機関との対話を他人任せにしてはいけない
どうぞ、ご一読下さい。
1 中小企業にとって金融機関は最大の資金の出し手である
私、北出が代表を務めている北出経営事務所は、中小企業の銀行対策に特化している経営コンサルタント事務所です。
弊所のお客様は、全て、非上場の中小企業で、上場企業とのお付き合いは残念ながらありません。
そこで、考えるのが、中小企業と、上場企業や大会社との差です。
両者の最大の差は、資金調達の手段にあると、北出は勝手に考えています。
上場企業は、不特定多数の株主さんから株式を購入してもらうことで、株主さんに資金の出し手になってもらいます。
投資家から直接資金を調達する資金調達を「直接金融」と言います。
これに対して、中小企業の場合、成長企業で上場近くともなれば、ファンドが上場前でも資金を拠出してくれて、株主に名を連ねてくれますし、あるいは、事業に成長性があると認められれば、中小企業育成投資のような半官半民のファンドに少額出資を求めることができるかもしれません。
ところが、世の中のほとんどの中小企業は、資金調達源を事実上、金融機関に依存しています。
いくら、経営者が、「俺は銀行嫌いなのだ」と嘯いてみても、直接金融で資金調達ができるわけでもないので、資金が必要ということになれば、取引金融機関に「お願いします」と頭を下げることになってしまいます。
世の中のほとんどの中小企業にとって、取引金融機関は最大の資金の出し手であって、重要なステークホルダーであることは間違いありません。
もちろん、「うちの会社は銀行から資金調達せずにクラウドファンディングに取り組むのですよ」という経営者がいるかもしれませんが、いざクラウドファンディングということになると、よほどユニークな事業でない限り、軒並み控える他のクラウドファンディング案件と差別化するのは簡単なことではありませんし、クラウドファンディングで調達できる金額も数百万円というのが相場です。
加えて、クラウドファンディングの事業者に支払う手数料とて決して安価なものではありません。
中小企業にとってクラウドファンディングはあくまでも資金調達の補助的な手段に過ぎず、資金調達のメインストリームにはなり得ないのです。
このように、中小企業にとって、金融機関は最大の資金の出し手であることは間違い無いのです。
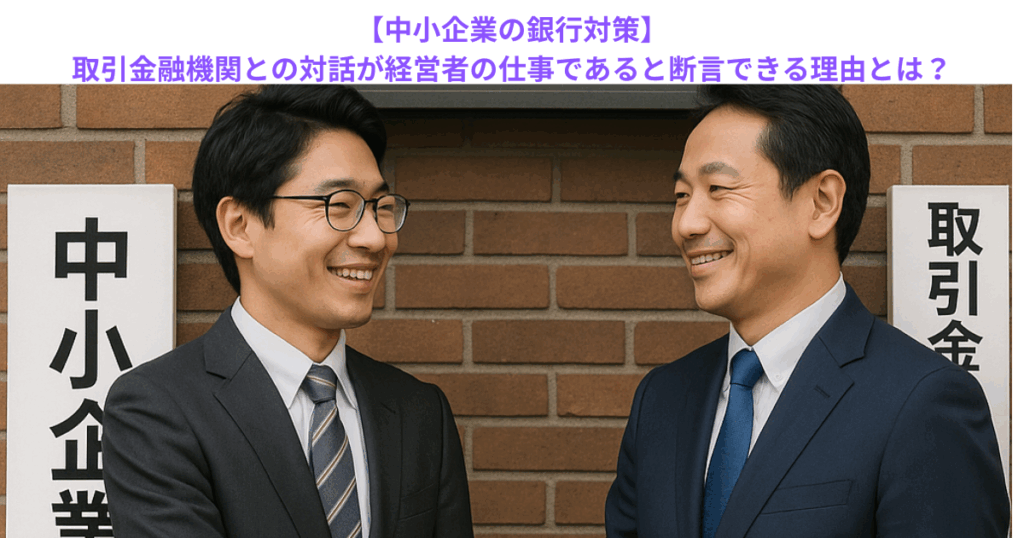
2 経営者は金融機関との対話を他人任せにしてはいけない
中小企業の中でも「中」位の中小企業や中堅企業の場合、経理部長がいて、普段の銀行取引の実務は経理部長が仕切っているケースが多く見受けられます。
他方、例えば、決算報告の場合、計数的な実績について経理部長が詳しい場合がありますが、取引金融機関の担当者、あるいは役席者や次席、部店長が同席する場合では、現進行年度の経営方針や営業戦略、中長期的な会社のヴィジョンについての話題となることも珍しくありません。
そのような会社の戦略的な領域に、経理部長であっても(それは俺の守備範囲を越えてるんやけど)と当惑してしまうことが想定されます。
ここぞという場合には、経営者自らが自分の言葉で、会社の戦略的な領域について語る必要があることは言うまでも無いことです。
現実に、上場企業の株主総会の議長は、代表権のある社長が務めます。
常日頃から、会社の株式を保有してくれて、かつ、中長期的に長く株式を持って欲しいという想いを社長が株主に向けて、共感を得ることができて、総会をシャンシャンで終わらせることができる面もあります。
非上場の中小企業・中堅企業の場合、上場企業の株主に替わる存在が取引金融機関ということができるかもしれません。
上場企業の株主と同様、中小企業経営者は、取引金融機関への対応を自ら行うことが極めて重要です。
中小企業経営者は、取引金融機関を最大の資金の出し手として重要なステークホルダーであることを認識して、丁寧に取引金融機関への対話を続けていくことが必要なのです。

