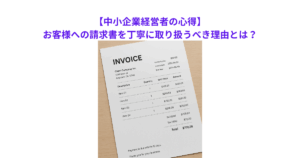【中小企業の銀行対策】歩積両建が禁止されている理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、歩積両建が禁止されている理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 保全がない丸裸の融資が金融機関にとってはリスク満載なのは理解できる
2 歩積両建はいまだになくなっていない
どうぞ、ご一読下さい。
1 保全がない丸裸の融資が金融機関にとってはリスク満載なのは理解できる
地域金融機関の合従連衡が随分進みました。
地方によっては、県域単位でトップのシェアを握る地銀と地域シェア2位の第二地銀が持ち株会社方式で経営統合したり、あるいは合併して一つの銀行に集約されていたりして、地域単位で明らかに地域金融という市場が寡占化してしまって、金融機関相互の健全な競合が阻害されてしまっているケースもなきにしもあらずです。
一方、弊所が拠点を置いている大阪は、関西の地場金融機関の融資獲得競争が激しい中、関西2府4県以外に本店を置く地方銀行が大阪市内を中心に営業店を構えていて、金融機関相互の競合が熾烈を極めています。
大阪に営業店を構えている関西地場以外の金融機関は、リテール業務を行わず、雑居ビルの一角に事務所を置いて、カウンターもないような営業店が存在します。
大阪のような金融機関相互の競合が熾烈を極める中、後発組の関西地場以外の金融機関が新規融資先を獲得するのは容易なことではありません。
信用保証協会の保証枠や担保は、元々の関西地場の金融機関がメインバンクとして押さえ切っています。
このため、後発組の関西地場以外の金融機関が大阪で新規融資先を獲得する場合には、「担保を下さい」などと生ぬるいことを言っているわけにはいきません。
このため、「担保は結構です。当行のプロパーにて対応させて頂きます」ということになってしまいます。
とはいえ、それでは、保全(万が一不良債権化した時どのように債権回収するかという金融機関の視点)面が丸裸となってしまって、融資先と倒産したり支払不能となってしまった時には、ほぼ全額が貸し倒れてしまいます。
本店を置く地元の本部の与信所管部門(融資部や審査部)からすると、保全が丸裸ということはそう簡単に容認できることではありません。
この場合、例えば、30百万円の新規融資取引を行う際、40百万円融資を実行して、同時に10百万円を定期預金に縛ってしまうことで一定の保全を確保することができるようになります。
本来、融資先中小企業が求めていた融資金額30百万円であったにもかかわらず、融資額を40百万円に増やして、10百万円を定期預金で事実上拘束することを「歩積両建」といいます。
昔はさることながら、現在は金融庁が「歩積両建」を金融機関に禁止する行政指導をしています。
「歩積両建」は過剰債務の温床となることに加えて、10百万円の定期預金が拘束されてしまい、10百万円を運転資金に充当することもできません。
このように、「歩積両建」は金融機関が融資先中小企業に対して優越的地位にあることから成立することで、中小企業経営者からすれば、「歩積両建」は決して容認できるものではないのです。

2 歩積両建はいまだになくなっていない
このように、金融機関を管理監督、所管する行政庁から「歩積両建」を禁止されているにもかかわらず、金融機関激戦区の営業店では、いまだに「歩積両建」がいまだになくなっていないという現状が歴然と存在します。
このため、決算書を見ると、借入金も多いけれど、固定性預金(定期預金、積立定期や定期積金)の残高も相当額に及んでしまっていて、資金効率の悪さが目立ってしまいます。
また、借入残高が多いため、毎期支払利息が相当金額に上っていて、金利上昇局面であることも相まって、支払利息が収益圧迫要因となっているケースがなきにしもあらずです。
そのような状況に陥っている中小企業経営者は、頭ごなしに金融機関に対して、「『歩積両建』は行政庁から禁じられている」と怒鳴ってしまうといきなり角が立ってしまうため、消費税の確定分や中間納税時に合わせて納税資金として、正式には質権設定されていない固定性預金を解約していくことで、「歩積両建」を徐々に解消していくことも検討事項です。
中小企業経営者は、「歩積両建」の意味を正しく理解をして、金融機関との取引をあるべき姿にしていく必要があるのです。