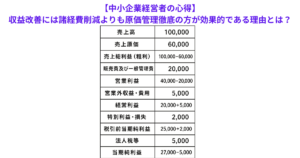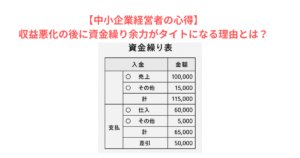【中小企業の銀行対策】取引金融機関担当者と揉めてはいけない理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、取引金融機関担当者と揉めてはいけない理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 人間なので好き嫌いは必ずある
2 個人対個人ではなく組織対組織で付き合うべき
どうぞ、ご一読ください。
1 人間なので好き嫌いは必ずある
中小企業であっても、取引金融機関から複数の融資を受けていて、入出金の実績もそこそこあれば、外回り(渉外係、営業課、得意先課などなど)の銀行員が担当者としてつきます。
彼ら彼女らは、既往の融資を管理したり、ニューマネーの要請があった時に行内の手続きを進めて、最終的に稟議書の起案をします。
一昔前と違って、外回りの担当者も女性の数が増えて、彼女らが同期の男子行員と共に、数字を負って融資先を回っています。
ジェンダー平等なのか、女性の社会進出を感じさせられます。
一方、担当してもらう中小企業経営者としても、取引金融機関の担当者がどのような人間にあたるのか、気になるところです。
通常、担当者ベースでも、3年から5年程度で人事異動や掛替などで、担当者が変わっていきます。
中小企業の場合、若手や中堅が担当することが多く、場合によっては、「外回りになりたてです」みたいな若葉マークの人が担当することも珍しくありません。
「もはや銀行は斜陽産業である」という向きもありますが、それでも、少なからぬ大卒新卒者が銀行を就職先として入行します。
男性、女性を問わず、新人、中堅を問わず、中小企業経営者とすれば担当者の全てとソリがあう保証は何もありません。
担当替えから数ヶ月もすると、すっかりと打ち解けて、仕事の話だけではなく、プライベートの趣味の話がマッチすることもあります。
一方、「あいつ、気に入らんやつや」と生理的に受け付けないようなケースもなきにしもあらずです。
当たり前ですが、生身の人間同士ですから、好き嫌いがあって当然です。
とはいえ、担当者ベースでは、中小企業経営者が年長の場合が多いため、中小企業経営者の方がちょっと大人になって、むしろ彼ら、彼女らの目線に降りていくことが必要かもしれません。

2 個人対個人ではなく組織対組織で付き合うべき
そうは言っても、やや口調が高飛車であったり、仏頂面ばかりの担当者がいないとも限りません。
しかしながら、そこで、「おい、お前、態度悪いやないか!」と中小企業経営者がキレるようなことは絶対あってはなりません。
彼ら、彼女らは、一担当者にすぎず、決裁権限は何もありません。
役席や、次席、部店長(支店長)、場合によっては本部の与信所管部署の意向をそのまま伝えているメッセンジャーのような担当者もいないわけではありません。
少なくとも、彼ら、彼女らには何の権限がないことは間違いないのです。
このため、中小企業経営者としては、彼ら、彼女らを組織の人間として認識して、個人対個人ではなく、組織対組織のお付き合いと割り切ることが重要であり、「おい、お前、態度悪いやないか」とキレずに済む方策でもあります。
中小企業経営者は、万が一、ソリが合わない担当者があった場合には、「短ければ3年、長くても5年の辛抱」と割り切って、担当者との信頼関係構築に努める必要があるのです。