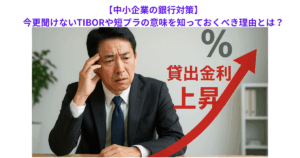【中小企業の銀行対策】予算の立案と実行が収益改善の鍵となる理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、予算の立案と実行が収益改善の鍵となる理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 予算の立案によって部署別のKPIが明確となる
2 どんぶり勘定を放置していては収益改善は実現できない
どうぞ、ご一読下さい。
1 予算の立案によって部署別のKPIが明確となる
取引金融機関にリスケジュールを要請したり、赤字が累積して実態ベースでBS上で実質債務超過に転落してしまうと、曲がりなりにも経営改善計画を策定して、それを実行に移していくことになります。
収益改善計画は、期間3年から10年間が一般的で、現進行年度を計画0年目とした毎期の収益計画(PL)とBSの改善を立案するもので、具体的な取組をアクションプランに落とし込むというのが一般的です。
本来の場合、収益計画を月次に落とし込んで、月次で進捗管理をするモニタリングを行うことが理想なのですが、モニタリングが半年に一回になったり、年1になったりして、モニタリングが不十分で、決算を締め上げて、蓋を開けてみたら、計画値に対して実績値が未達に終わるというケースがなきにしもあらずです。
このような事態を防ぐために、弊所では、お客様の中小企業に対して、現進行年度の収益計画を月次に落とし込んで、月次で着実に収益計画を達成していくことを推進しています。
月次で収益計画を落とし込むことによって、営業部門、製造部門、管理部門といった部署別で達成すべきKPIを明確にするという効果があります。
もっといってしまえば、今月の予定売上高が明確になるので、営業部門の売上目標が明確になります。
売上に対して、主要原材料の仕入高のリミットを設定することによって、原材料の「買い過ぎ」を防止して、売上総利益率の計画値を達成することへの製造部門の目的意識を明らかにすることができます。
このような取組は、まさに予算を立案して、予算を実行していくというプロセスに他なりません。
現実的には、受注時にトップラインがバチっと決まる建設業では、実行予算管理が当たり前になっています。
このような取組を建設業だけではなく、製造業等他の業種、業態にも積極的に取り込んでいくことによって、収益計画に対する実績値が下ブレることを防止する効果があるのです。
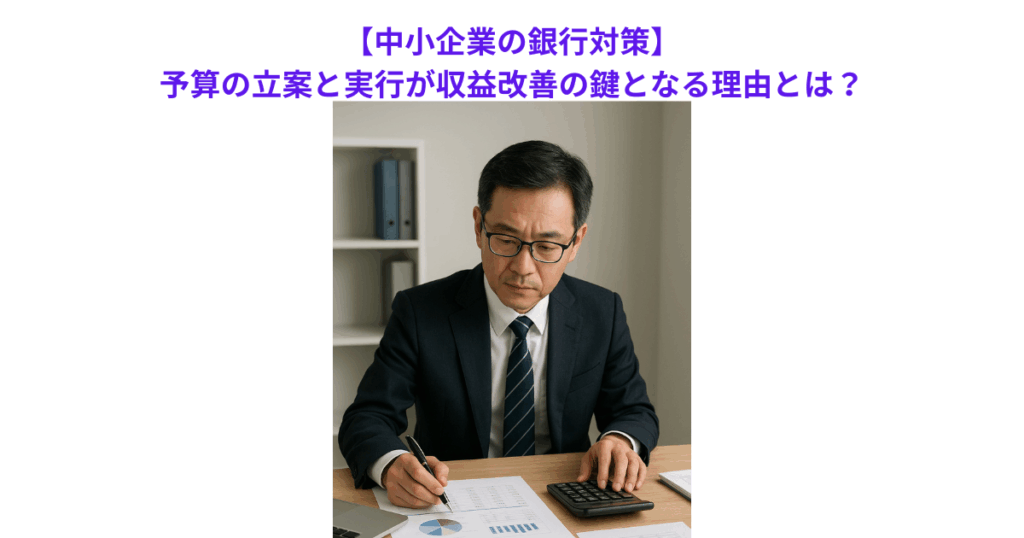
2 どんぶり勘定を放置していては収益改善は実現できない
とはいえ、実際、月次で立案した予算を現場に下ろして、予算を実行していく段になると、現場ではアレルギー反応が起こる可能性がなきにしもあらずです。
「社長、そこまでやらんとダメなんですか?」
そういう反応が従業員が出てきても不思議でもなんでもありません。
しかしながら、いわば、どんぶり勘定を放置して、蓋を開けてみたところの出たとこ勝負では、収益改善が思うように進まないというのが現実です。
また従業員の側からしても、賃上げに関心があるのと同時に、会社が安定した収益体質を維持できるようになり、「安心して働ける」ようになることへのニーズは決して小さくはありません。
つまり、経営者の側も、従業員側にも、収益を改善するということに関しては、利害の対立がないのです。
中小企業経営者は、自らの言葉で、安心して働ける場をしっかりと提供していくことを従業員にしっかりと伝えて、利害が一致していることを共有する必要があります。
取引金融機関、中でも、メインバンクにしても、月次モニタリングを実施して、社内でも部署別のKPIを明示してその達成に向けて、経営者も社員も一体になって取り組んでいることを両手を挙げて歓迎してくれること、間違いありません。
中小企業経営者は、「脱・どんぶり勘定」への決意で腹を括って、収益改善に取り組み続ける必要があるのです。