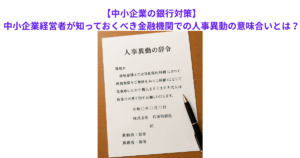【中小企業の銀行対策】サブ行との理想的な距離感とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、サブ行との理想的な距離感について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 メイン行とサブ行を切り分ける
2 サブ行の取組スタンスを見極める
どうぞ、ご一読下さい。
1 メイン行とサブ行を切り分ける
中小企業であっても、メイン行と日本政策金融公庫との取引のみで、事実上の一行取引であるケースは基本的に多くはありません。
年商3億、4億円程度の中小企業でも、メイン行(民間金融機関)、サブ行(民間金融機関)と日本政策金融公庫の3行取引といったケースが多いように北出の肌感覚では感じています。
メイン行とサブ行の民間金融機関2行の取引の場合でも、両行がせめぎ合っていて、事実上並行メインとなっているケースもなきにしもあらずです。
もちろん、事実上並行メインであれば、両行ともに取引深耕を狙っていて、場合によっては、他行の肩代わりを提案してくることもあります。
一方、並行メインは、業績が順調であれば問題はないのですが、経営改善局面になった時、並行メインの両行は、「当行はメインではありません。他行さんにご相談されてはどうですか?」と手のひらを返してくることもないとは言えません。
メイン行、サブ行との切り分ける指標として、融資残高の「残高シェア」が挙げられます。
民間金融機関2行と日本政策金融公庫との3行との間の理想的な残高シェアのイメージが、メイン行50%、サブ行30%、公庫20%というところです。
このくらいの残高シェアですと、メイン行は「うちがメイン行でしっかり支えさせて頂きますよ」となり、サブ行は、「メインさんは向こうですが、うちにもちゃんと声かかけて下さいね」となることが多く、各行ともに、角がたたないというわけです。
メイン行とサブ行とをしっかりと切り分けることは、中小企業にとっては、円満な銀行取引に必要なことなのです。

2 サブ行の取組スタンスを見極める
金融機関の営業店では、店内の会議で、ザクっと言ってしまうと、部店長(支店長等)が融資先毎に取組スタンスを決めます。
「ここは他行を攻めて、シェアを上げて取引深耕すること」とか、「あそこはあかん、撤退スタンスやな。ニューマネーは出すな。どんどん約定返済を進めていけ」とかいう具合です。
もしも、サブ行でイケイケ支店長が着任して、イケイケ支店長の指示を受けた担当者は、「社長、うちでどんどんやらせて下さい。メインさんの肩代わり、やりますよ。金利勉強させてもらいますから」と甘い言葉で誘い水を出してきます。
ところが、こういう手合いの誘いに安易に乗ってはいけません。
そもそもメイン行との取引は創業時代以来続いていたりするので、これまでの取引実績も豊富です。
また、融資だけではなく、お客様からの入金がほとんど入っていたり、総合振込や給振もやっています。
融資の肩代わりは物理的に可能ですが、お客様の入金を変えるとなると、お客様の経理担当者に手間を取らせますし、振込先が変わるとなると、取引先が警戒する可能性がなきにしもあらず。
取引先の社長からすれば、「あそこ、銀行と揉めたな。あの会社、そうそう長ないかもしれん」となると、不必要な信用不安が立たないとも限りません。
定番となっているのは、イケイケの支店長の後は、審査畑が長く、ブレーキを踏むのが大好きな慎重な支店長が着任する可能性が高いので、サブ行からの一時の甘い言葉に乗ってしまうのはやや危険なのです。
中小企業経営者は、サブ行が本気で肩代わりを取りに来ているのか、サブ行の取引スタンスを慎重に見極める必要があるのです。