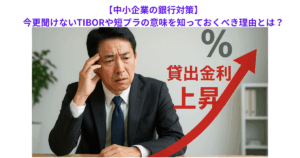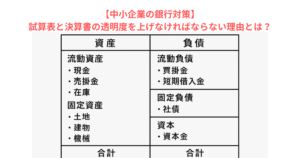【中小企業の銀行対策】取引金融機関担当者と信頼関係を築くためのコツとは?
今日は、中小企業の銀行対策として、取引金融機関担当者と信頼関係を築くためのコツについて考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 債権債務に関する事柄は金融機関担当者の方が上である
2 業界ネタを取引金融機関担当者に教えてあげよう
どうぞ、ご一読下さい。
1 債権債務に関する事柄は金融機関担当者の方が上である
取引金融機関から一定程度の融資取引があるような中小企業には、取引金融機関の外回り(渉外係、営業課、得意先課など)の担当者がつきます。
担当者は取引金融機関営業店の都合で決まり、基本的に中小企業側には担当者を選択する余地はありません。
このため、どのような担当者が就くのか中小企業経営者にはわかりません。
一般に、外回りの担当者は、入行して預金や融資の内勤業務を一通り経験してから外回りになるので、入行して3年目の若手が担当者になることもあれば、30代中盤の中堅の担当者が就くこともあります。
銀行員といっても、どこまでいっても生身の人間なので、どうしても、中小企業経営者にとってみれば、ウマが合う担当者もいれば、「なんやこいつ、気に入らん奴やな」と思えてしまう担当者が割り振られることも十分ありえます。
ここで、重要なことは、いかに「なんやこいつ!!」とウマが合わず、気に入らない担当者であったとしても間違っても、営業店(支店等)に乗り込んで、次席(次長、副支店長)や部店長(支店長等)に直談判して、「うちの担当者、別の人間に交代してもらえませんか」と訴えることは絶対に控えなければなりません。
直談判された次席や部店長からの自社への心証は間違いなく悪くなってしまいますし、そもそも、担当者本人の顔が潰れてしまいます。
まかり間違って、担当者を替えてもらったとしても、新担当者は、間違いなく(この社長、気付やなあかんな)と端から構えてしまいます。
また、担当者との話題のほとんどは、会社業績に関することと、融資に関することです。
融資に関することはどこまでいっても、債権債務のことなので、ちょっと中小企業が勉強したくらいでは、担当者には勝つことができません。
債権債務に関することは、金融機関役職員の方がどう見ても、上であることは間違いないことです。
このため、間違っても、融資に関することで、担当者と見解が合わなかった場合でも、担当者にキレるようなことはぜ隊に避けなければなりません。
このようなことは、中小企業経営者として、取引金融機関担当者と面談するときには、十分踏まえておく必要があるのです。

2 業界ネタを取引金融機関担当者に教えてあげよう
このように言ってしまうと、「銀行員には、ずっとヘイコラせなあかんのか!」という中小企業経営者からのお叱りを受けるかもしれないので、次は、別の話をします。
どの中小企業でも、それぞれの業界、業種、業態の中で営業活動をし、収益を出しているわけですが、意外にも銀行員は、個別の業界の事情についてそれほど精通しているわけではないのです。
もちろん、稟議書を書かなければならないので、一般論としての業界慣習は把握していても、業界ならではの業界慣習や業界ネタにはあまり強いというわけではありません。
例えば、マンションの建築工事を主体とする建築業者の場合、一般住宅を建築するのとは違って、独特の業界慣習が存在したりするものです。
また、製造業でも、自動車のエンジン部品の中の「この部品」を製造している場合、アッセンブリーを行う自動車メーカーとは違う職人技があったりするものです。
取引金融機関の担当者が、勉強好きで、興味津々の人物であれば、「社長、社長との技術てすごいやないですか。もっとお話し、聞かせて下さい」ということになって、信頼関係構築に大いに貢献することは間違いありません。
中小企業経営者は、自社の業界ネタに精通しているので、せっかく経営者自身が持っている業界ネタに関する情報を積極的に取引金融機関担当者に共有してあげることは、担当者にとっても無形の資産になって、きっと喜んでくれるに違いありません。
中小企業経営者は、取引金融機関担当者と信頼関係を構築するため、自らが持っている自社の業界ネタをどんどん取引金融機関担当者に共有させてあげる必要があるのです。