【中小企業の銀行対策】金融機関の融資先評価は決算書だけで決まらない理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、金融機関の融資先評価は決算書だけでは決まらない理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 決算書は最重要だが全てではない
2 融資先表は総合的に判断される
どうぞ、ご一読下さい。
1 決算書は最重要だが全てではない
「うちの会社は、メインバンクからどのように評価されているのだろう?」
資金調達を金融機関に依存している非上場中小企業の経営者にとっては、興味津々の永遠のテーマと言えます。
融資先の評価は、大きく分けると2つの観点から構成されます。
1つ目が、定量的要素と呼ばれるもので、簡単に言えば、数値で表現できる要素で、その最も重要で代表格であるのが決算書です。
PL上できっちり稼げいるのか、BS上では資産は健全で、実質資産超過を維持できているかが債務者区分、信用格付に直結するものです。
定量的要素は決算書以外に、試算表、資金繰り表や受注明細といったものが挙げられます。
2つ目が、定性的評価と呼ばれるもので、決算書等数値では表現できない要素のことを言います。
定性的要素の代表格とすると、経営者の力量、技術力、取引先の質などが挙げられます。
定量的要素と定性的要素の評価ウェイトとすれば、北出の肌感覚からすれば、定量的要素7〜8割、定性的要素2〜3割というところですが、場合によってはより定量的要素の方がより高めのウェイト付けがされるケースが見受けられます。
定量的要素の方が定性的要素よりもより重要視される理由としては、定性的要素は、どうしても担当者の主観が入ってしまうことがあって、より保守的に融資先を評価しようとすると、金融機関としては、定量的要素を重視してしまいがちになるのはやむをえないところがあります。
このように、融資先評価は、決算書が最重要要素ですが、決算書が全てではないのです。
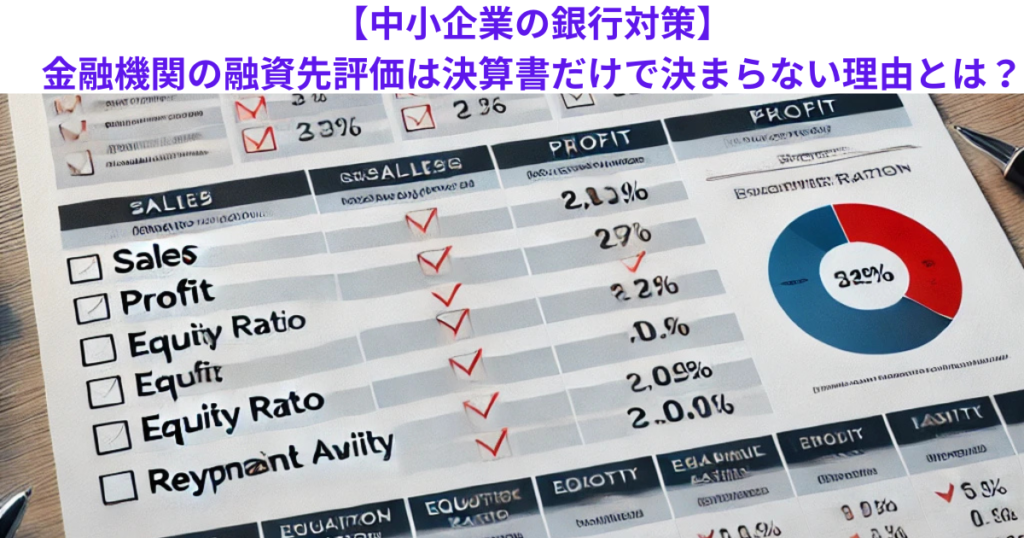
2 融資先表は総合的に判断される
このように、金融機関の融資先の評価は、大きく分けて、定量的要素と定性的要素で構成されることを申し上げました。
この2つの要素に加えて、金融機関の融資先評価に関わる要素として、融資先の取引内容も加味されます。
取引内容の筆頭格が、融資残高と預金残高です。
融資残高によって、金融機関は所定のレートで貸出金利息を受け取り、これが金融機関にとっての「売上高」に相当します。
預金についても重要で、特に、当座預金や普通預金といった調達コスト(金融機関側の目線)の安い(あるいはタダ)の預金の平残が多ければ、金融機関としては、安い資金を仕入れることができて、調達コストを低減することができます。
また、総合振込や給与振込の件数次第で、手数料が金融機関に落ちます。
ゴールドのクレジットカードの法人カードの加入状況や、代表者個人の投資信託や保険の取引内容も加味されます。
このように、金融機関の融資先の評価は、かなりの程度で多岐にわたります。
中小企業経営者は、特に、メインバンクに対しては、預貸以外の総合振込や給与振込だけではなく、ゴールドカードや個人の取引も考慮されていることを認識する必要があるのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご覧下さい。

