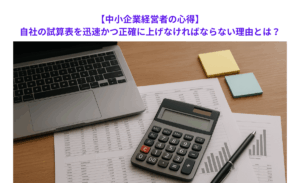【中小企業の銀行対策】取引金融機関から定期預金の預入をお願いされた時の理想的な対応とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、取引金融機関から定期預金の預入のお願いをされた時の理想的な対応について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 規模の大きな金融機関ほど預金獲得に熱心である
2 個人預金で協力するのが妥当である
どうぞ、ご一読下さい。
1 規模の大きな金融機関ほど預金獲得に熱心である
金融機関から融資を受けている中小企業経営者の身からすると、大手行と地方銀行から昨年秋以降2度に渡る短プラを引き上げられていることで、金利の上昇を実感しているはずです。
一方、金融機関の貸出利息の引き上げ幅には及ばないものの、預金金利の利率も引き上げられています。
普通預金であっても、そこそこの平残(平均残高のこと)を維持していれば、直近ですと8月半ばにちょっとした預金金利がついてきました。
貸出利息にせよ、預金利息にせよ、中小企業経営者にとっては、「金利のある世界」を実感できる状況です。
金融機関では、預金金利の上昇によって資金調達コストは上がっていますが、資金調達コストの上昇幅以上に、貸出利息の引き上げ幅が大きいため、多くの金融機関がデフレ下では見られなかった好決算を弾き出しています。
実際、金融機関では、預金の獲得に注力しています。
デフレ下では、預金を解約させてでも、投資信託等の販売によって預かり資産の増加に力を入れて、手数料収入(金融機関では「役務収益」と呼ぶ)によって収益アップを目指してきましたが、金利の上昇局面を迎えて、預金の獲得に躍起になってきています。
預金獲得により一層力を入れている金融機関は総じて預貸率が高いことが共通しています。
預貸率とは、融資残高を預金残高で割ってパーセンテージ表示したものです。
例えば、預金残高5兆円に対して、融資残高4.5兆円であれば、預貸率は90%となります。
預貸率が高い金融機関ほど、一般預金者から広く集めた預金を自前で融資として運用できていることなので、預貸率の高い金融機関は資金運用力が高いということができます。
預貸率が100%を超える金融機関の場合、融資に回せる資金が預金だけで賄うことができないので、銀行間で資金をやり取りする金融市場から資金を調達する必要があります。
預貸率が100%近かったり、100%超となっている金融機関では、市場から借りてくるのではなく、自前で預金を獲得することで、より総資金利鞘(一般企業でいう売上総利益に相当します)を高めることができます。
他方、預貸率が低い規模の小さな金融機関では、積極的に預金を獲得しようとはしません。
預貸率は、意外にも金融機関の体力や運用力を示す重要な指標なのです。
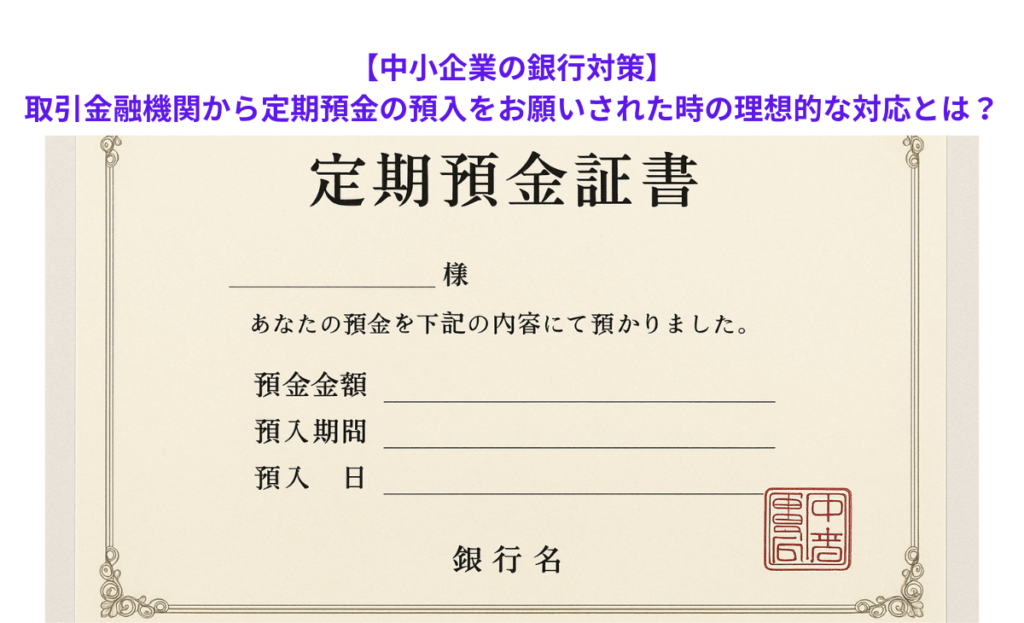
2 個人預金で協力するのが妥当である
それでは、実際に、取引金融機関担当者から「社長、奥さん、なんとか定期預金をお願いできませんでしょうか?」とお願い営業をされた場合、経営者としてどのように対応すべきでしょうか。
まず、特に、お願いしてきた金融機関がメインバンクである場合、ゼロ回答は絶対いけません。
外回りの担当者には、本部の営業推進部署から営業店(支店等)に降りてきた数字から、目標(ノルマ)が課されます。
外回りの担当者は、「未達でした」というのは基本的に許されないので、念入りに見込み先を選定して、満を持してお願いにやってきます。
そこで、4番手や5番手行ならいざ知らず、メインバンクの外回り担当者からのお願いを蹴ってしまうと、後々双方に禍根を残してしまいかねません。
コロナ資金のような非常時対応をはじめとして、経営者からメインバンクに無理を聞いてもらうことも十分想定できるので、可能な限り、協力することが穏当です。
ただし、法人預金を定期預金で縛るのは、担保等で拘束されてはいないものの、突発的な資金繰りで定期預金を解約せざるを得ない事態も想定されます。
金融機関も法人預金よりも個人預金の獲得に注力するのが普通です。
このため、金融機関担当者から「定期預金をなんとかお願いしたいんですが・・・」と頭を下げられた時には、個人名義の個人預金を定期預金で協力するのが妥当です。
中小企業経営者は、銀行取引を単に融資を受ける際だけに重視するのではなく、常日頃から、外回りの自社の担当者とのコミュニケーションを取ることが重要なのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。