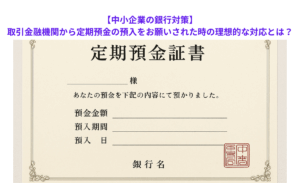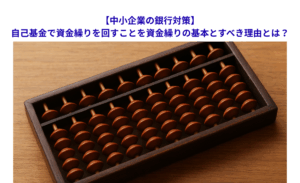【中小企業の銀行対策】「担保があるから借りられる」が幻想である理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、「担保があるから借りられる」が幻想である理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 保全は融資の可否判断の一要素でしかない
2 返済原資の捻出が融資実行の大前提である
どうぞ、ご一読下さい。
1 保全は融資の可否判断の一要素でしかない
中小企業経営者の中には、「うちの会社には担保に出せる不動産があるから銀行からおカネを引っ張れる」と考えている向きがあるようです。
確かに、担保に出せる物件があるということは、銀行から融資を受ける際、プラスに働くことは間違いありません。
ところが、「担保があるから借りられる」というのは実際には幻想にしか過ぎません。
なぜなのでしょうか。
金融機関が融資の審査を行う際、稟議手続きを踏みます。
金融機関営業店(支店等)の担当者が、稟議書を起案して、役席者、次席を経て、決済権限が営業店部店長(支店長等)にあれば営業店部店長が稟議を承認することで、融資が初めて実行に移されることになります。
融資の金額が大きかったり、債務者区分が正常先でない(例えばその他要注意先など)場合は、営業店部店長の意見が付されてから、本部の与信所管部署に稟議書が回されて、本部与信所管部署の承認を受けることになります。
中小企業経営者が、金銭消費貸借契約書にサインをするのは、融資の稟議が承認された後のタイミングです。
稟議書で融資の可否が審査される要素としては、大きく3つの項目が挙げられます。
一つ目が、「資金使徒」で、おカネの使い道です。
経常運転資金なのか、設備資金なのか、何に融資のおカネが使われるかという点です。
二つ目が、「返済原資」で、融資の実行後、着実に返済してもらえるかという点です。
三つ目が、「保全」で、万が一、融資先が倒産等の状況に追い込まれてしまった場合、どのように、融資した資金を回収するかという点です。
この3つの要素が揃って、初めて、金融機関では融資の稟議が承認されることになるのです。
つまり、「担保に出せる不動産がある」というのは、保全の観点なので、3つの要素のうち、1つの要素を満たすことに過ぎないのです。

2 返済原資の捻出が融資実行の大前提である
そもそも、金融機関は、不特定多数の預金者から預金を集めて、それを原資に企業や個人に資金を貸し付けているので、不良債権の発生は建前としては許されません。
このため、上記で申し上げた融資の三原則である資金使徒、返済原資並びに保全のうち、返済原資が最も重要視されます。
融資した資金は約定通りに回収するというのが金融機関の大原則です。
このため、運転資金にせよ、設備資金にせよ、返済に支障がないようなFCF(フリーキャッシュフロー)もしくは簡易CF(=経常利益ー法人税等+減価償却費)を捻出できていることが、返済原資の確保の大前提です。
返済の見込みのない融資が実行されてしまうと、担当者も部店長も、本部与信所管部署の調査役や審査役が背任罪と問われかねないのです。
先般報道された福島県の信用組合のような不正融資が明るみに出てしまうと、金融システム全体に影響が出ないとも限りません。
このようなことから、いくら入担できる物件があったとしても、FCFや簡易CFが返済に足りていない場合には、融資は謝絶されてしまうのです。
中小企業経営者は、金融機関の融資の審査の仕組みを正しく理解をして、資金調達に耐えうるような収益を創出できるよう、経営努力を継続しなければならないのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。