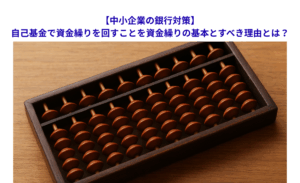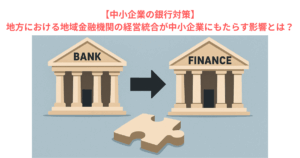【中小企業の銀行対策】労働争議が対金融機関にネガティブな影響を与えてしまう理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、労働争議が対金融機関にネガティブな影響を与えてしまう理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 支払った解決金は試算表に反映する
2 解決金支払はキャッシュフロー上百害あって一理なし
どうぞ、ご一読下さい。
1 支払った解決金は試算表に反映する
いつの頃からかよく判然としないのですが、少なくともここ十数年来、労働司法のトレンドが、労働者に優しく、会社側に険しい判断を下すようになっているように感じてなりません。
わたくし北出は、法律家ではありませんが、弊所のお客様の中小企業に於いて、時折発生するのが社員(元社員も含む)との労働争議の存在です。
よほどの事情がない限り、労働審判や民事訴訟に於いて、労働者側が会社側を訴えると、会社側に厳しい司法判断が下されているように感じています。
多くの場合、労働者側が社員としての地位保全を主張することによって、最終的に会社側が「解決金」を支払うことによって和解するようですが、労働争議に発展し、支払うこととなる「解決金」が、中小企業にとっては、資金繰りにネガティブな影響を与えてしまうことは珍しいことではありません。
実際、仮に、労働争議によって会社側が「解決金」を支払うことになったとして、それが中小企業の資金繰りに大きな影響を与えなかったとしても、取引金融機関に対しては、極めてネガティブな影響を与えてしまいます。
なぜならば、実際支払った「解決金」は試算表や決算書にしっかりと顕在化してしまうためです。
勘定科目としては、営業外費用の「雑損失」や、特別損益の「その他特別損失」として費用計上されるケースが大半ですが、当然、試算表や決算書に目を通した取引金融機関担当者は、「社長、この雑損失の中身は何ですか?」と質問をしてきます。
経営者としても、取引金融機関担当者の質問に対して、偽りをいうわけにはいきません。
元社員との間で労働争議があって、その解決金を支払ったのだけれど、これは一発キリの突発的な損失だと経営者が取引金融機関担当者に説明をすると、取引金融機関担当者は納得はするのでしょうが、「社長、今後は労働争議にならないよう、労務管理に注力するよう、お願いしますよ」と決してポジティブには捉えてくれません。
少なくとも、取引金融機関には、労働争議にかかる「解決金」は前向きな投資とは受け取らず、担当者から報告を受けた役席者や、次席、部店長も担当者に「おい、この先は注意して見とかなあかんぞ」と注意を促すことになってしまうのです。

2 解決金支払はキャッシュフロー上百害あって一理なし
仮に、労働争議が起こったとして、解決金の支払いによって労働者側と和解をし、以降債権債務の存在を主張しないことを合意したとしましょう。
また、解決金の金額自体も会社の資金繰りに大きな支障を与えないレベルにとどまったとしましょう。
それにしても、解決金は多くの場合、労働の対価ではなく、あくまで「解決金」であって、言葉は悪いのですが、中小企業経営者側からすれば、大切な会社のおカネをドブに捨てるのと変わりはありません。
前向きの投資でもなく、必要経費への支出でもない「解決金」の支払は、キャッシュフロー上から見ても、百害あって一利なしであることは間違いありません。
会社の持続性を高め、事業価値を高めていくためにも、労働争議は発生させてはいけないものです。
会社の資金繰り余力が低下してくると、経理担当者から他の社員に「うちの会社、危ないかもしれへんから、転職先探したほうがええで」となってしまうと、お昼休みに休憩室で転職雑誌が回し読みされるようになったりして、従業員の士気は下がり、モラルハザードも蔓延してしまいます。
中小企業経営者は、生産性アップ、省力化を推進できるような設備投資を行いつつ、社員全員が安心して働ける職場にできるよう、自社が儲かる会社にしていくことに邁進する必要があるのです。