【中小企業の銀行対策】「質の悪い借金」の意味を知る必要性とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、「質の悪い借金」の意味を知る必要性について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 悪い借金と良い借金の違いについて
2 質の悪い借金は実行後も中小企業を苦しめる
どうぞ、ご一読下さい。
1 悪い借金と良い借金の違いについて
とかく、借金といえば、世間的には決して良いイメージを持たれていません。
「借金が多過ぎて首が回らない」とか、「借金が多過ぎて、あの会社は潰れた」とか、とにかく、借金のイメージは一言で言ってしまうとネガティブに尽きるというのが実際のところかもしれません。
とはいえ、借金を一絡げてにして、悪と決めつけるのは、少し乱暴すぎます。
一般的な中小企業は、商取引上、どうしても力関係が弱くて、回収サイトが長くなる一方、支払サイトは短くなりがちです。
わかりやすくいえば、なかなかお客さんから払ってもらえない一方、仕入先や外注先からは「先にはろてくれや」と支払を督促されるという弱い立場です。
このように、相対的に力関係が弱い取引状況下で、受注が増加すると、とかく資金繰りがアップアップになります。
そこを解消するのが「増加運転資金」という借金で、取引金融機関から増加運転資金を調達することで、仕入先や外注先との取引実績を重ねていくと、取引上の信用が形成されて、仕入先からの支払条件が当月末締切、翌月15日であったのが、当月末締切、翌月末でOKになったりします。
こうなると、資金繰りは安定して攻めの商いに取り組むことができるようになります。
同様に、機械を買ったり、工場を増築したりするのに際して、設備資金を調達して、減価償却費を返済原資にできれば、工場のキャパは広がり、幅広くお客様からの受注に対応できるようになるほか、生産設備の増強によって省人化も実現できます。
このような「前向き資金」の借金は良い借金といえます。
他方、悪い借金の典型例が、後ろ向き資金需要に伴う借入金です。
支払遅延が発生しそうなくらい、資金繰り余力が低下している中、後ろ向き資金需要による借入金を借り入れると、流動負債の買掛金、未払金、未払費用を消し込むので精一杯となってしまいます。
このように、良い借金というのは、在庫、売掛金、あるいは固定資産等で借方に勘定科目が残ることが特徴です。
一方、悪い借金は、流動負債を消し込むだけで借り入れた現預金が消失してしまって、借方には何も残りません。
良い借金か、悪い借金かの判定は、借入金実行後に借方に何かしらの勘定科目が残るか否かで決するのです。
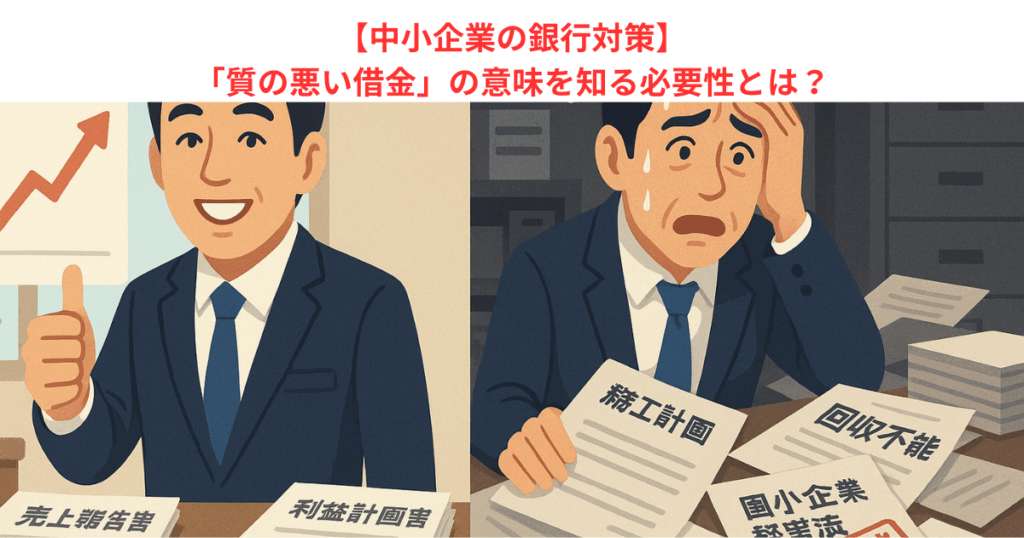
2 質の悪い借金は実行後も中小企業を苦しめる
質の悪い借金といえども、資金繰り余力が低下する中、「支払、どうしたものか?」と頭を抱えていた経営者にとっては、質の悪い借金はその時はまるで救世主のような存在です。
ところが、実際問題、取引金融機関に泣きついてやっとのことで質の悪い借金を実行してもらっても、その後も質の悪い借金は中小企業を苦しめる存在です。
なぜなら、質の悪い借金には借方に何も残らないので、いずれ現預金に生まれ変わっていく流動資産が存在しないのです。
また、通常、資金繰り余力の低下の背景には、その事前の段階での発生ベースの損益(PL)の悪化があるため、質の悪い借金の返済も加わって、資金繰りは厳しい状況が続いてしまうのです。
もちろん、原価高、人手不足の世間ですから、発生ベースの損益悪化はいつでも起こり得ます。
それに伴って、後からじわっじわっと資金繰り余力が低下していくことはやむを得ない面も否めません。
しかしながら、「世の中が悪いから」、「政治がアホやから」と片付けるのは簡単ですが、そのような中でもしっかりと儲けている経営者は着実にいるのです。
中小企業経営者は、外部環境の悪化を嘆く前に、自社の強み、弱みを把握して、常に成長軌道に会社を乗せて、質の悪い借金を回避し続ける弛まぬ経営努力が必要なのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。

