【中小企業の銀行対策】モニタリング(業況報告)を継続させるためのコツとは?
今日は、中小企業の銀行対策として、モニタリング(業況報告)を継続させるためのコツについて考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 モニタリングは取引金融機関との信頼関係構築への早道である
2 1回あたりのモニタリングに必要以上に時間をかけない
どうぞ、ご一読下さい。
1 モニタリングは取引金融機関との信頼関係構築への早道である
弊所では、お客様の中小企業経営者に、月次でお客様の会社の取引金融機関に対するモニタリング(業況報告)を基本的に行うようにしてもらっています。
多くの中小企業経営者にとって、取引金融機関の担当者と接する機会が、決算書提出時もしくは資金の要請を行う時に限られてしまいがちです。
もちろん、それで事足りといえばそうなのですが、取引金融機関の担当者の本音とすれば、「この社長は、自分の都合だけでアポイントを取ろうとしている」と不審に感じていないとも限りません。
取引は、あくまでも、会社と金融機関との間のことですが、実際には、会社は社長が資金調達の責任者であることが多いですし、金融機関担当者も生身の人間です。
結局のところ、どこまでいっても人対人との付き合いなので、肝心なことは信頼関係です。
このことは、銀行取引だけに限ったことではなく、大口の取引先にも同じことが言えます。
所詮、銀行取引も人対人であるわけなので、どうせならお互い、気の知れた存在であることに越したことはありません。
信頼関係構築には、実際に会って、前月の試算表、資金繰り表(に加えて、建設業であれば受注明細)を揃えて、モニタリングを定期的(弊所は、毎月モニタリングを推奨しています)に行うことが効果的なのです。
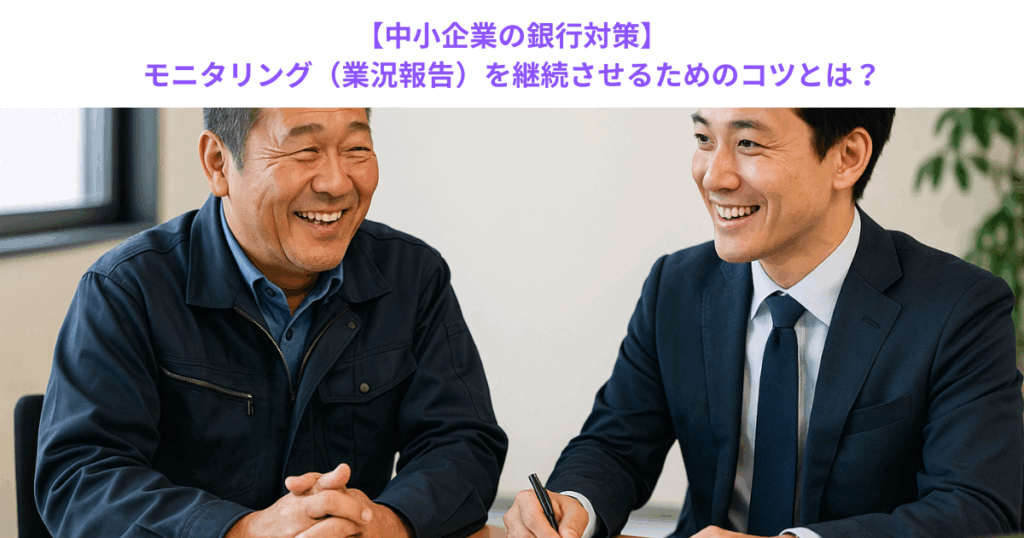
2 1回あたりのモニタリングに必要以上に時間をかけない
多くの中小企業経営者が、モニタリングの重要性を理解してくれるのですが、毎月モニタリングとなると「え、毎月なの?」と途端に顔を曇らせる中小企業経営者がいないわけではありません。
もちろん、中小企業経営者は、そこら辺のサラリーマンとは比べものにならないくらい多忙ですし、その位の事情はよくわかります。
なので、一回モニタリングに必要以上の時間を取らないように弊所ではしています。
モニタリングを始めてすぐの頃は何かとビジネスモデル自体や会社の強みを話したりするので、時間を少々とりますし、「毎月業況報告にお邪魔させて頂きますのでよろしくお願いします」と金融機関担当者に伝えると、社長の顔をまじまじと見て「毎月ご報告に来てくださるのですか」と少々驚いてくれたりします。
しかしながら、金融機関担当者の人間関係ができてくると、せいぜい、一回一行当たり30分もあれば十二分です。
3行お邪魔するとして、モニタリング自体90分、移動で30分とすれば、せいぜい2時間仕事で、午前中で終わらせることができます。
人間関係がしっかりできてくると、場を和ませるために雑談を交えたりする必要はなく、「今日はいい天気ですねえ」みたいな非生産的な会話は不要となります。
前月の試算表の数字を今月の進捗状況、向こう3ヶ月程度の業績見込みといったところを簡潔に伝えてしまえば十分です。
必要以上にモニタリングに時間を割かないことがモニタリングを継続させるためのコツなのです。
次にモニタリングを継続させるためのコツとしては、当たり前のことですが、来月のモニタリングの日程を決めてしまうことです。
業績が想定以上上振れて資金繰りの不安が遠のいたり、逆に、業況が想定以上に落ち込んだ時には、ついつい、経営者は、モニタリングから足が遠のいてしまいがちですが、来月の日時を確定させることで、ほぼ強制的にモニタリングを継続させることができるのです。
このように、お客様の会社の経営者と共に、モニタリングに同行している北出とすれば、毎月モニタリングは、対銀行対策には極めて有効です。
中小企業経営者は、自社の最大の資金調達源が取引金融機関であって、取引金融機関との信頼関係の構築のため、毎月モニタリングを実行してみる価値は十二分にあることを認識する必要があるのです。

