【中小企業の銀行対策】収益悪化と資金繰り余力低下との相関関係とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、収益悪化と資金繰り余力低下との相関関係について考えてみます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 資金繰り余力の低下要因は大きく2つである
2 収益が悪化すると後追いで資金繰りがキツくなる
どうぞ、ご一読下さい。
1 資金繰り余力の低下要因は大きく2つである
「資金繰りがキツくなってしまいまして・・・」と弊所、北出をご指名頂き、ご相談下さる中小企業経営者の方がいらっしゃいます。
ザックリと乱暴に言ってしまうと、資金繰り余力が低下する要因は大きく二つです。
良い順番に申し上げると、一つ目が、売上が増加した結果、資金繰りがキツくなるケースです。
原価のある商い場合、受注が増加すると、当然原材料を大きく仕入れたり、外注さんの応援を頂かなければなりません。
リードタイムが必要な場合であれば、材料仕入や外注先への支払が先行する一方、在庫や売掛債権が増加してしまうため、現預金が減少します。
このようなケースで、取引金融機関に資金を要請を行うと、金融機関では、「増加運転資金需要がある」と見做され、「良い融資案件」ということになって、「当行(当庫?)が資金の支援をさせて頂きます」となります。
増加運転資金により借入金は、「良い借入金」ということができます。
受注増加分によって膨らんだ在庫や売掛債権はいずれ現預金に替わっていくことで、収益も上がって資金繰りは安定化します。
一方、売上が減少したり、売上原価が嵩んで、収益が悪化した結果、2ヶ月、3ヶ月先に資金繰り余力が低下する場合です。
資金繰り余力の低下分をカバーする借入金を取引金融機関では、「後ろ向き資金需要」と見做して、警戒アラートの度合いを高めます。
「後ろ向き資金需要」の借入金は、いわば、「悪い借金」です。
中小企業にとってみれば、コロナ禍以降、世の中が動き出した一方で、原材料高、人手不足といった厳しい外部環境が蔓延しています。
中小企業経営者は、いつ、自社に「後ろ向き資金需要」が発生しても不思議ではないことを改めて実感すると共に、資金繰り表を作成することで、収益悪化によって近い将来起こり得る資金繰り余力の低下を早期に察知し、必要に応じて、取引金融機関と対話をし、必要な資金手当を打診する必要があるのです。
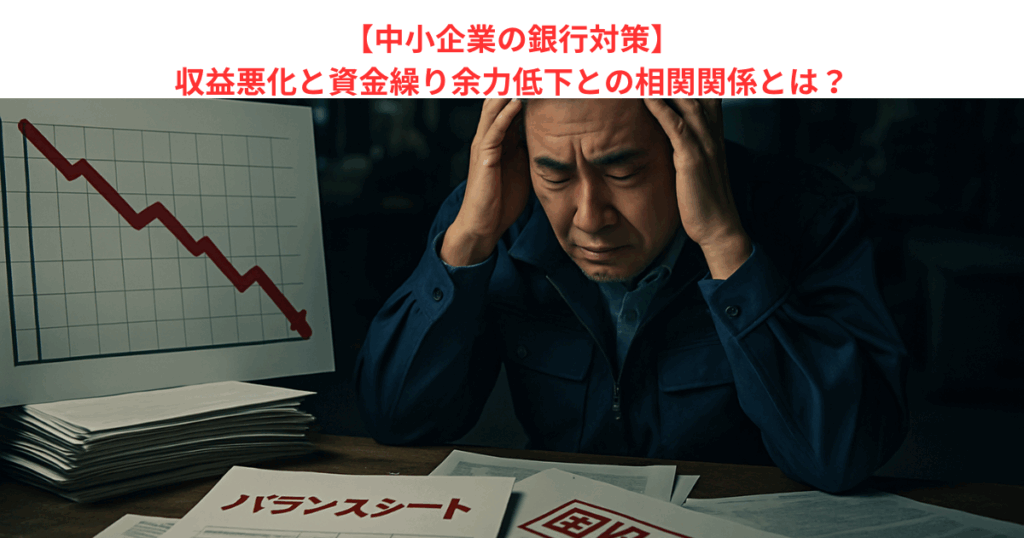
2 収益が悪化すると後追いで資金繰りがキツくなる
このように、収益が悪化すると、数ヶ月の資金繰り余力が低下します。
最初、試算表上で、赤字が出た時、経営者はついつい「大したことないな」と軽視しがちです。
しかしながら、数ヶ月後に「あらら、カネが足らん。おかしい」となってしまうのです。
営業畑で凄腕の経営者がやってしまいがちなのが、「あかん、赤字になってしもたから、俺の手腕で大口の仕事を取ってきた」という素晴らしい頑張りなのですが、ところが、収益悪化で資金繰り余力が低下した中で、増加運転資金需要が高まるような急速な受注増加を実現してしまうと、さらなる資金繰り余力の低下を招いてしまいます。
そもそも、会社が倒産に追い込まれる最大の要因が、「おカネがなくなること」です。
いくら、試算表上で利益が出ていても、キャッシュが絶えてしまうと、給料資金が枯渇したり、外注先への支払が滞ってしまうのです。
逆に言えば、試算表上で赤字が出てしまって、債務超過であったとしても、日銭が入ってくるようなB to Cの商いであれば、実際には潰れにくいのです。
中小企業経営者は、我が国の中小企業ベースでの商いが、他の国や地域では珍しい掛の商いである「信用取引」で成り立っていることを認識して、受注が取れても、実際にキャッシュの創出には数ヶ月単位の日数を要することを肝に銘じる必要があるのです。

