【中小企業の銀行対策】銀行員が連続休暇を取得するこのタイミングで留意すべきこととは?
今日は、中小企業の銀行対策として、銀行員が連続休暇を取得するこのタイミングで留意すべきことについて考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 銀行員の連続休暇は不正防止の意味合いを含む
2 担当者の休暇を把握しておく
どうぞ、ご一読下さい。
1 銀行員の連続休暇は不正防止の意味合いを含む
関西では、6月中に梅雨明けが宣言され、一気に真夏がやってきました。
世の中は、すっかり夏休みモードいっぱいですが、渇水にならないか、少し心配なところではあります。
ところで、多くの銀行員が7月と8月に連続休暇を取得します。
若手行員は、わざとこの季節を避けて、10月、11月といった閑散期に連続休暇を取得する傾向が見受けられますが、家族がある中堅以上の銀行員は、どうしても子供たちに夏休みに合わせて、連続休暇を取得することになります。
どこの金融機関でも、役職員に連続休暇の取得を義務付けています。
多くの銀行員が前後の土日をくっつけて、9連休を取得しますが、中小企業経営者とすれば、「長い休みで、ええご身分ですなあ・・・」と皮肉る向きがあるかもしれませんが、銀行員といえども、連続休暇を取得して、日常業務から解放され、リフレッシュすることは重要です。
一方で、連続休暇の取得の目的の一つとして、不正防止が挙げられます。
先だってのメガバンクでの貸金庫での盗難事件を取り上げるまでもありませんが、実際、メガバンクの営業店で役席者を勤めていた犯人は、貸金庫の利用者が来店する際には、率先して対応して、挙句の果てには貸金庫が故障しているとまで言い募って、盗難事件の隠蔽を行なっていたようです。
確かに、あのような盗難事件の犯人であれば、心配で心配で、うかうかと休みを取ることもできません。
「あの人は休みを取らず、皆勤賞やな」と褒められることは、金融機関ではあり得ない話なのです。
中小企業であっても、不正防止のため、特定の人しかできない業務を無くして、複数の社員がバックアップできるような体制を構築する必要がありそうです。
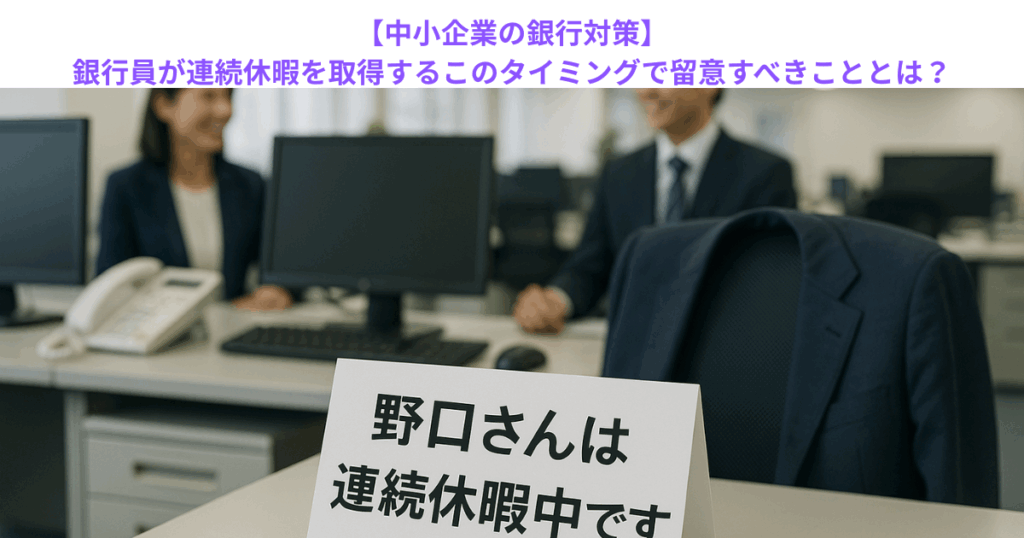
2 担当者の休暇を把握しておく
中小企業経営者からすると、急な資金需要が発生する際には、まずはメインバンクの担当者にニューマネーを打診することになりますが、いつものように、担当者の業務用携帯電話にかけると、「○×は今週いっぱい、休暇を頂いております」と事務的な対応がされないとも限りません。
もちろん、担当者が休暇中には、役席者や次席に引き継ぎをしますが、急な資金需要が発生する際には、担当者がいないとどうしてもいつも以上に対応に時間がかかったりします。
特に、建設業の工事見合いの引当融資や、季節変動で夏季繁忙期で増加運転資金が必要となる場合には、この季節では「もしかしたら担当者が休暇を取っているかも」と心得て、早め早めに、ニューマネーの打診を行うことが重要です。
中小企業経営者は、取引金融機関の担当者がこの季節、「休みを取っているかもしれない」ことを念頭に置いておく必要があるのです。

