【中小企業の銀行対策】業績予想は保守的に固めに表明すべき理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、業績予想は保守的に固めに表明すべき理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 業種によっては決算整理で収支は大きく変化する
2 業績予想でハッタリは厳禁である
どうぞ、ご一読下さい。
1 業種によっては決算整理で収支は大きく変化する
弊所では、お客様の中小企業経営者と共に、その会社の取引金融機関担当者とのモニタリング(業績報告)を行いますが、期末が近づいてくるタイミングや、決算が閉まって2ヶ月後の決算申告までの間では、取引金融機関担当者から、「期末の業績予想の着地はどのくらいでしょう?」というトピックスになることが極めて多くあります。
もちろん、弊所のお客様の中小企業は、皆、非上場で、かつオーナー企業ばかりなので、上場企業のように、業績予想を発表するわけではありません。
しかしながら、期末近く、あるいは期末を迎えて決算整理に向けて集計中のタイミングでは、ある程度、売上高、売上総利益、営業利益に経常利益の見込みが立つ場合があります。
一方、例えば、在庫を多く保有する製造業や、未成工事支出金や未成工事受入金を計上する完成工事ベースで売上計上する建設業では、決算整理で、大きく収支が変わってしまうことが珍しくありません。
売上高については、概ね概算数値が読めるのですが、製造原価の大きな業種では、おいそれと収支見込を言いにくいと言うのが本当のところなのです。
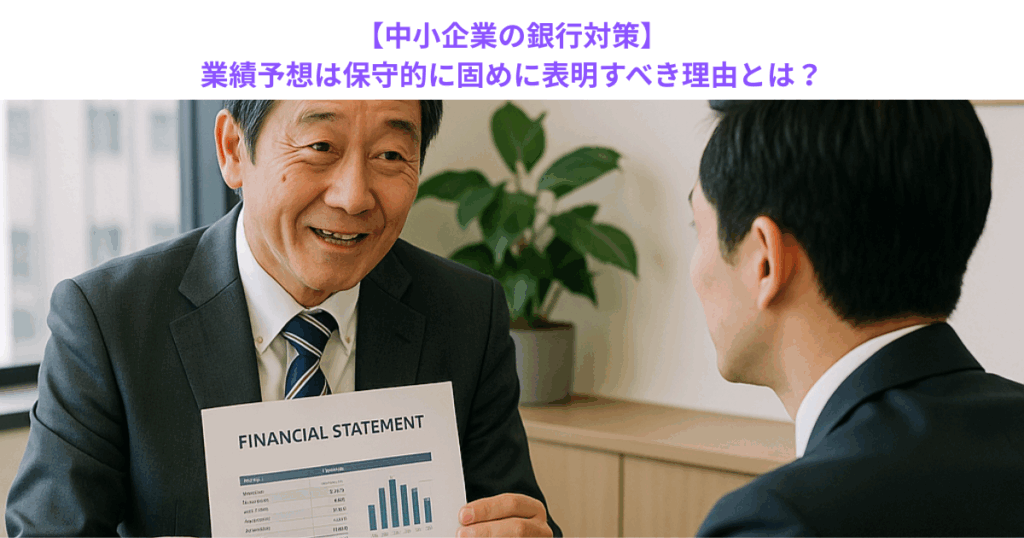
2 業績予想でハッタリは厳禁である
このように、売上高の予想はとにかく、収支の見込がなかなか軽々に申し上げにくいケースが多々あるのは間違いありません。
こうしたケースでは、よくありがちなのが、取引金融機関担当者が、少しでも上席に良い報告をしたい思いと、融資先の業績がなるべく好転して欲しいと念ずることから、ついつい、「社長、営業利益は前期よりも上振れしそうですよね?」と誘導的な質問をしてくることがなきにしもあらずです。
この手の誘導的な質問に対して、中小企業経営者は、なんとなく、「そうやなあ、多分行けそうやで」と答えてしまいそうですが、どちらかというと、楽観的な業績予想は決して良いものではありません。
ましてや、実際厳しい業績予想が見えている中で、期末まで押し迫っている中で、「今期はV字型とは言わないけど、まあまあええ数字でいけそうです」とハッタリをかますのは厳禁です。
中小企業の場合、決算が閉まって2ヶ月後には決算申告が完了し、取引金融機関担当者が決算書の提出を求めてくることが見えている中で、ハッタリはいけません。
もちろん、営業畑の社長で、通常の商い上でハッタリをかますことは珍しくないかもしれませんが、取引金融機関への業績予想は、保守的、固めと言うのが鉄則です。
なんなら、厳し目の業績予想を表明しておいて、実際の決算書を見てみたら、上振れしていたと言う方が、取引金融機関にはずっとずっと効果的です。
中小企業経営者は、取引金融機関へのモニタリング(業績報告)は楽観的な物言いは一切排除して、保守的、固めに表明しておくことが鉄則なのです。

