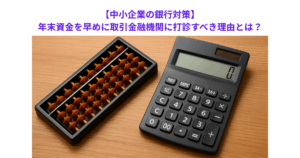【中小企業の銀行対策】他人事ではない長期金利上昇が及ぼす中小企業への影響とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、他人事ではない長期金利上昇が及ぼす中小企業への影響について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 長期金利上昇によって金融機関が保有する債券の含み損が拡大する
2 金融機関が保有する債券の含み損拡大は貸し渋りを誘発する
どうぞ、ご一読下さい。
1 長期金利上昇によって金融機関が保有する債券の含み損が拡大する
ここ数ヶ月間にわたって、株価が高い水準を維持している一方で、景気刺激策への懸念から財政出動の機運が高まっていることから、日本国債(JGB)が売られ、長期金利の上昇傾向が続いています。
直近ですと、8月初旬に長期金利は1.46%程度で推移していましたが、昨日(10月23日)の終値ベースでは、1.665%にまで上昇しています。
2ヶ月半の間で、長期金利の上昇幅は実に約0.2%にまで達しています。
金融機関は、基本的なビジネスモデルとして、一般預金者から集めた預金を原資に、貸付(融資)を行っています。
他方、預貸率(=融資残高÷預金残高×100%)が低い金融機関では、貸付(融資)で運用できないいわば余剰資金を投資有価証券で運用しています。
投資有価証券といっても、一般預金者からの預金を原資にしているため、リスクの高い投資有価証券で運用するわけにはいかず、安全資産とされる日本国債(JGB)を債券投資の中心とせざるを得なくなります。
ところが、長期金利が上昇する(即ち日本国債の価格が下落する)と、金融機関が保有する投資有価証券に含み損が発生してしまいます。
日本経済新聞社の集計によれば、2025年3月期の金融機関業態別の日本国債の含み損益は、地銀、第二地銀で1兆8,000億円のプラス(含み益)である一方、信用金庫で2兆5,000億円のマイナス(含み損)、信用組合で1,400億円のマイナス(含み損)となっています。
上記の数字は2025年3月末時点のものなので、現在では、上記の含み損益はさらに低下していることが予想されます。
長期金利の上昇が、地域金融機関の経営体力を大きく削いでいることは間違いことなのです。
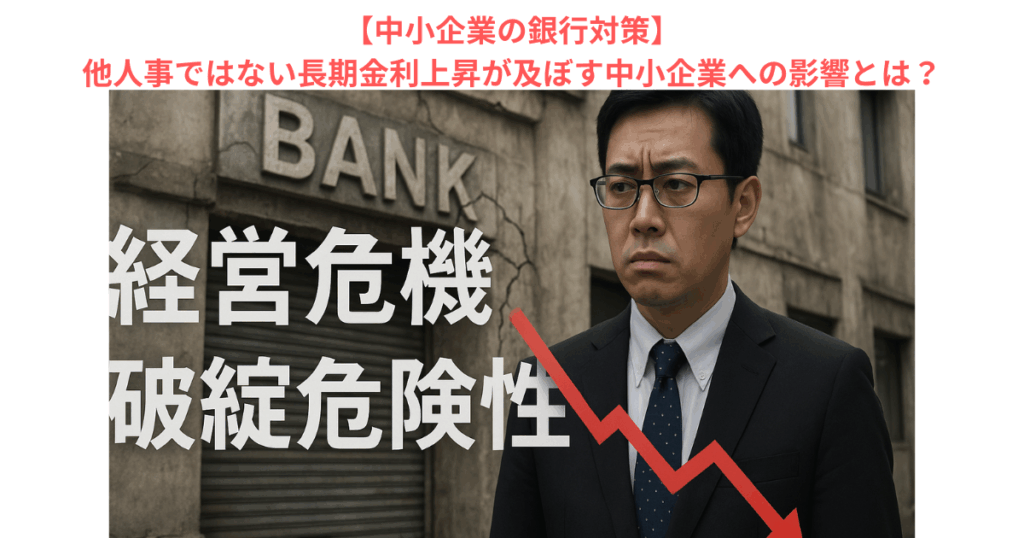
2 金融機関が保有する債券の含み損拡大は貸し渋りを誘発する
一方で、地域金融機関にもアメが与えられていて、地域金融機関が投資目的で保有する債券に含み損が発生していたとしても、投資目的が「満期保有」であれば、直ちに時価評価をして投資有価証券評価損を計上する必要はないとされています。
ただし、それも、問題の先送りに過ぎず、日本国債等投資有価証券に満期が到来する度に、投資有価証券売却損が発生して、地域金融機関のBSがどんどん傷んでいきます。
ここまでお話しして、中小企業経営者の中には、「長期金利が上がろうが、金融機関の話であって、うちの会社には関係ないわな」となってしまいがちなのですが、実はそう楽観的にはいかないのが現実なのです。
地域金融機関が保有する投資有価証券に順次満期が到来すると、今のままの長期金利の水準が続けば、投資有価証券売却損が断続的計上されていきます。
結果として、地域金融機関のBSが傷んでしまい、一定の自己資本比率を維持するために、地域金融機関の最も大きな資産である貸出金(融資をしているおカネ)を圧縮する必要が出てきます。
地域金融機関の本部は営業店に対して、「ニューマネーは出すな」、「既往の融資をどんどん回収すること」という指示を飛ばすようになってしまいます。
こうなると、かつてのバブル崩壊後に起こった貸し渋りや貸し剥がしが再発しないという保証は何もありません。
今の所、個別の金融機関の信用不安があからさまに露見するような状況は見受けられません。
また、貸し渋りや貸し渋りが問題となっているわけでもありません。
しかしながら、長期金利の上昇は、着実に預貸率の低い金融機関の経営体力を削いでいくことになります。
地域金融機関から融資を受けている中小企業経営者は、長期金利の上昇を対岸の火事として片付けるのではなく、早ければ12月には2025年中間期の地域金融機関のディスクロージャー誌がリリースされるため、特に、自社のメインバンクの投資有価証券の保有状況に関心を注ぐ必要があります。
そして、万が一、貸し渋りや貸し剥がしが起こった時にでも、他行に肩代わりしてもらえるような利益の出る収益体質と健全な財務状況を維持し、自らの会社を守ることが中小企業経営者の責務なのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご覧下さい。