【中小企業の銀行対策】今更聞けないTIBORや短プラの意味を知っておくべき理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、中小企業経営者が今更聞けないTIBORや短プラの意味を知っておくべき理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 為替よりも金利に強くなる
2 支払利息をコストとして捉える
どうぞ、ご一読下さい。
1 為替よりも金利に強くなる
金利がジワジワ上昇していると、一部で報道されたりしています。
中小企業経営者としては、金融機関から融資を受けている限り、特別な制度融資を除けば、借入金に対して支払利息を金融機関に払っているため、内心、(金利が上がるのは困るなあ)と不安に思っていても不思議ではありません。
報道からすれば、金利よりも為替の変動の方が取り上げられる頻度が高いため、中小企業経営者としても、為替の動向が気になるのは当然と言えば、当然です。
自社ブランドで輸出をしている中小企業はごくごく少数である一方、中国や新興国から直接、間接を問わず、原材料や商材を仕入れているため、円安に振れてしまうと原価の上昇に直結するため、為替の動向に注意が向くのは当たり前のことです。
しかしながら、長期、短期を問わず、金利の動向も経営者としては無視することはできません。
そもそも、自社の借入金に対する借入レートがいくらで、どのように決まっているかを正確に把握している中小企業経営者は実際にはごく少数です。
中小企業向けの貸出レートは金融機関の実務的にどのように決まるのか、簡単に説明をします。
まず、金融機関から見て優良先に関しては、市場金利連動型でレートを設定しています。
具体的には、TIBOR3ヶ月ものにスプレッド50ベイシスポイント上乗せするといった具合です。
では、TIBORとはなんぞのものなのか、今更聞けないようなことですが、簡単に触れておきます。
一口に金融機関といっても、資金が余っている金融機関がある一方、慢性的に資金が足らない金融機関があります。
もう少し具体的にお話しすると、資金が余っているというのは、預かっている預金に対して、融資として運用している資金が相対的に少ない金融機関が存在します。
これを示す指標としては、預貸率(=融資残高÷預金残高×100%)が挙げられますが、資金が余っているということは即ち、預貸率が低い金融機関ということになります。
預貸率が低い代表的な規模の大きな金融機関としては、農林中央金庫やしんきん中金などが挙げられます。
預貸率が低い金融機関は余った資金を現金で金庫に入れておいても何の収益も産まないので、資金が不足がちな金融機関(預貸率が高い金融機関)に資金を融通して、運用益を得ます。
資金がダブついている金融機関を「ローンポジション」と呼びます。
資金がダブついている資金の出し手の銀行以外の金融機関としては、大手証券会社や生命保険会社が挙げられます。
一方、預貸率が高い(資金が慢性的に足りない金融機関)の代表格が3メガバンクです。
資金が慢性的に足りない金融機関のことを「マネーポジション」と呼びます。
資金の出し手金融機関が、資金の受け手金融機関から得られる金利のことをTIBOR(タイボー、Tokyo Inter Bank Offerd Rate)と言い、多くの場合、TIBOR3ヶ月もので資金をやり取りするようになっています。
今年に入ってからのTIBORは基本的に上昇傾向です。
代表的な3ヶ月ものに関して言えば、年初時点でのレートが0.620%であったのが、昨日(11月11日)時点で0.809%にまで上昇しています。
つまり、スプレッドが50ベイシスポイントであれば、年初時点の出来上がりのレートが年率1.120%でしたが、昨日時点では、年率1.309%となっています。
優良先の融資先であったとしても、資金調達コストは年率0.189%上昇していることになるのです。
次に、メガバンク、地銀、第二地銀が中小企業向け融資で適用しているレートが短期プライムレート(短プラ)です。
短プラは、各金融機関が、自行の預金による調達コストを中心に考慮して独自で設定する基準金利です。
各行によって、短プラはマチマチで、現時点の短プラは、メガバンクで1.875%、関西を代表する地銀としては、京都銀行や南都銀行で2.575%、関西みらい銀行で2.900%となっています。
各行の短プラは、マチマチですが、昨秋からの短プラは上げ幅は0.400%となっています。
金融機関は、融資先毎に信用格付や債務者区分に基づいて、自行短プラに上乗せ幅を決めて(例えば、自行短プラ2.575%プラス0.750%で出来上がりが3.325%という具合)いるのです。
それに加えて、一部の信用金庫や信用組合では、独自の短プラを設定しない場合があって、そのような金融機関では、みずほ銀行の長期プライムレート(長プラ)を基準金利としていて、年初の長プラは1.900%でしたが、昨日付で2.450%に引き上げられいて、年初来からの上昇幅は、実に0.550%にまで達しています。
着実に金利上昇の波は、迫ってきているのです。
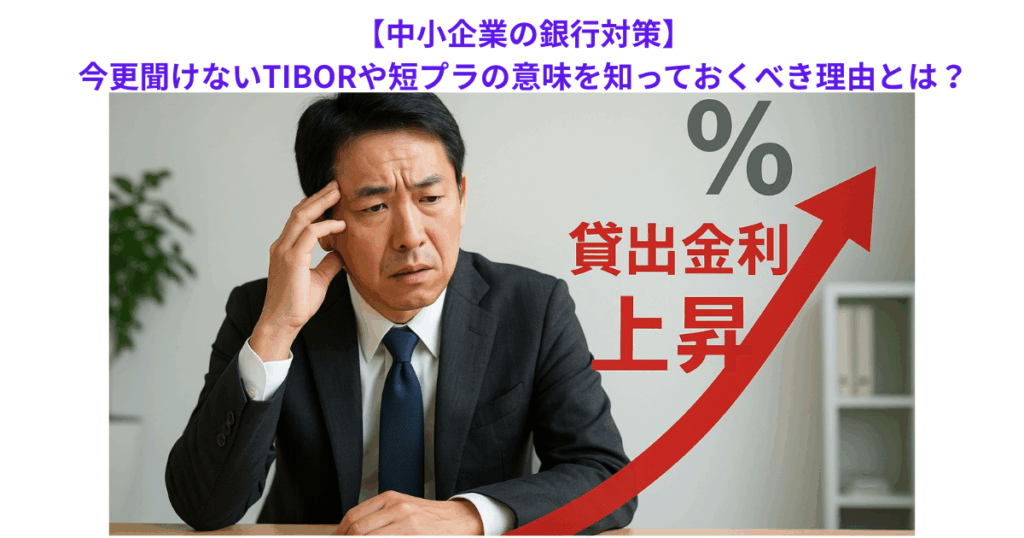
2 支払利息をコストとして捉える
通常の商取引の場合、どの中小企業でも、単価の交渉をするはずです。
「もう少し勉強してもらえませんか?」とか、「端数、切っといてもろてええですか?」なんていう価格交渉は営業現場では当たり前の世界です。
ところが、中小企業が金融機関から融資を受ける際、借入レートについて中小企業経営者が主体的に金融機関担当者に尋ねることはほとんどありません。
そもそも、中小企業が金融機関から融資を受ける際、金融機関の方が優越的な地位に立つことが多いため、中小企業経営者としては、金利がどうのよりも「1日でも早く実行してもらえませんか」の方が関心が先行します。
このようなことから、中小企業経営者は、どうしても自社の借入レートに強い関心を払わず、借入レートは金融機関の「言い値」で決まってしまうことが大半です。
ところが、金融機関へ支払う支払利息は、中小企業にとっては立派なコストそのものです。
そもそも、損益計算書(PL)の下の方ではありますが、営業外費用の中に、ドーンと「支払利息」が計上されています。
今後数年間は、よほどの天変地異のようなことがない限り、緩やかながらも、金利水準は上昇局面が続くことが予想されます。
もちろん、月次約定返済の進展によって支払利息を削減することができますが、借入レートの上昇は、想定以上のコストとして、収益圧迫要因にならないとも限らないのです。
中小企業経営者は、支払利息をコストとして捉え、借入レートの維持、低減のためにも、収益をより一層改善すると共に、安定した財務基盤(BS)を拡充することによて、債務者区分の引き上げ、信用格付の良化に注力する必要があるのです。


