【中小企業の銀行対策】金融機関の融資審査に一定の日数が必要となる理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、金融機関の融資審査に一定の日数が必要となる理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 本部審査とはなんなのか
2 実際の融資審査にかかる日数の目安
どうぞ、ご一読下さい。
1 本部審査とはなんなのか
中小企業経営者であれば、取引金融機関に融資の打診をしてから、一定の日数がかかることを経験則として実感していることでしょう。
取引金融機関に融資の打診を行ってから、融資実行に至るまで、金融機関の中でどのようなプロセスが取られるのか、掘り下げてみます。
まず、融資の可否については全て、「稟議(リンギ)手続き」によります。
営業店の担当者が、稟議書を起案し、渉外役席(営業課長、得意先課長、渉外担当支店長代理等)、融資役席(融資課長、融資担当支店長代理等)、次席(副支店長、次長等)が稟議所見を付し、部店長(支店長、支社長、法人営業部長など)に回付されます。
融資の審査に当たっては、債務者区分、信用格付、融資金額、保全(保証協会をつけるのか、あるいは不動産担保があるのか、保証人の有無など)、融資の期間などなどによって、決裁権限が厳格に決められています。
決裁権限の実際のところは、金融機関によってマチマチで、一概には言いにくいところがありますが、金額が小さかったり、債務者区分や信用格付が上位で、保全があれば、決裁権限は、営業店(支店等)の部店長にあることが多く見受けられます。
一方、部店長の決裁権限外の融資案件となれば、営業店の上位に位置する本部の与信所管部署(融資部や審査部等)に営業店から稟議書が回付され、調査役、審査役あるいは融資(審査)部長が決裁するケースがあります。
もっともっと、大きな融資案件であれば、役員決裁が必要であったり、究極的には頭取決裁という案件も存在します。
昔は、紙の稟議書が現金輸送車で営業店から本部に送られていたのですが、今時は、ほとんどの金融機関で、稟議手続きは電子化されています。
このように、本部審査の融資案件となれば、営業店だけではなく本部融資所管部署に至るまで、数多くの役職者に稟議書が回付され、煩雑な手続きとなるのです。
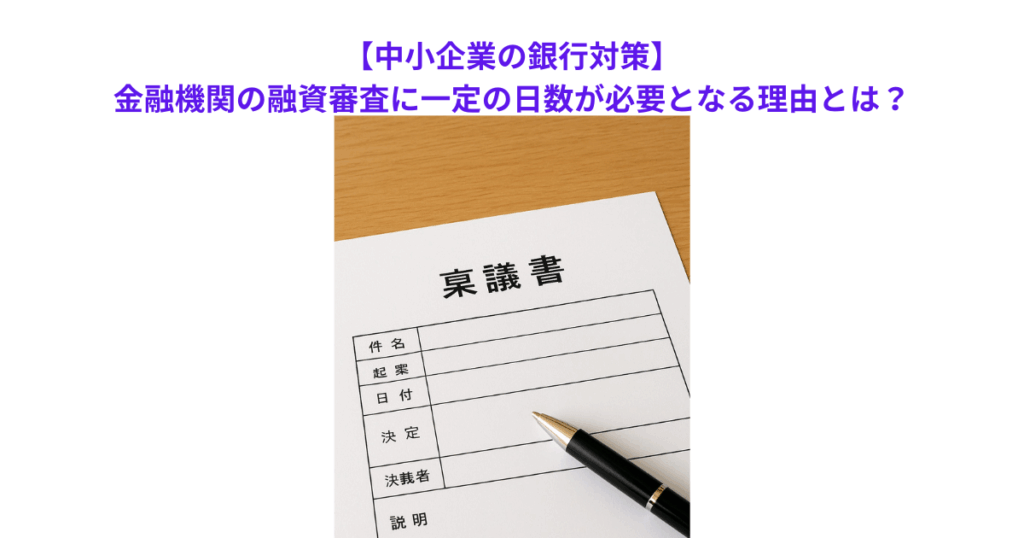
2 実際の融資審査にかかる日数の目安
融資案件の稟議手続きにおいて、稟議書の回付を受けた役席者全員が納得し、最終の決裁者が気持ちよく決済されるようなピカピカの案件は、正味のところ、少数派です。
特に、本部の融資所管部署の調査役や審査役は、業種別で担当が決まっていることが多く、その専門業種について営業店の役席者よりも理解が深いことが少なくありません。
そうなると、稟議書と付帯書類を見比べて、調査役や審査役は、「これは矛盾があるな」と疑問を感じると、営業店の融資役席に直接電話をかけて、「これ、おかしいんと違うか」と鋭い指摘を受けたりします。
痛い指摘を受けた融資役席は、担当の渉外担当者を呼びつけて、「この矛盾について論理的な説明をしてくれ」と渉外担当者を詰めます。
このようなやり取りが本部融資所管部署と営業店との間であり、営業店の中でも再度揉み直すようなことがあるとどうしても最終の決裁をおろしてもらうまで、一定の日数がかかってしまうのです。
ましてや信用保証協会の保証をつけるともなると、稟議手続きの前に、信用保証協会の保証承諾を頂かなければなりません。
このように、プロパーであろうと、保証協会の保証付きであろう、本部決裁の融資案件は短くても3週間は見込んでおく必要があります。
今日は11月28日金曜日。
11月の金融機関最終営業日となりました。
年末まで残り1ヶ月。
年内の金融機関最終営業日となる12月30日まで、営業日数は22日しかありません。
年末資金が必要で、年内のニューマネーをと考えている中小企業経営者がいらっしゃれば、もう残り時間はわずかです。
年内にニューマネーを、ということであれば、週末のうちに最新の試算表と資金繰り表(建設業であれば受注明細も)を準備した上で、週明け早々にメインバンク担当者を捕まえて、融資の打診を早急に行う必要があるのです。


