【中小企業の銀行対策】経営改善の鍵がアクションプランにある理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、経営改善の鍵がアクションプランにある理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 アクションプランはマニフェストである
2 具体的なアクションプランが実現可能性の高い収益計画策定につながる
どうぞ、ご一読下さい。
1 アクションプランはマニフェストである
中小企業が二期連続赤字となったり、実態ベースで債務超過に転落すると、取引金融機関から経営改善計画の策定を求められることがあります。
経営改善計画の策定に当たっては、もちろん、経営者自身が策定できれば良いのですが、多くの場合で、専門家が策定をしたりアドバイスをしたりします。
仮に、専門家に経営改善計画の策定を専門家に任せたとしても専門家に丸投げしてしまうのは危険です。
専門家への丸投げは、経営改善計画が絵に描いた餅となってしまうことが多く、経営者からも共感を得にくくなります。
経営改善計画は、いわば金融機関等債権者に対する約束事です。
その経営改善計画の重要な構成要素がアクションプランです。
アクションプランとは、ザクっといってしまえば、
1 具体的にどのような施策に取り組むのか
2 いつから実施するのか
3 その施策によってどのような効果があるのか
というところになります。
言ってしまえば、アクションプランはマニフェストのようなもので、政治家は往々にしてマニフェストをホゴにしてしまいがちですが、金融機関へのマニフェストはしっかりと実行に移していかなければなりません。
従って、経営改善計画策定を専門家に委ねる場合でも、経営者自身がアクションプランの策定にしっかりとコミットする必要があるのです。
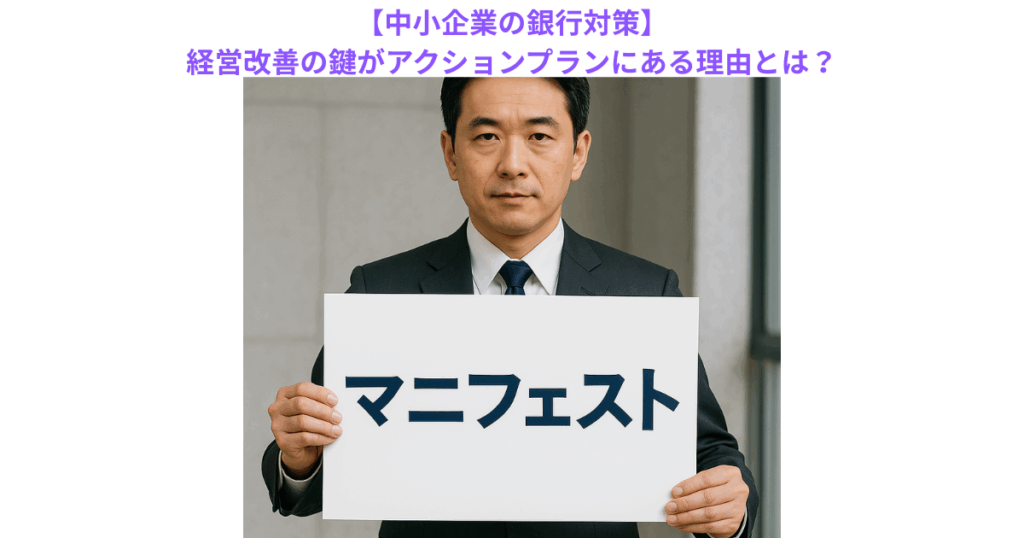
2 具体的なアクションプランが実現可能性の高い収益計画策定につながる
1 具体的にどのような施策に取り組むのか
2 いつから実施するのか
3 その施策によってどのような効果があるのか
という3つの要素で構成されるアクションプランですが、経営改善計画の精度の高さは、このアクションプランの実現可能性にかかっていると言っても過言ではありません。
逆に言ってしまえば、アクションプランを忠実に計数計画に落とし込んだ収益計画こそが、実現可能性が高いものとなります。
もちろん、借入金の返済にFCF(フリーキャッシュフロー)が不足する際には、アクションプランを再度見直して、より収益性の高い施策を検討しなければなりません。
借入金の返済に必要なFCFを確保することは、リスケジュール中であろうが、返済が正常であろうが、同じように重要なことです。
昨年から二度にわたって引き上げられた短期プライムレートは現在、落ち着きを取り戻していますが、長いトレンドでみれば、金利は上昇していくことが想定されます。
着実に借入金を返済して、有利子負債を圧縮していかないと、支払利息が嵩み、営業利益が吹っ飛びかねません。
経営改善計画の策定は、自社の経営課題を明確化して、収益を改善するために必要なアクションプランを導き出す絶好のチャンスです。
経営改善局面でなくても、収益計画を策定し、定期的にその進捗状況をトレースしていくことが重要なのです。

