【中小企業の銀行対策】中小企業の経理業務適正化に立ちはだかる課題とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、中小企業の経理業務適正化に立ちはだかる課題について考えます。
今日の論点は以下の2点です。
1 経理業務を間接部門を軽視してはいけない
2 開かれた経理部門を実現する
どうぞ、ご一読下さい。
1 経理業務を間接部門を軽視してはいけない
営業畑で独立した中小企業経営者の中には、「営業には人を割くけれど、経理はコストでしかない」という意識を持っている方がなきにしもあらずです。
確かに、経理部門は直接収益を産むことはありません。
しかしながら、非上場で、比較的事業規模の小さな中小企業であっても、経理部門の果たすべき役割は極めて大きいのです。
例えば、試算表一つ取ってみても、会計事務所に丸投げするケースもあれば、自社で会計ソフトを入力して会計事務所に必要に応じてアドバイスをもらうケースもありますが、中小企業経営者の手元にある試算表が前月のものがある会社もあれば、3ヶ月前のものしかない会社も存在します。
試算表は、なるべく直近のものを経営者がチェックして、先月は儲かったのか、損が出ていないのか、損が出ていれば営業方針を転換しなければならないわけで、直近の試算表こそが、経営者の経営判断を左右する重要な社内帳票であることは言うまでもありません。
また、取引金融機関から試算表の提出をリクエストされた時に、3ヶ月前の試算表しかなければ、取引金融機関の担当者は、「この会社、ホンマ、大丈夫か」と心配になったりします。
直近の試算表が随時リフレッシュされ、試算表自体の精度が高いことが極めて重要です。
試算表では利益が出ていたのに、最終的に決算整理を経て出来てきた決算書が赤字であれば、試算表の精度に疑問符がついてしまいます。
このように、試算表一つ取ってみても、中小企業にとって、経理部門がしっかりしていることの重要性は明確なのです。
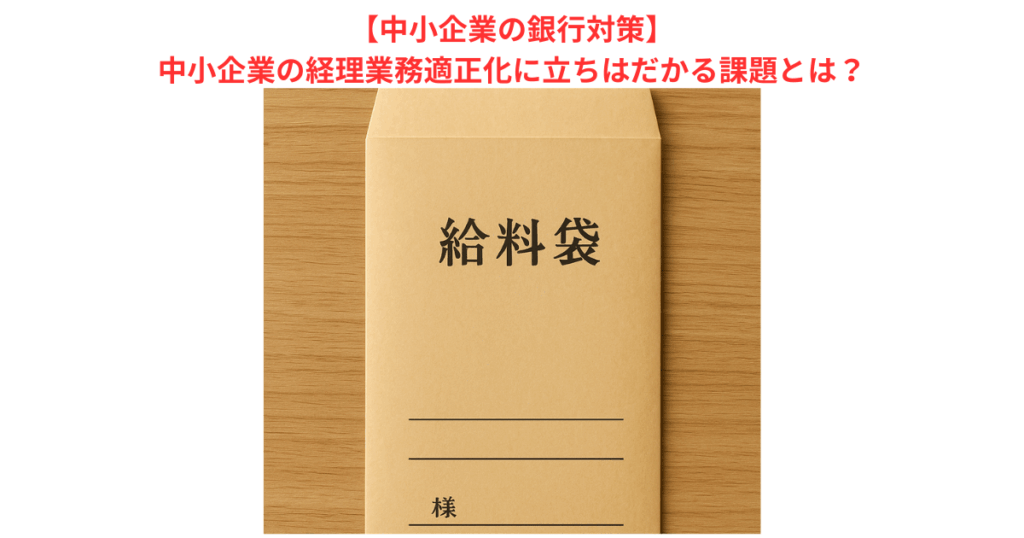
2 開かれた経理部門を実現する
中小企業の多くの場合で、経理業務は、社長の奥様が専務取締役兼経理部長で、経理担当者が3名というケースが多いようです。
社長の奥様が専務取締役兼経理部長であれば、社長にズンズンモノを言ってくれるので、これはうまく行くように感じます。
奥様が「社長、先月末、入金予定のX社、まだ入金あらへんからはよ督促の電話入れて下さい。なんなら今から領収書切るから集金行ってきてえな」と債権管理もしっかりやってくれます。
営業畑の社長には、金庫番の奥様が経理の責任者を務めるのは極めて適任です。
また、専務取締役兼経理部長の部下の経理担当者は入社以来、経理一筋というケースもまた散見されます。
中小企業で、経理担当者を固定化せざるを得ない理由の一つが会社独自の給与計算にありそうです。
人事制度がしっかりと確立されていて、人事評価が半期毎に回されていれば、社員一人一人の評価が明朗で、評価結果によって、給与テーブル上の何等級何号俸と決まるので社員一人一人の給与がいくらというのは社内で共有できます。
ところが、人事制度が確立されていない多くの中小企業の場合、給与テーブルも存在しないため、従業員Aさんはなんとなくいくら、Bさんもなんとなくいくら、というような給料の決まり方になっているので、社内で給料がいわばブラックボックスのようになってしまっています。
こうなると、人事ローテーションで経理担当者をどんどん入れ替えるということが事実上難しくなります。
経理部門自体がいわば会社の中のクローズな部署になりかねないのです。
「へぇ〜、Cさんてろくに働いてもないのにこんなにもらってるんや〜」と新しい経理担当者から他の社員にも、会社の中の究極の個人情報と言える給料の金額が伝播してしまいかねません。
中小企業ではなかなか難しいのは百も承知ですが、中期的な経営課題として、人事評価制度を社内で確立して、経理部門自体を開かれた部署にすることも経営者の役割の一つです。
いずれにしても中小企業にとって、経理部門は戦略部門であり、会社の中枢部といっても過言ではありません。
中小企業経営者は、経理部門をコストとだけ捉えるのではなく、経理部門をしっかりと位置付けることが、銀行対策にも有効であることを認識する必要があるのです。

