【中小企業の銀行対策】収益改善の最初の第一歩が赤字の原因特定である理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、収益改善の最初の第一歩が赤字の原因特定である理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 赤字が一過性か経常的かを見極める
2 収益改善に経営者の想いは極力封じる
どうぞ、ご一読下さい。
1 赤字が一過性か経常的かを見極める
コロナ禍が明けて以降、原材料高、人手不足、その他諸経費の上昇によって、中小企業の外部環境は厳しさを増しています。
本来であれば、サービス業を中心に、新型コロナウイルス感染症の影響が傷んでしまった会社を一気に立て直すことを目論んでいた経営者にとってみれば、アフターコロナのコストアップは想定外のことであったことは想像に難くはありません。
原材料高を代表するコスト高によって、赤字に転落してしまう中小企業は残念ながら珍しくありません。
経営者の本音からすれば、「こんなコスト高は長続きしないから、現進行年度以降は、収支は改善するさ」と楽観視してしまいがちですが、一度上がってしまった原材料、人件費は簡単に下がりません。
むしろ、前期よりも現進行年度、現進行年度よりも来期の方が、収益環境は益々厳しさを増すとネガティブに想定する方が無難です。
そこで、赤字に陥ってしまった場合、中小企業経営者がいの一番にやらなければならないことを「赤字の原因特定」です。
例えば、稼働率が大きく落ちてしまった生産設備の評価替えといったような赤字の要因であれば、キャッシュアウトは発生していませんし、あくまでも赤字の要因としては、「一過性」です。
一過性の赤字要因がなくなる現進行年度は着実に黒字転換できるということであれば、経営者としては焦る必要はありません。
ところが、複数の事業や事業所を運営している場合、特定の事業や事業所が不採算となっていて、全社の足を引っ張っているということであれば、特定の事業や事業所からの撤退を検討しなければならなくなります。
逆に、不採算となっている特定の事業や事業所を放置してしまうと、経常的な赤字要因となってしまい、黒字転換への道が遠くなってしまいます。
取引金融機関としても、融資先の健全化のため、赤字の要因を特定しようとしたり、赤字要因の特定を融資先の中小企業に求めてきます。
取引金融機関、中でも、メインバンクが赤字の要因の特定と、赤字体質からの脱却についての相談があれば、積極的に対話に応じて、率直に取引金融機関側の主張を傾聴し、必要となる赤字要因除去への手順についても、助言を受け入れる必要があります。
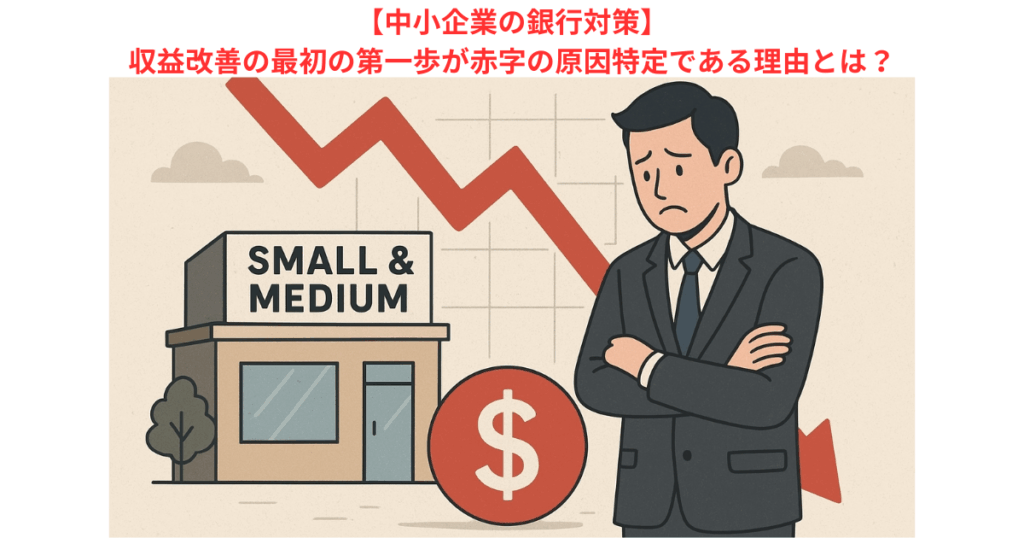
2 収益改善に経営者の想いは極力封じる
収益改善の効果測定は、基本的に四則演算(足し算、引き算、掛け算、割り算)で計算できるため、決して難しいものではありません。
ところが、収益改善への具体的な取り組みを始めようとする時に、意外に邪魔をするのが「経営者の想い」です。
例えば、事業部Xが不採算で収益改善が難しいという状況になった場合、現経営者が「それは先代が肝入りで立ち上げた事業やから、そう簡単に撤退するわけにはいかへんのや」という類の経営者の発言が出てくる場合です。
確かに、経営は全て計算で完結して、哲学は一切不要というつもりはありません。
確かに、経営理念で創業者の想いが綴られている会社も珍しくありません。
ところが、債権者の立場である金融機関からすれば、「先代の想いが詰まっている」と元経営陣から発言されてしまっては「元も子もないわな」と経営改善が立ち往生してしまいかねません。
社内的にも、「なんや、X事業部の奴らは赤字を垂れ流しててもノーペナやないか」と別の事業部門から不満が出てこないとも限りません。
このように、収益改善に取り組むと経営者が腹をくくる限りには、経営者個人の想いは極力封印をして、四則演算に従って、収益改善に邁進する他ないのです。

