【中小企業の銀行対策】取引金融機関の担当者からのお願い事はどこまで聞いてあげるべきなのか?
今日は、中小企業の銀行対策として、取引金融機関担当者からのお願い事はどこまで聞いてあげるべきかについて考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 銀行の外回りは「目標」を負っている
2 極力担当者のお願いを聞いてやる
どうぞ、ご一読下さい。
1 銀行の外回りは「目標」を負っている
一見すると、銀行等の金融機関の役職員はスーツを着用して、さぞかしホワイトに見えてしまいます。
しかしながら、実情は必ずしもホワイトとはいえません。
そもそも当たり前ですが、金融機関はどこも営利企業です。
本部に対して、営業店(支店、営業部、法人営業部、支社など)があって、営業店は、いわば「現場」で、どこも独立採算制です。
営業計数(100円儲けるのにいくら経費がかかるのか)が弾き出され、部店長(支店長等)の業績評価の基準の一つになります。
営業店が独立採算制である以上、営業部隊(渉外係、営業課、得意先課等)一人一人にも数字が降ってきていて、目標が設定されます。目標は言い換えると「ノルマ」なので、目標は必達です。
9月末や3月末は半期末、期末なので、目標達成のため、誰も必死です。
目標についても少し内容が変わってきていて、ゼロ金利、マイナス金利の時は、役務収入(手数料等)が得られる投資信託の販売に注力していましたが、金利がつく世の中となってからは、預金、中でも個人預金(一般個人からの定期預金)の獲得に重きが置かれています。
個人預金が重視される理由としては、法人預金が運転資金に充当されるなどして、解約される可能性が比較的高い一方、個人預金は比較的解約のリスクが低く、安定した資金調達源となるためです。
このように、銀行員の外回り部隊は、個人預金などの目標が設定され、目標未達は許されないという比較的厳しい世界なのです。
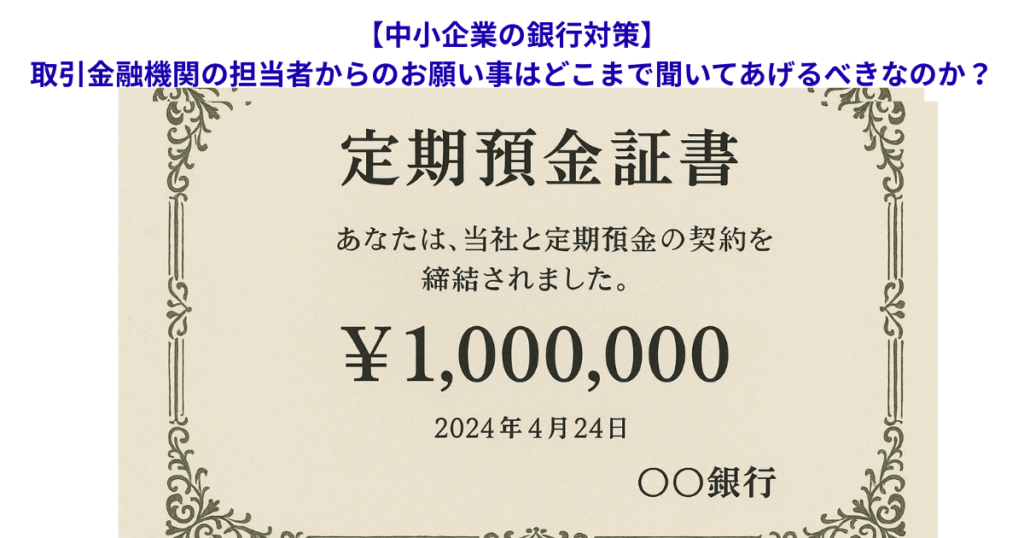
2 極力担当者のお願いを聞いてやる
来月になれば、外回りの銀行員は、上半期の末を迎えるので、融資先の社長に対して、お願い事をしてくる可能性が高まります。
このような取引金融機関担当者からもお願い事にどこまでお付き合いするべきなのでしょうか?
少なからぬ中小企業経営者が悩むところかもしれません。
取引金融機関担当者からのお願い事については、基本的に「聞いてあげる」というスタンスが妥当です。
コンプライアンスの厳しい世の中です。
特に、金融機関はコンプライアンスの縛りの中で仕事をしているようなものです。
このため、「そりゃ、無茶苦茶やろう」というくらいのお願い事はそもそも言ってくることはありません。
コンプライアンス同様に、優越的地位の濫用にも金融機関では十分配慮さsれているので、無理くりなお願い事は基本的にあり得ないというのが基本的なところです。
そもそも、取引金融機関担当者は、自分の担当先を一覧して、「この社長なら、このくらいはお願いできるやろう」という具体に見込み先を選定しています。
お願い事が定期預金であれば、別に拘束される(入担)わけではないので、次回の満期時に満期解約すれば角が立つわけでもありません。
中小企業経営者の側としても、いつ、資金が必要となって、取引金融機関担当者に資金のお願いをしなければならないとも限りません。
「俺は、銀行嫌いやからお願いされても絶対協力しないからな」と意固地になることなく、もちつ持たれるではありませんが、中小企業側に過度な負担とならず、お付き合い可能な範囲で担当者のお願い事を聞いてあげることも必要なのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。

