【中小企業経営者の心得】債権回収の難易度が高い理由とは?
今日は、中小企業経営者の心得として、債権回収の難易度が高い理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 我が国の商取引は基本「掛売り」である
2 貸倒はゼロにはできないが限りなく0を目指すことはできる
どうぞ、ご一読下さい。
1 我が国の商取引は基本「掛売り」である
我が国では、小売業や飲食業といったB to Cを除いたB to Bの商いは、基本「信用取引」です。
「信用取引」とは、文字通り、取引相手を信用して取引をすることでで、売る側とすれば、掛売をするということです。
具体的には、取引相手と売買契約が成立、受注をして、納品書と共に、役務を提供して、締日支払日に合わせて請求書を取引相手に送付して、銀行振込、集金などで売掛金を回収するという流れが信用取引のフローとなります。
「信用取引」は世界的にも珍しい取引形態で、諸外国ではほとんどの商取引が、キャッシュオンです。
諸外国では、多くの場合、性悪説なので、代金後払いでは払ってもらえなくなるという懸念が第一に先行するため、キャッシュオンが基本なのです。
我が国の信用取引は、取引相手を信用して、「お代は後で結構です」という性善説に立ってものです。
もちろん、新規取引の場合、ほとんどの会社では、前金もしくはキャッシュオンとするのが主流ですが、取引実績が重ねられていくと、「では、今回から掛売りで結構です」となります。
この信用取引を悪用するのが取り込み詐欺です。
取り込み詐欺は古くて新しい詐欺の手口ですが、最初3回の取引はキャッシュオンで支払って、段々取引金額が増えていきます。
営業担当者としては、「こりゃ、ええお客をめっけた」と喜んでいたら、掛売りに切り替えた途端、相手からの入金がなくなって、連絡が取れなくなります。
「こりゃ、やばい」と悟った営業担当者が、相手方の所在地に乗り込んでみたら、空き倉庫で、もぬけの殻という輩が令和の時代になっても生き残っていること自体、驚きですが、このような詐欺の手口に巻き込まれないよう、取引先の動向には十分注意を払う必要があることは言うまでもありません。
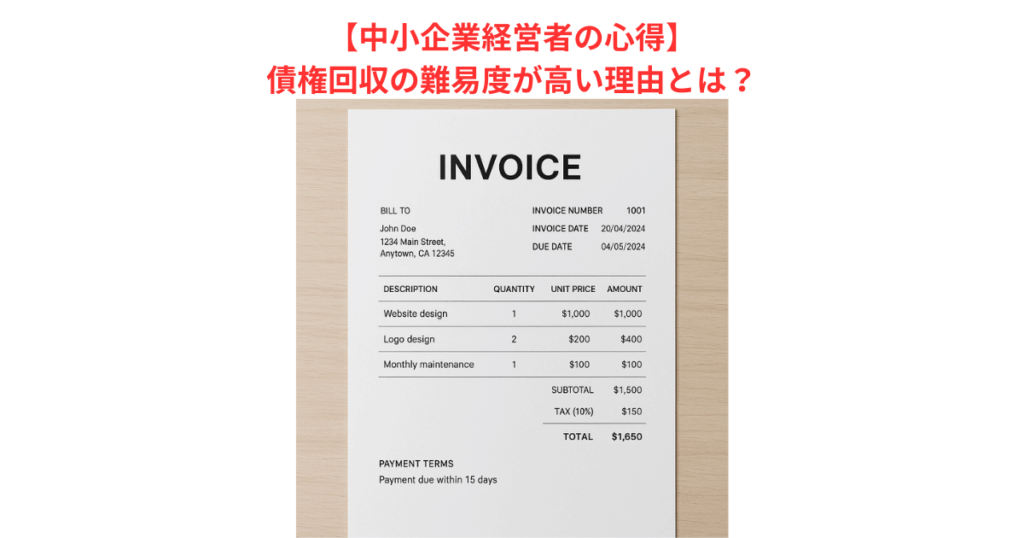
2 貸倒はゼロにはできないが限りなく0を目指すことはできる
実際、掛売りの場合、売上を作ることは難しくありません。
極端な話、相手に納品してしまえば、売上高を計上することができるからです。
問題は、債権回収の難しさにあります。
相手に納品して、請求書を送っても、いつまで経っても入金がない場合で、相手が破産等の法的措置にならないと貸倒損失としてBSから落とすこともできません。
債権回収の難しさは、金融機関でも同様です。
一般預金者から預かっている預金を原資に融資をしている金融機関は、貸出が不良化することは重大な問題です。
金融機関でもあっても、中小企業金融円滑化法施行以降、約定通りに、きっちり元利共々回収することの難易度は大きく跳ね上がりました。
中小企業が貸倒を防ぐために、打てる手はどのようなものがあるでしょうか?
保全という観点から、最も望ましいのが担保を頂くことですが、中小企業の場合、取引の力関係上、取引先から担保物件を徴求することはほぼ不可能に近いというのが現実です。
その上で、貸倒を防ぐために経営者や営業担当者が心得なければならないこととして挙げられることが、取引相手とトラブルにならないことです。
商談時の取引条件を曖昧なままにしてしまうと、「話が違うやないか!」と相手の怒りを買ってしまう懸念が残ってしまいます。
理想的には取引約定書等の契約書を取り交わすことが望ましいですが、取引先が中小企業同士であれば、契約自体、口頭で行われることが大半です。
現実に、契約は口頭でも十分有効なので、相手の支払条件を含めた取引内容をしっかりと詰めておくことがまずは肝心です。
また、納品後に、取引相手の反応を確認しておくことも重要です。
きっちりと相手が望むものを提供できたかどうかを確認して、フォローすることによって、リピート需要に繋げることもできるかもしれません。
とはいえ、信用取引、掛売りが基本である以上、貸倒を完全にゼロにすることは残念ながら難しいというのが現実です。
しかしながら、経営陣や営業担当者の丁寧な対応によって、貸倒をゼロに近づけることは十分可能です。
貸倒損失の発生は、PLにもBSにも大きなダメージをもたらします。
大口不良債権の発生は会社の存続を危うくしてしまいかねません。
取引金融機関も、融資先の不良債権の発生には警戒します。
中小企業経営者は、自社の持続可能性を高めるためにも債権回収には十分な注意を払うことが必要なのです。

