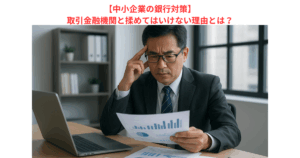【中小企業の銀行対策】難解なことを煙に巻こうとする金融機関をメイン行にしてはいけない理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、難解なことを煙に巻こうとする金融機関をメイン行にしてはいけない理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 わかりにくいことを平易に説明できる担当者は当たりである
2 中小企業経営者が知ったかぶりをしてはいけない
どうぞ、ご一読下さい。
1 わかりにくいことを平易に説明できる担当者は当たりである
中小企業経営者は、実に激務で、業務範囲も社内外に広範囲に及びます。
中でも、金融機関対応は、経営者の大切な仕事で、金融機関はなんといっても「資金の出し手」なので、経営者自らが折衝や交渉に当たるのが王道です。
日常的な入出金については、経理部長や総務部長に投げても構わないのですが、資金調達や既往の借入金への対応について、雇われの身の経理部長や総務部長にとっては身に余る仕事です。
経理部長や総務部長が金融機関担当者相手に対応しようとしても、資金に関することは会社にとっては中枢の機密事項なので、せいぜい、「社長と相談させて頂いて回答させて頂きます」と答えるのが精一杯です。
中小企業経営者は、銀行対応を雇われの身に丸投げするのではなく、自らが納得いくまで丁寧に折衝を重ねる必要があります。
そもそも、中小企業にとっての銀行対応は、どこまでいっても民法の債権債務に関することです。
大学の一般教養で、民法の債権総則をかじったことがあればさることながら、一般には債権債務に関することは馴染みが薄いと言えます。
昨年来、金融機関から説明を受けていることが「金利に関すること」です。
「自行短プラがいくらで、上乗せ幅(スプレッド)が何ベイシスポイントなので、出来上がりが何%にまであがります」、あるいは、「当庫では、みずほの長プラに連動させて頂いておりまして、みずほの長プラに何パーセント上乗せさせて頂いて、年一回4月に金利の見直しをさせて頂くのですが」という説明を金融機関担当者から受けているはずなのですが、よくよく社長の話を聞いてみると、「よお、わからんなあ」というケースがなきにしもあらずです。
金利の決まり方は、融資実行時に交わす金銭消費貸借契約証書にバッチリ記載されているのですが、実際に、自社の借入金の金利について、正確に把握している経営者はむしろ少数派だと北出は肌感覚で感じています。
これは、一義的には、金融機関側の説明不足(もっと言えば、担当者のプレゼン能力の欠如)がその原因になっているというのが北出が感じていることです。
適用金利が上がるというのは、金融機関担当者からすれば「社長に怒られるかも・・・」とビビりながら説明をする体になってしまいがちですが、そもそも難しいことについて、「適当に煙に巻いてしまえ」と考える金融機関担当者がいないとは限りません。
むしろ、難解なことを丁寧に平易に説明できる金融機関担当者は、中小企業経営者にとっては当たりなのかもしれません。
いずれにしても大切なことは、金利の引き上げは、中小企業にとってコスト上昇に直結することなので、経営者側が粘り強く自身の腹に落ち切るまで説明を求めるという姿勢が大切なのです。

2 中小企業経営者が知ったかぶりをしてはいけない
一般に難解な債権債務に関する事柄ですが、中小企業経営者がうっかりやってしまいがちなことが、説明を受けていることを被せてしまって、「俺、そのくらいのことはよおく知ってるで」と力んでしまうことです。
確かに、中小企業といっても、経営者は一国一城の主人で、そう簡単になれる職業でもありません。
やはり、トップセールスマンの経験から独立した営業畑の社長であれば、「銀行員に弱いところを見せてたまるか」と思う気持ちはよくよく理解できます。
しかしながら、債権債務の事柄は、非常にデリケートで難解です。
さらに、金融機関は数多くの融資先を持っていることで、圧倒的な情報量を有していますが、せいぜい、中小企業側は、民間金融機関から融資を受けるのは、現実的には3行、多くて5行程度です。
そもそも、金融機関と中小企業とでは、圧倒的な情報量の格差が歴然と存在します。
このような場合で、中小企業経営者は、「そんなことくらい、俺、知ってるで」とイキってしまうのはわかりますが、それは得策では決してありません。
むしろ、「当社は主たる債務者なので、経営者である私が納得いくまで説明してくれないと困ります」位のスタンスの方が健全です。
金融機関側が自行の都合のよくないことを煙に巻いてしまおうとして、中小企業経営者が知ったかぶりをしてしまっては、煙に巻こうとする金融機関の術中にそのままハマってしまいます。
後々、「ん〜、この金利のこと、よおわからんなあ」と困っても、説明を受けた時、知ったかぶりをしてしまっては、今更「もう一回説明してくれへんか」とはプライドの高い経営者ほど言えなくなってしまいます。
聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥とはよくいったもので、中小企業経営者が銀行員相手に知ったかぶりをするのは損して一利ありません。
金融機関担当者は、平時から彼ら、彼女らが意識していようがしてまいが、ついつい、専門用語を多用してしまいます。
中小企業経営者は、金融機関担当者が発する専門用語について、自身が納得いくまで説明を求める姿勢を維持することが必要なのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。