【中小企業の銀行対策】自社の借入レートの相場感を知る必要性とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、自社の借入レートの相場感を知る必要性について感がせます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 自社の借入レートを詳しく知る
2 借入レートは金融機関の評価に直結する
どうぞ、ご一読下さい。
1 自社の借入レートを詳しく知る
中小企業が金融機関から融資を受ければ、元本返済と共に支払利息を支払います。
中小企業が金融機関に支払う支払利息は、金融機関からすれば「売上高」に相当します。
中小企業であっても、優良なお客様には販売単価を引き下げるのと同様に、金融機関も融資先の信用度に応じて、レートを設定します。
金融機関にとって、優良先であれば、市場から資金を調達してTIBOR(Tokyo Inter-Bank Offred Rate)に連動させて50ベイシスポイントや場合によっては30ベイシスポイントという超破格のスプレッドを摘要することがあります。
他方、収益悪化、手元流動性低下によってリスケジュールに応じている融資先には、自行短プラに0.825%や1.250%も上乗せした出来上がりのレートで対応することもあります。
ところが、中小企業側からすれば、自社に適用されている借入レートが世間の相場から比較して高いのか、低いのか、判断がつかないケースが大半です。
親しい社長仲間であっても、「おい、お前のところの借り入れの金利でなんぼやねん?」というのは、関西のノリであっても、なかなか切り出しにくいことです。
ここに、金融機関と中小企業との間で、圧倒的な情報量の格差が存在しています。
この圧倒的な情報量の格差を埋めるためには、中小企業経営者自身が、メイン行、サブ行、政府系金融機関との間で、短プラ連動なのか、市場金利連動なのか、そしてスプレッドがいくらのっているかを正確に把握をして、メイン行の短プラのレートを差し引けば、上乗せされているスプレッドがいくらかわかります。
そもそも、中小企業経営者自身が、どうやって自社への出来上がりのレートが決まっているのかを把握しないケースが大半です。
情報格差を埋めるためにも、中小企業経営者自身が金利に強くなることが銀行取引をいい意味で緊張感を産む最初の第一歩なのです。
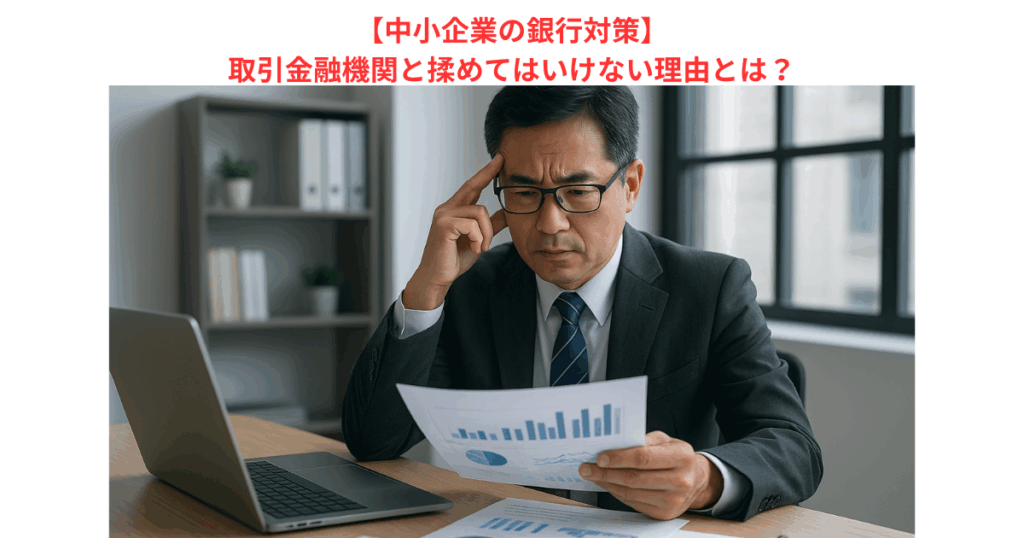
2 借入レートは金融機関の評価に直結する
金融機関から、運転資金、設備資金を調達しながら、商いをさらに大きくしていきたいと考えている中小企業経営者の中には、「メインバンクはうちの会社をどのように判断しているのやろう?」と時に、不安になったり、心配になったりしても不思議ではありません。
その中小企業経営者の心配、不安は不思議なものでもなく、また取り越し苦労でもありません。
なぜならば、借入レートは、金融機関の評価に直結するといっても過言ではないからです。
もちろん、一般論として、大企業の取引が多く、当座預金や普通預金といった流動性預金による資金調達のウェイトが高い大手金融機関は低レートで対応してくれるというのがありますが、サブ行、サブサブ行との絡みで、融資の残高シェアをより高めていきたい(取引深耕先)という先であれば、仮に、信金・信組であっても、本部の与信所管部署の稟議を経て、破格の低レートを提示することも十分行われています。
金融機関の大小や業態の問題ではなく、取引金融機関からの信用度を高めていくために必要なことは、適宜の情報開示、安定した財務体質と返済原資をしっかり確保できている収益力を維持、拡大していくことに尽きます。
中小企業経営者は、必要以上に奇を衒うことなく、持続可能性を高め、取引金融機関との信頼関係をより堅固にしていくための弛まぬ経営努力が必要なのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へ
もご覧下さい。


