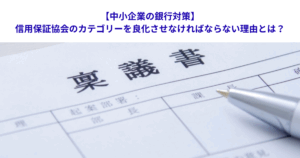【中小企業の銀行対策】経営責任を取るということの本質的な意味とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、経営責任を取るということの本質的な意味について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 株主イコール代表取締役がほとんどの中小企業の実態である
2 業績悪化時には経営責任が問われる
どうぞ、ご一読下さい。
1 株主イコール代表取締役がほとんどの中小企業の実態である
規模の大小を問わず、会社の業績が悪化したり、不祥事が起こった時に、経営者が経営責任を問われます。
上場しているような大企業の場合、代表権のある社長が退任したりしますが、彼らは、基本的に雇われ社長であり、ましてや、会社に対して金融機関への個人保証を追っているわけではないので、退任の記者会見の席上で「申し訳ございません」と頭を下げれば、基本、それでおしまいです。
その一方で、中小企業の場合はそういうわけにはいきません。
中小企業のほとんどは、オーナー経営です。
つまり、代表取締役である社長が大株主で、株主構成も社長一族で占められています。
赤字が続いて、資金繰りが悪化すれば、取引金融機関は、担当者だけではなく、支店長までが出てきて、「社長、これからどないするんですか?」と詰められてしまいます。
株式会社の場合、取締役は株主が決定した経営方針に従って、業務を指揮し、執行していくわけですが、オーナー経営の中小企業の場合、株主=代表取締役なので、経営方針の決定から実際の業務執行まで全面的に経営責任を負うことになります。
それに加えて、オーナー社長が、取引金融機関に対して、個人保証をしているのであれば、会社と社長個人は切っても切れない関係にあって、一蓮托生といえます。
このように、我が国の中小企業のほとんどは、オーナー経営で、会社と社長個人は一心同体の関係にあると言えるのです。

2 業績悪化時には経営責任が問われる
このように、中小企業のオーナー経営者は、取締役と株主として重たい責任を負っています。
一方、中小企業オーナー経営者は、取締役会と株主総会を牛耳ることができ、会社の中では絶対王者でもあります。
とはいえ、実際には、コンプライアンスにうるさいこのご時世なので、絶対王者として独裁的に振る舞うわけにはいきません。
実際には、オーナー社長が行使できる権限と取締役、株主として負う責任とを比べると、責任の方が重たくなっているのが現実です。
オーナー社長と取引金融機関との関係性が悪化する局面が、オーナー社長の会社業績の悪化です。
赤字が続き、FCF(フリーキャッシュフロー)が枯渇して、事業継続を最優先とするため、やむなく、取引金融機関各行にリスケジュールを要請するようなケースがその典型例です。
この時、取引金融機関は、オーナー社長に対して、経営責任を明確にすることを求めます。
経営責任を明確にする一番わかりやすい手段が役員報酬の削減です。
取引金融機関とすれば、「うちも泣くんやから社長も泣いてもらわんと合いませんわな」となってしまいます。
また、有休資産があれば、換金して借入金に内入れしたり、入担することも視野に入ります。
北出の経験則以上、入担となると、融資残高が最も大きなメインバンクが担保を徴求することになりそうですが、サブ行以下からすると、「メインばっかり保全厚くしやがって」と不満が出かねないので、換金してプロラタで各行に内入れする方が無難のように感じます。
中小企業経営者は、外部環境が厳しい中にあっても、経営責任を訴求されることのないよう、儲けをしっかりと出して安定した資金繰りを実現するため、日々弛まぬ経営努力が必要なのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。