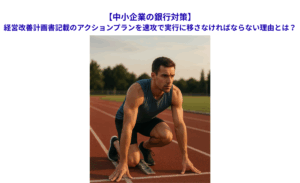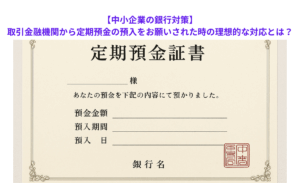【中小企業経営者の心得】自社の試算表を迅速かつ正確に上げなければならない理由とは?
今日は、中小企業経営者の心得として、自社の試算表を迅速、かつ、正確に上げなければならない理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 早さだけではなく正確性も大切である
2 試算表は経営判断の重要な材料である
どうぞ、ご一読下さい。
1 早さだけではなく正確性も大切である
ほとんどの中小企業では、自社の経理部門にて、もしくは関与している会計事務所に丸投げにて、月次で試算表を作成しています。
試算表は、いわば、決算書ができるまでの月次の通信簿です。
弊所では、お客様の中小企業経営者と共に、お客様の中小企業の取引金融機関担当者と月次モニタリングで同席をして、面談をしますが、試算表はその際の重要なアイテムです。
単純に、当該月の売上高、売上原価、売上総利益率、販管費、営業利益と、その前月との比較でどのようになったのかを試算表で把握をすることができるので、金融機関担当者も、試算表には強い関心を払います。
このように、試算表は直近の会社の収益状況を反映するため、なるべく早く試算表を上げなければなりません。
試算表はそもそも取引金融機関に提出するだけではなく、経営者自身が経営判断を行う際の重要なアイテムです。
一方、試算表の作成に当たって、迅速性を優先させるがために、正確性が十分担保されていなければ、それはそれで問題です。
PLでは、損益がキャッシュベースではなく、きちんと発生ベースで計上されていなければなりませんし、BSでも、現金や売掛金、在庫などいわば「現物」の残高に相違があってはいけません。
もちろん、業種や業態によっても、試算表の作成には負荷に違いがあるのも事実です。
小売業や飲食業のように、現金商売の場合、どうしても仕訳の数が増えてしまいますし、関与してもらっている会計事務所の事務能力にも違いが出てしまいます。
とはいえ、北出の肌感覚ですが、業種、業態を問わずに、試算表の正確性を担保しながらも、前月の試算表が遅くとも当月25日頃には経営者の手元に届くようにするのが「相場」のように感じます。
前月の試算表が当月25日頃にどうしても上がらないというのであれば、経理の業務フローや会計事務所とのコミュニケーションに問題があると考えるのが自然です。
その場合、往々にして、経理担当者が長年経理業務に従事していて、昔からの紙ベースでのやり方が継続されていることが懸念されるので、業務フローの抜本的な見直しを検討する必要があります。
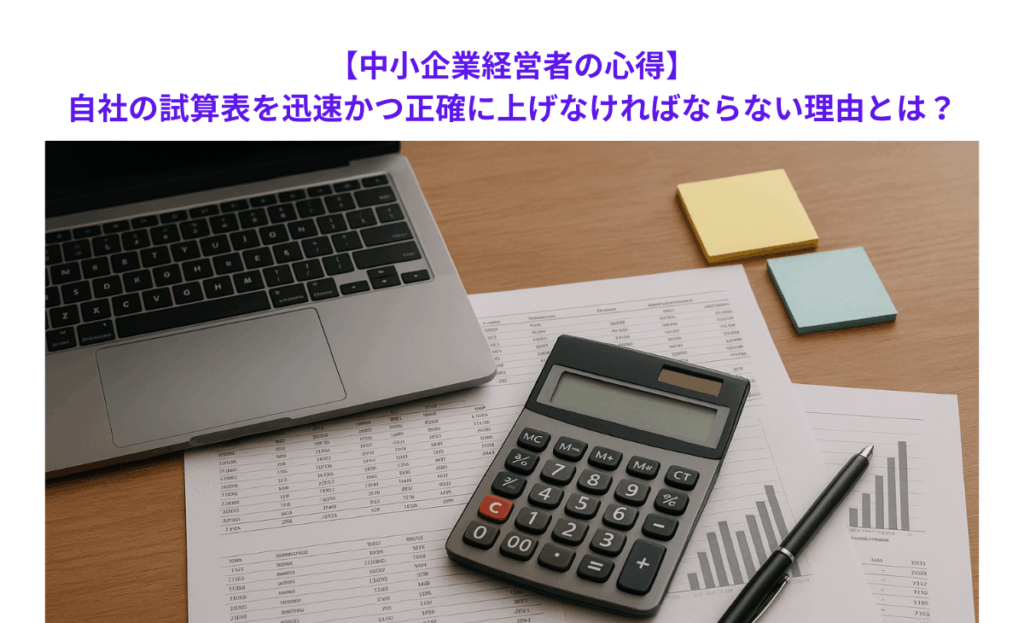
2 試算表は経営判断の重要な材料である
同時に、経営者自身の意識を変える必要があるかもしれません。
「たかが試算表やんか」と甘くみてはいけません。
試算表を国に例えて、考えてみることにします。
我が国では、各省庁が、様々な「統計」を発表しています。
例えば、不動産価格の場合、国土交通省が公示地価や不動産価格指数を発表していますが、不動産価格が高騰してバブルが疑われると、中央銀行である日本銀行は政策金利を引き上げて、過度な不動産価格上昇を抑制することを検討します。
GDPが落ち込むようなことがあれば、景気浮揚のため、与党の政治家は財政出動を伴うような追加経済政策に関する法案を立案します。
このように、国や与党、中央銀行は、様々な統計を精査して、様々な政策立案と実行に繋げているのです。
中小企業の場合も同様で、経営者は、試算表の推移を見て、仮に会社の売上や収益目標が設定されていて、進捗状況が思わしくなければ、営業部門に増収施策を業務指示として飛ばして、売上、収益目標必達に向けて、会社の進むべき方向に修正しなければなりません。
中小企業経営者にとってみれば、試算表は会社の経営判断を行う上で、重要な判断材料になるのです。
中小企業経営者は、試算表を銀行に提出するためのものというネガティブな発想を転換して、試算表を自らの会社の持続可能性を高めるための重要な判断材料であることを認識する必要があるのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。