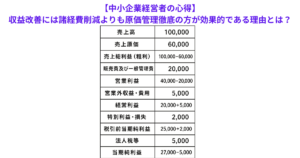【中小企業の銀行対策】地方における地域金融機関の経営統合が中小企業にもたらす影響とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、地方における地域金融機関の経営統合が中小企業にもたらす影響について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 地域金融機関の経営統合は寡占化を産む
2 複数業態の金融機関との取引を拡大する
どうぞ、ご一読下さい。
1 地域金融機関の経営統合は寡占化を産む
地域、地方によって差はありますが、全体として、特に地方において、地域金融機関の経営統合が進んでいます。
弊所が事務所を構える大阪府内には、関西地盤の金融機関が乱立するだけではなく、関西以外の地域の地方銀行が大阪に支店や支社を構えて、新規融資拡大にしのぎを削っていますが、総じて地方によっては、地域金融機関は経営統合によって地域金融という市場自体、寡占化が進んでいるケースが見受けられます。
金融庁等所管官庁は、金融システムをより堅固なものにするため、経営統合を推進していて、経営統合する金融機関には「資金交付制度」を設けているほどです。
あるいは、「俺が合併を推し進めたとして歴史に名を残したい」と考える野心的な頭取など銀行経営者がいないとも限りません。
一方、特に地方においては、金融機関の経営統合によって健全な競争が阻害されるとして公正取引委員会が待ったをかけるケースも見受けられますが、公取の意見が採用されて、金融機関の経営統合が破談になるということは今のところ、聞かれません。
とはいえ、一般論して、特に地方において、金融機関の経営統合が進むことによって、その地域における金融市場というマーケットで寡占化が進むことは避けられないことは間違いなさそうです。
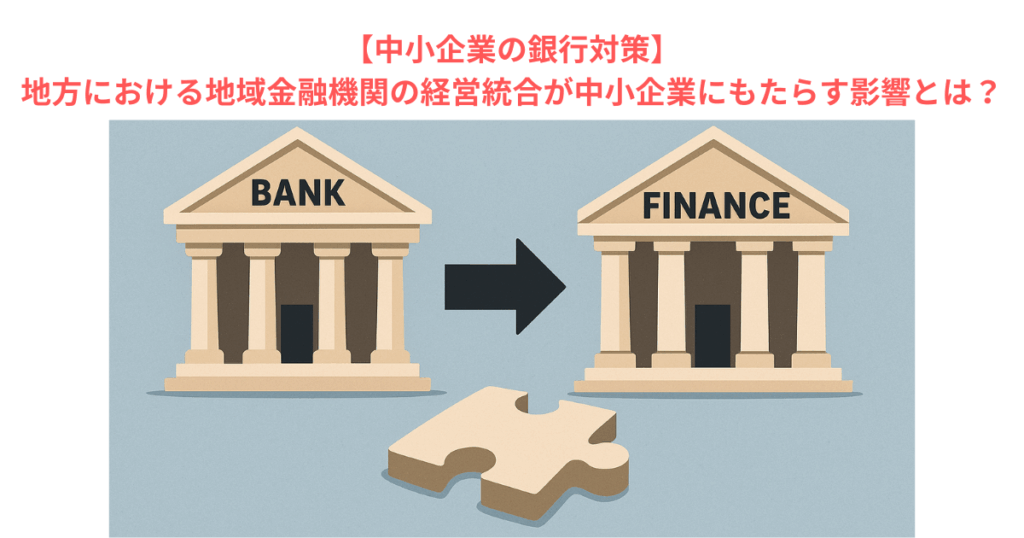
2 複数業態の金融機関との取引を拡大する
それでは、実際、中小企業において、取引金融機関が経営統合した場合、どのような影響があるのか、考えてみることにします。
中小企業X社の取引金融機関がメイン行A銀行、サブ行B銀行であった場合で、A銀行とB銀行が対等合併するとしましょう。
合併前のA銀行とB銀行は、ライバル関係にあって、X社の財務内容は安定的で、債務者区分が両行共に「正常先」であれば、A銀行とB銀行は、取引深耕を進めるべく、金利も良い条件を出し合って、融資残高シェアの拡大とに注力するのが普通です。
しかしながら、A銀行とB銀行が対等合併した場合には、事実上一行取引となってしまい、これまでのA銀行とB銀行の競合関係はなくなってしまいます。
これでは、取引深耕競争もなくなり、金利も上がってしまう懸念が拭えません。
このようなケースでは、X社にとっては、資金調達と財務戦略上、大きなマイナスに作用してしまいます。
このようなことを回避するため、中小企業はどのような手段を講じるべきでしょうか。
まずできることは、同業態の金融機関ではなく、複数業態の金融機関を取引行とすることです。
例えば、メイン行を地元ナンバーワンの地方銀行、サブ行を信用金庫にすることです。
第一地銀(従来からの地方銀行)と第二地銀(旧相互銀行から普通銀行に転換した銀行)をメイン行、サブ行とする手もありますが、第一地銀と第二地銀が経営統合して合併した「第1.5地銀」も珍しくなくなりましたので、第一地銀と第二地銀とで棲み分けることもリスク回避にはなりません。
このように、中小企業経営者は、安定的に資金調達を行い、堅固な財務戦略を実現していくためにも、取引金融機関を厳選する必要があるのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。