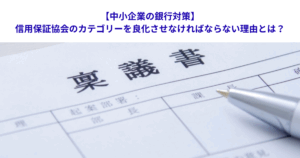【中小企業経営者の心得】計算機を使わずに済む社内の仕組み作りの効用とは?
今日は、中小企業経営者の心得として、計算機を使わずに済む社内仕組み作りの効用について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 計算機は紙ベースでの仕事の象徴である
2 計算機の最大の弱みが履歴が残らないことである
どうぞ、ご一読下さい。
1 計算機は紙ベースでの仕事の象徴である
中小企業の営業や経理の現場では、まだまだ重要な役割を果たしているのが計算機です。
確かに、例えば、お客様の中小企業経営者とその取引金融機関担当者との打ち合わせの中で、試算表の中身で「この比率はいくらで、最近の推移はどうなっているだろう?」という議題になった時、取引金融機関担当者は、すかさず、計算機を取り出して、実に慣れた手つきで計算機を叩き始めます。
一方、試算表がCSVでダウンロードされていて、エクセルに変換されているファイルがあれば、簡単な演算式を置けば、それらの答えは一撃で回答を出すことができます。
そもそも、銀行員は、打ち合わせの際、必ずと言っていいほど計算機を携行していて、忙しなく計算機を使うのが常です。
なぜ、銀行員は、計算機を使い慣れていて、当たり前のように使うのでしょうか。
これは銀行という組織に於いて、カチカチのシステムが運用されていて、エクセルなど汎用ソフトをなるべく使わずに済むような行内の仕組みになっているからに他ありません。
銀行という組織では、「勘定系」と「情報系」という2本の基幹システムが運用されています。
「勘定系」とは、預金と貸出金に代表される貸借対照表と融資利息と預金利息との差額である業務粗利益を中心とした損益計算書によって構成されていて、毎日毎日、営業店(支店等)で、BSとPLの借方と貸方を合わせているシステムのことです。
「情報系」とは、お客様個々の情報を管理するもので、例えば、山田太郎さん一家全員の取引状況を「名寄せ」して、世帯全体の取引状況がわかるようなシステムです。
世帯主でおじいちゃんの山田太郎さんとその奥様は当行で年金を貰っていて、同居する長男とその嫁さんは二人とも共稼ぎで当行に給与振込が入っていて、世帯合計の定期預金が1億20百万円という具合に、世帯全体の取引状況を把握できるのが「情報系」と呼ばれるシステムです。
このように、金融機関では、「勘定系」と「情報系」という二つの基幹システムで支えられているため、自分たちでエクセルのファイルを加工するような発想が乏しく、何事もプリントアウトをして、紙ベースでの仕事の仕方になりがちなのです。
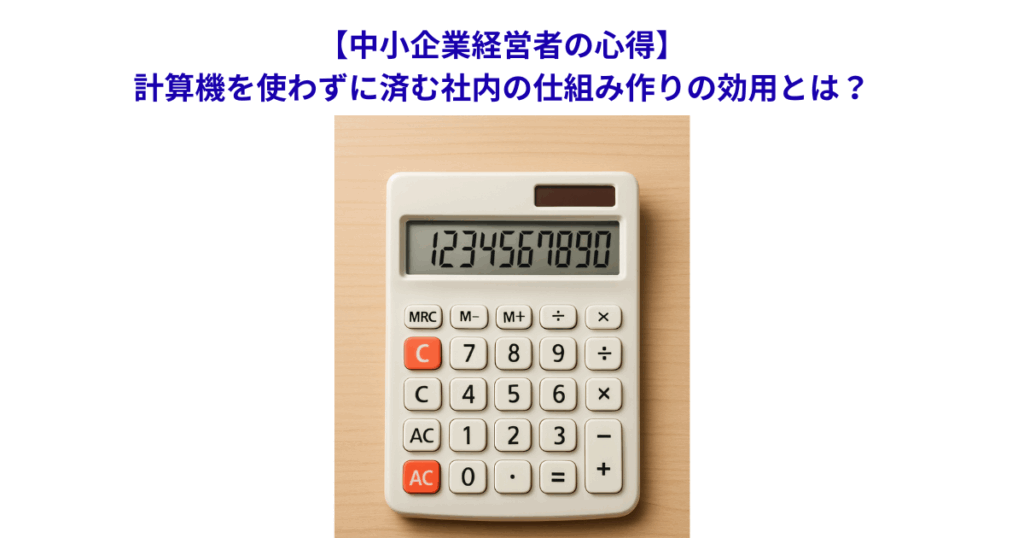
2 計算機の最大の弱みが履歴が残らないことである
先ほど、金融機関でのシステム運用のお話をしました。
翻って、中小企業の場合は、どうでしょう。
弊所のお客様の中小企業でも、最近は、システム会社のSEさんの協力を得て、汎用ソフトを自社に即したようにブラッシュアップした自社オリジナルのシステムを取り入れて、運用されているケースが多くなりました。
確かに、紙ベースでの仕事をするよりは、格段に生産性が上がっていることは間違いなさそうです。
一方で、SEさんはシステムの専門家ですが、その会社の社内の状況に精通しているとは言えないケースが多いため、自社のソフトを運用しながら、PCの傍で、担当者の社員の人が計算機で検算をしていたりするシーンがなきにしもあらずです。
せっかく、安くはないシステムを導入しているにもかかわらず、自社の最適マッチしているとは言い難いシステムが運用されているのは残念と言わざるを得ません。
下手におカネをかけてシステム拘置するよりは、真っ白けのエクセルファイルに演算式をバババッと入力して、試行錯誤をしながら、自社の現場が使いやすい手作りのファイルを作成するのも一つのやり方かもしれません。
いずれにしても、計算機を置きながら仕事をするのは決して効率良いものは言えません。
計算機はALL Clearにしてしまうと、履歴が残らず、後から数字を見ても、その計算根拠がわからなくなってしまうことも計算機のウィークポイントです。
働き方改革で、時短の流れは止められないトレンドです。
中小企業経営者は、余計な残業をさせず、社員が定着するためにも、計算機を使わずに済むような社内の仕組み作りに注力する必要があるのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。