【中小企業の銀行対策】安定性と成長のあるべきバランスの取り方とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、安定性と成長とのあるべきバランスの取り方について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 安定性と成長とを両立させる
2 中小企業経営者と旅客機の機長は役割が似ている
どうぞ、ご一読下さい。
1 安定性と成長とを両立させる
今日は2024年度の最終日です。
3月末が決算月ではない中小企業であっても、経営者とすれば、「明日は新年度のスタート、新年度は今年度よりももっともっと良い1年にする」と気合を入れるタイミングです。
まるで、今日が大晦日で、明日が元日のようなものです。
このような節目のタイミングでは、経営者は、自社を成長させることに目がいきがちです。
もちろん、あらゆる物価が上昇しているこのご時世ですから、売上を増加させ、増益を実現していくことは当たり前に極めて重要です。
とはいえ、売上を増加させ、成長路線を歩むことは、リスクも大きくなります。
成長を実現するために、大規模な設備投資を行ったけれど、想定していた受注がなくて、過大投資になり、設備資金の借入金が過多となって、返済が立ち行かなくなったという話も世間では珍しいことでは決してありません。
特に、非上場中小企業の場合、資金調達はどうしても金融機関頼みです。
金融機関は、不特定多数の預金者から預金を集めて、それを原資に貸付に回すので、不良債権が発生することは極力ゼロに近づけなければなりません。
融資先が経営破綻しないためにも、金融機関は融資先に対しては、成長よりも安定性をより重視します。
取引金融機関と友好的な関係を維持し続けるためにも、BSの健全性を維持しつつ、緩やかな成長路線を歩んでいくことが必要です。
非上場中小企業にとって重要なことは、安定性と成長をバランス良く両立させることなのです。
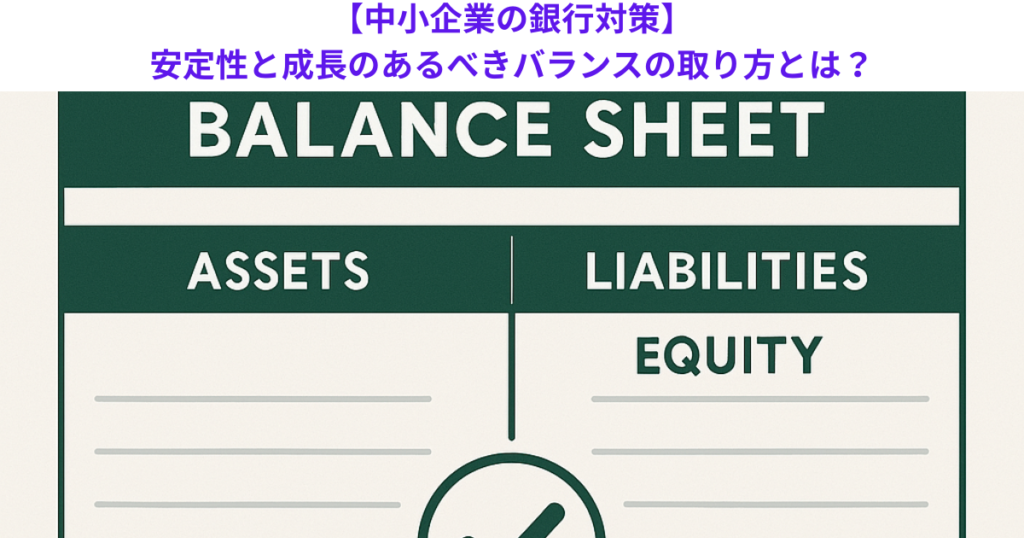
2 中小企業経営者と旅客機の機長は役割が似ている
成長と共に安定性が重要である理由は、なんといっても、成長を重視し過ぎて、地雷のようなリスクを踏みまくって、会社が経営破綻してしまっては元も子もないことに尽きます。
北出は、中小企業経営者と旅客機の機長とは役割が似ていると考えています。
中小企業経営者は、社員が路頭に迷うことがないよう、サステナビリティを高めつつ、成長路線を維持しなければなりませんし、旅客機の機長は、いざ離陸したら機体に不具合が発生しようが、乱気流に巻き込まれようが、意地でも、旅客機を安全に着陸させねばなりません。
中小企業経営者も、旅客機の機長も、判断ミスが生じた場合には、それを修正し、会社と旅客機を安定した状況に立て直す必要があります。
中小企業経営者は、新年度を迎えるにあたって、自社が成長と安定性を両立できるよう、経営方針を明確にする良い機会が到来しているのです。

