【中小企業の銀行対策】足し算・引き算・掛け算・割り算で会社の計数管理が十分可能な理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、足し算・引き算・掛け算・割り算で会社の計数管理が十分可能である理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 会社の計数管理は意外とシンプルである
2 計数管理の徹底で予実管理を実現する
どうぞ、ご一読下さい。
1 会社の計数管理は意外とシンプルである
我々のような専門家が作成する経営改善計画書や資金繰り表は、ともすれば、複雑で、作成に大変な労力が要るように見られがちです。
もちろん、経営改善計画書や資金繰り表は、それぞれの計数に個々に意味があって、会社の収益と財務体質を良化させていくための施策が盛り込まれているのですが、実のところ、盛り込まれる計数は微分積分といった複雑なものはなく、基本、足し算・引き算・掛け算・割り算の四則演算の集合体と言えるものです。
例えば、キャッシュフロー計算書は、足し算、引き算の塊でしかありませんし、売上総利益率や売上高経常利益率などは、言葉の通り「率」を求めるものなので、割り算で構成されます。
あるいは資金繰り表などはさらにシンプルで、将来の資金繰りを読むのに、掛け算・割り算を使用しますが、基本的には足し算・割り算で完結します。
北出の経験則上、取引金融機関から作成を求められているケースを除けば、ほとんどの中小企業では、資金繰り表が作成されていません。
資金繰り表は、いわば会社のビジネスモデルを資金の流れで表現したものなのです。
会社が倒産する根本的な原因は「おカネが尽きてしまうこと」なので、資金繰り表を作成することは、将来の資金ショートの可能性を探る経営上極めて重要なツールなのです。
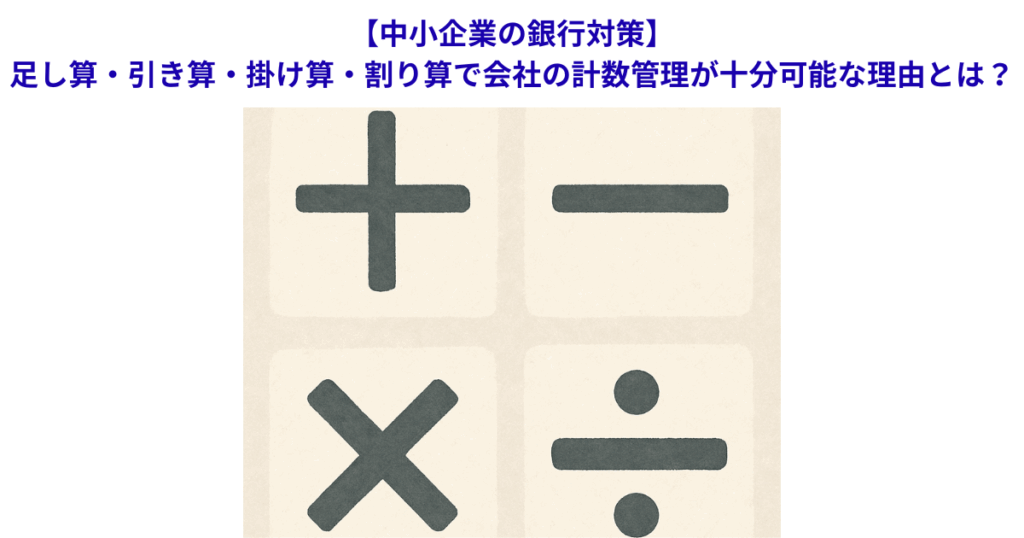
2 計数管理の徹底で予実管理を実現する
このように、会社の計数管理は、四足演算で十分に足りていて、基本的にシンプルなものです。
四則演算で求められる損益計画や資金繰り表は基本的に将来予測です。
損益計画や資金繰り表は作成して終わりではなく、将来予測の計画値に対して、実際の実績値がどのように推移し、計画通りであったのか、上振れしたのか、あるいは、計画未達に終わったのかを検証するのが重要です。
計画値と実績値との乖離の有無を検証することを、「予実(ヨジツ)管理」(予定に対して実績を管理すること)と呼びます。
計画値をクリアできれば良しなのですが、未達に終わった場合には、未達となった要因を明らかにして、具体的なアクションプランを修正することで、未達となったマイナス分を取り戻さなければなりません。
計画未達となったマイナス分はいわば「借金(プロ野球の勝敗の差と同じ感覚です)」なので、借金生活から一刻も早く脱する必要があります。
予実管理を徹底することは、会社を持続的に運営していくために極めて重要な経営陣の責務です。
中小企業経営者は、自社の持続可能性をより高めていくためにも、会社の計数管理を予実管理で徹底して、PDCAサイクルを回し続ける必要があるのです。

