【中小企業の銀行対策】出来上がりの借入レートを知っておくべき理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、出来上がりの借入レートを知っておくべき理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 メインバンクの短プラからの上乗せ幅を知っておく
2 資金調達コストはまだまだ上がっていく
どうぞ、ご一読下さい。
1 メインバンクの短プラからの上乗せ幅を知っておく
トランプ関税の影響を嫌って、外国為替レートが大きく触れながらもドルが売られて円が買われていることを反映して、春先まで上がり基調であった日本の短期金利は横ばいに推移しています。
とはいえ、去年秋以降、メガバンクと地方銀行各行は、二度の短プラ引き上げに踏み切り、トータルの短プラ引き上げ幅は0.400%に達しています。
短プラは、金融機関によって差が生じますが、その差が生じる要因として挙げられるのが、金融機関の資金調達の構造の差にあります。
大まかに言って、メガバンク等規模の大きな金融機関は調達コストの低い流動性預金(当座預金や普通預金等)での資金調達ウェイトが高いため、資金調達コストは小さく、このため、短プラは低めに設定されています。
一方、地方銀行等の場合は、流動性預金よりも固定性預金(定期預金や積立定期等)のウェイトが高いため、メガバンク等規模の大きな金融機関よりも短プラは高めに設定される傾向にあります。
金融機関によって差がある短プラですが、自社のメインバンクの短プラのレートを躊躇なく答えられる中小企業経営者はそう多くないというのが実際のところです。
因みに、現在の短プラは、3メガバンクで1.875%で、関西の地方銀行では、みなと銀行2.200%、京都銀行、滋賀銀行並びに南都銀行2.575%、紀陽銀行2.700%、関西みらい銀行2.900%となっていて、意外にも地方銀行ではばらつきが見受けられます。
さらに、大切なことは、信用格付や債務者区分によって短プラの上乗せ幅が個々の融資先で個別に設定されていることです。
例えば、メインバンクの短プラが2.575%で、短プラ上乗せ幅が0.500%であれば、出来上がりの借入レートは、3.075%となります。
変動金利の借入の出来上がりレートが3%超が珍しくなくなりました。
長らく続いたゼロ金利、マイナス金利の時代からすると、借入金利は相当程度上昇していることがわかります。
出来上がりの借入レートが3.000%ということは、1億円の借入残高の場合、支払利息は実に年間3百万円、月額250千円に達します。
月額250千円とは、概ね新卒初任給に相当するので、1億円の変動金利適用分3.000%であれば、新卒一人分の人件費が吹っ飛ぶ計算です。
大切なことは、メインバンクの短プラの引き上げ幅がいくらなのかを中小企業経営者自身が知っておくべきで、この上乗せ幅を縮小させるため、信用格付のより一層の引き上げを実現するための更なる収益改善が必要なのです。
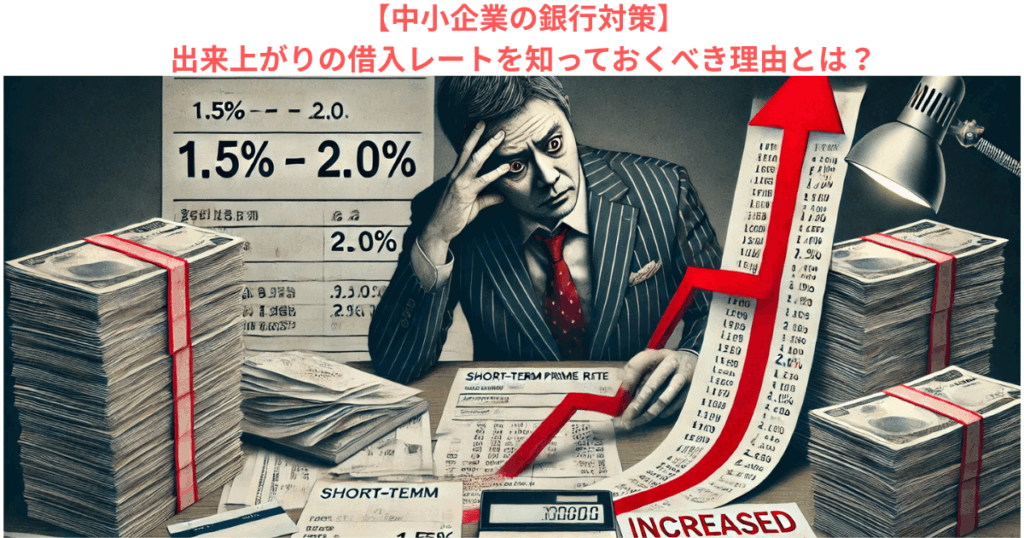
2 資金調達コストはまだまだ上がっていく
先日、米中の関税交渉が市場予想をいい意味で裏切る水準で妥結を見たことで、ドル円相場は一気にドル高円安に振れました。
トランプ関税の関税戦争は、どこの誰も徳をしないので、トランプのメンツを最低限保てる程度で収束することが期待されます。
ドル高円安基調が戻れば、短期金利は再び上昇基調に転じる可能性が高まります。
短期金利が上昇基調となれば、金融機関の短プラ引き上げ第3弾、第4弾が実現する公算が高まります。
こうなれば、地方銀行の短プラは3%を突破して、個々の融資先中小企業の出来上がりのレートが4%に達することも夢物語ではなくなります。
短プラ引き上げの次第によれば、原材料、光熱費の上昇、人件費の高騰のあおりをクリアして、たんとか叩き出した虎の子の営業利益が増加した営業利益で吹き飛んでしまいかねないのです。
中小企業経営者は、常に短期金利の動向に注目しつつ、短プラ上昇は來るべきものとして覚悟を決めて、本業を研ぎ澄まし、原価高、経費高を克服し営業利益をしっかり出せるようなビジネスモデルを常に追求していく必要があるのです。

