【中小企業経営者の心得】中小企業にとって不採算事業からの撤退が容易ではない理由とは?
今日は、中小企業経営者の心得として、中小企業にとって不採算事業からの撤退が容易ではない理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 不採算事業の撤退によってBSが痛む
2 不採算事業撤退によって予期せぬキャッシュアウトが生じる
どうぞ、ご一読下さい。
1 不採算事業の撤退によってBSが痛む
トランプ関税の影響が徐々に顕在化する中、少しずつ倒産件数の増加が報じられています。
中小企業が倒産に至るシンプルで最も深刻な原因が「おカネがなくなること」に他なりませんが、おカネが尽きる前に不採算事業を撤退することが必要となるケースがあり、取引金融機関から不採算事業撤退へのリクエストがあるかもしれません。
現実に、大手企業では、当たり前に採算の取れない工場を売却したり、赤字の店舗や事業所を閉鎖したりしますが、特に、中小企業の場合、残念ながら、不採算事業からの撤退へのハードルが決して低くはないというのが現実です。
中小企業が易々と不採算事業からの撤退に踏み切れない理由の一つが、資産の一部が不良化してしまい、実態ベースでのBSが大きく痛んでしまうことにあります。
具体的には、工場を売却する場合には、固定資産として計上していた建物の建屋や生産設備を処分する必要に迫られるので、固定資産売却損や固定資産除去損といった特別損失がドドーンと発生してしまって、場合によっては実態ベースで実質債務超過に転落してしまう懸念が払拭できません。
もちろん、不採算事業や死に体の資産を処分することで、PLが抜本的に改善したり、固定資産が内包していた含み損のようなものが解消して、V字型に回復できれば良いのですが、不採算事業からの撤退によってトップラインが大きく低下して、売上、入金が大きく減少してしまうと、V字型回復の前に会社が持たなくなることも想定されます。
このように、中小企業の場合、大手企業と違って、不採算事業からには、決して低くはないハードルが聳え立っているのです。
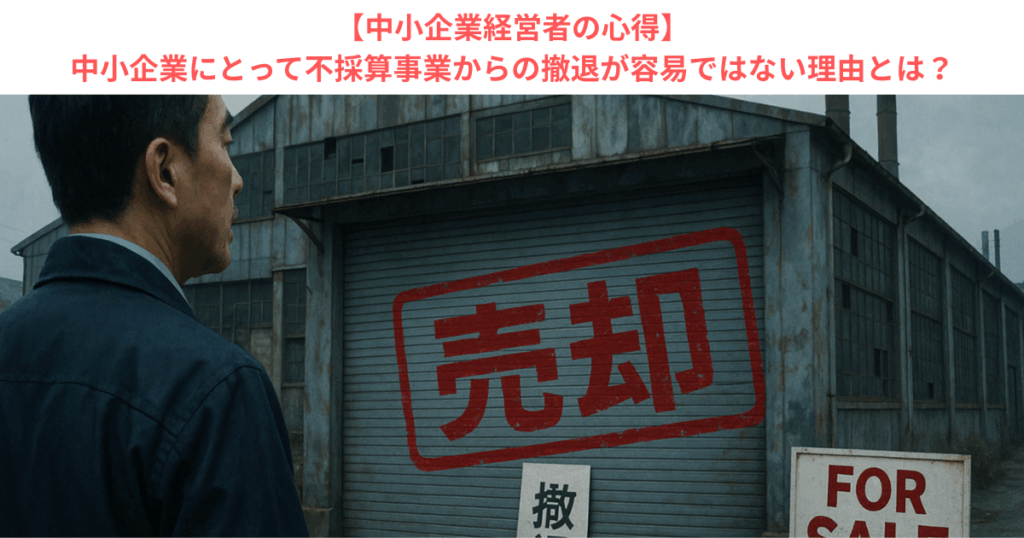
2 不採算事業撤退によって予期せぬキャッシュアウトが生じる
不採算事業撤退に伴う特別損失は、実態ベースのBSを痛め、取引金融機関の自己査定にもマイナスに作用してしまいます。
一方で、固定資産売却損や除去損といった特別損失は基本的にキャッシュアウトは発生しないケースが多いので、キャッシュフロー的に大きな負荷にはならないように一瞬思えます。
しかしながら、いざ、不採算の事業を整理するとなると、予期せぬキャッシュアウトが発生してしまうのが常です。
賃貸物件の中途解約に伴う違約金、生産設備の移転に伴う運送費用などなどに加えて、人員削減を伴う場合には、会社都合での解雇となることが多いため、割増で退職金を支払う必要が出てきます。
BSが痛む以上に、予期せぬ相応の臨時的支出はフリーキャッシュフローを大きく毀損し、会社の息の根が止まってしまうことさえ十分起こりうるのです。
下手をすると、不採算事業からの撤退ができず、赤字を垂れ流しながらキャッシュフローを痛めてしまって、本業も諸共行き詰まってしまうことさえ起こりかねません。
中小企業経営者は、外部要因による採算悪化に対しては、その影響を保守的で、リスクシナリオにて対応して、BSの傷み具合を見極めることとフリーキャッシュフローの想定(資金繰り表の作成)を緻密に行う必要があるのです。

