【中小企業の銀行対策】金融機関の目線が赤字決算に対してさまざまである理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、金融機関の目線が様々である理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 質の悪い赤字と質の良い赤字が存在する
2 粉飾するより赤字決算を選択すべき
どうぞ、ご一読下さい。
1 質の悪い赤字と質の良い赤字が存在する
一口に赤字決算と言っても、赤字決算には質の悪いものと質の良いものがあります。
そもそも論として、金融機関の融資先の評価としては、ザクっと言ってしまうと、BS7割、PL3割です。
金融機関の与信所管部署としては、融資先の安全性の評価が優先するので、BSをより重視する傾向が強いのです。
具体的に言ってしまうと、質の良い赤字決算は、一過性の特殊要因がはっきしているもので、かつ、実態BS上では、内部留保が潤沢であれば、一期だけの赤字で融資先の屋台骨が揺らぐような可能性は比較的低いのです。
一方、質の悪い赤字決算としては、本業で赤字体質が続いていて、収益改善が急務であって、返済原資が捻出しにくければ、リスケジュールに追い込まれる可能性が高まります。
また、簿価ベースで費用性の資産が計上されていたり、貸付金や仮払金など資産性の乏しい資産が計上されている場合で、実態BSでは、実質債務超過に転落しているようなケースでは、債務者区分を要管理先以下に引き下げられることが懸念されます。
このような融資先に対しては、金融機関として、取組スタンスを撤退・回収とせざるを得なくなります。
こうなると、中小企業としては、追加のニューマネーの調達が難しくなり、早急に経営改善を迫られることになります。
このように、赤字決算と一口に言っても、質の良いものと悪いものが混在するのです。
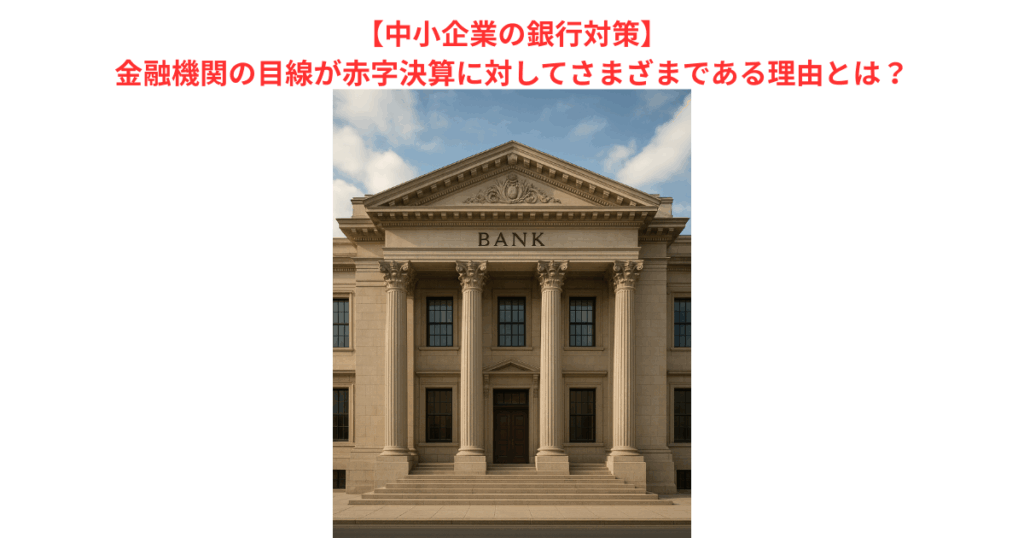
2 粉飾するより赤字決算を選択すべき
上記のように書いてしまうと、中小企業経営者の中には、赤字決算を回避するため、粉飾もやむなしと考える経営者がなきにしもあらずです。
会計事務所からも、「社長、期末在庫をちょっといじっときましょか」という悪魔の囁きが出るかもしれません。
しかしながら、粉飾決算は絶対にやってはいけません。
「この一期だけで、来期は元に戻す」と言っても、粉飾をしてしまったら、収益改善に取り組むことも消極的になってしまいます。
さらに、粉飾決算は、債権者の金融機関を騙すことになってしまって、詐害行為そのものです。
粉飾することは絶対に回避して、赤字決算となった原因を特定して、それを改善するためのアクションプランを明確化して、アクションプランを実行に移していくことの方がずっとずっと合理的です。
実態ベースで、実質債務超過に陥る懸念があれば、実態ベースでの債務超過解消を念頭に置いた経営改善計画を策定することも金融機関に対しては、極めて効果的です。
いずれにしても、粉飾は許されません。
粉飾するくらいなら、赤字決算を選択することが経営者として賢明な選択と言えるのです。
原材料高、人手不足、諸経費増加など、中小企業をめぐる外部環境は厳しさを増す一方です。
中小企業経営者は、この厳しい外部環境を跳ね除けて、自社が健全に次世代に継承していけるような会社にしていくための弛まぬ努力が必要なのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へ

