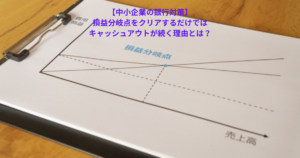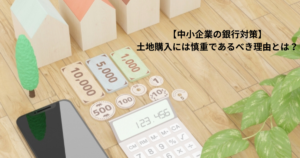【中小企業の銀行対策】営業力の源泉が価格競争力と債権回収である理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、営業力の源泉が価格競争力と債権回収である理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点。
1 安売りは手っ取り早いが首を締める
2 売りっぱなしは資金繰りを悪化させる
どうぞ、ご一読下さい。
1 安売りは手っ取り早いが首を締める
コロナ禍を脱して以降、すっかりデフレからインフレに局面が変わりました。
業界を問わず、原材料高は売上総利益率の低下に直結して、収益悪化要因となっています。
特に、中小企業の場合、原材料の多くが、輸入に依存していたことを改めて思い知らされます。
インフレ局面となって、B to Cの現場では安売り合戦が影を潜めました。
とはいえ、一部の業者が、逆張りなのか、安売りに走って、質より量を追い求めているのは、残念でなりません。
B to Bの営業の世界でも、低価格での受注は極力避けねばなりません。
もちろん、ガチンコの競合他社に受注をさらわれてはならないので、薄利を承知で、シェアを取りに行かねばならないケースもあるにはありますが、それも異例扱いとすべきです。
他方、個々の営業マンの立場からすると、受注を獲得するため、価格を下げようというマインドがなきにしもあらずです。
しかしながら、安売りを始めてしまうと、試算表上の売上総利益率が目に見えて下がります。
試算表をみたメインバンクの担当者は、売上総利益率の低下が顕著な場合、「この会社、大丈夫かいな」と疑心暗鬼に捉われてしまいます。
確かに、売上を作るためには、安売りは手っ取り早いですが、結果として会社の首を締めることにもなりかねないのです。
また、安値で取れたお客様は、遠くない将来、別の業者に更なる安値で落ちてしまう可能性が高いのです。
価格以外のサービスや、営業担当者の力量を常日頃から高めておく必要があるのです。
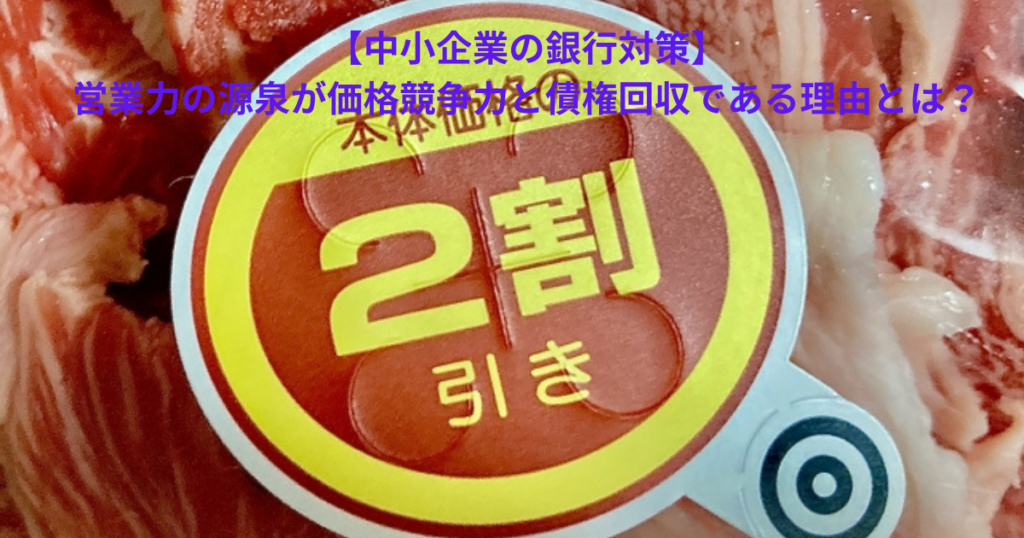
2 売りっぱなしは資金繰りを悪化させる
次の営業部門の課題が売りっぱなしが放置され、債権回収が十分にできていない中小企業です。
資金繰り余力が低下して、経営改善が必要な中小企業では、売りっぱなしが常態化しているケースが散見されます。
本来、得意先と取引を開始する場合、理想的には基本取引約定書の類の契約書を締結するのが理想的です。
しかしながら、特に、中小企業の場合、個別に契約書を交わすケースはむしろ少なく、現に、「契約は口頭で有効」です。
なので、あくまでも口約束ではありますが、営業担当者が先方としっかりと人間関係を構築できていたり、日頃からケアを怠っていなければ、請求書が先方に届けば、先方の締め日支払日に合わせて、振込で入金してくれますし、支払日に小切手と手形を集金することができるはずです。
ところが、価格だけで勝負していると、同業他社との競合に常にさらされていて、取引条件も満足に確認しないまま、受注して納品してしまうケースが見受けられます。
また、取引条件が曖昧であったりすると、お客様とトラブルになってしまって、支払ってもらえるものも支払ってもらえません。
北出も、お仕事をさせて頂く際に、売掛金を確認するのですが、長期未収金が放置されたままでは、資金繰りは悪化する一方です。
決算書の勘定科目明細の売掛金の欄に、毎年同じ先で、同じ金額が記載されていたりすると、メインバンク担当者は、実質的には不良債権と見做して、査定してしまいます。
実態BSが傷んでしまって、簿価では資産超過でも、場合によっては、実質債務超過と判断されてしまうと、ニューマネーの調達ができなくなってしまいます。
中小企業経営者は、営業担当者任せにするのではなく、営業担当者に債権回収までしっかりと責任を持たせて、長期未収金を限りなくゼロに近づけることで、メインバンク以下、取引金融機関からの信頼を得ることができるのです。