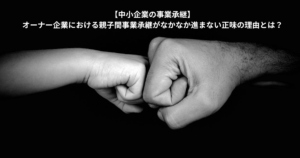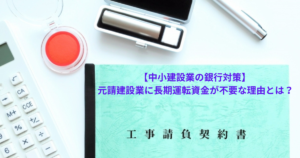【中小企業の銀行対策】経営改善は現実味があって実現可能でなければならない理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、経営改善は現実味があって実現可能でなければならない理由について考えます。
今日の論点は以下の2点。
1 急進的な経営改善は頓挫する
2 中小企業の経営改善に「和を以て貴しと為す」が必要である
どうぞ、ご一読下さい。
1 急進的な経営改善は頓挫する
今年に入ってから、知名度の高い一部の大手企業で、早期希望退職を募るような人員整理が散見されています。
知名度の高い大手企業であっても、円安による原材料価格の高騰や賃上げの影響によって人員整理に踏み切るケースが見受けられます。
原材料価格の高騰や人件費高は、中小企業に限ったことではないようです。
少なからずの中小企業では、コロナの影響を引きずっていたり、原価高の影響から、経営改善が必要な局面にあります。
経営改善を図っていく中で、経営改善計画を策定し、アクションプランを明確化して収益改善を実現していくわけですが、中小企業に限って言えば、北出の経験則上、過度な急進的な経営改善を強行しようとすると、経営改善が頓挫してしまう例を見てきています。
従業員が何万人、何千人もいて、日本国内だけではなくグローバルに展開している大手企業であれば、45歳以上を対象とした早期希望退職を募って、人員削減を強行することが有効かもしれません。
しかしながら、従業員が数十人規模の中小企業であれば、下手をすると、従業員が皆、少なくとも顔くらいは知っているというような事業規模です。
謂わば大家族的な中小企業であれば、急進的な経営改善はむしろ逆効果に作用してしまうことが珍しくないのです。
もちろん、収益をしっかりと改善して、返済原資を確保して、有利子負債を着実に圧縮していくことは、経営改善の当然の目的ですが、アクションプランの一項目に取り組んでいくに際しても、収益改善には従業員一人一人の頑張りに大きく依存します。
このご時世ですから、賃上げも実現しないと、優秀な従業員が会社から離反していくリスクが高まります。
中小企業経営者は、収益改善と従業員の満足度を上げることを両立する必要があるわけで、昭和の時代のように、「気合いで頑張るぞ」というわけにはいかず、経営者として、難しい舵取りが求められるのです。

2 中小企業の経営改善に「和を以て貴しと為す」が必要である
このように、中小企業の経営改善には、スパルタ一辺倒では、経営改善自体が頓挫してしまいます。
従業員が「こんなん、やってられへん!」と匙を投げてしまっては元も子もないのです。
特に、業歴の長い会社の場合、古参の従業員がキーマンとして現場を仕切っていることが多くあります。
急進的な経営改善は、ともすれば、「現状否定」という風に捉えられてしまいがちです。
他方、長く、安定して仕事をしたいという従業員のニーズと、経営者側の経営改善を図って収益改善と財務体質良化は、利害が一致するはずです。
決して、従業員側と経営側が半目するような関係では本来ありません。
このため、経営者の気持ちとして、「なんとしても経営改善を果たす」という気持ちと共に、従業員を始めとした全てのステークホルダーに対して、「和を以て貴しと為す」という発想が必要不可欠です。
多くの場合、経営改善の計画期間は最長で10年間にも及びます。
経営改善は短距離走ではなく、マラソンです。
途中で息切れすることなく、完走することが第一です。
完走するまでの過程では、決して計画通りに進捗しないことも多々発生します。
中小企業経営者は、次世代に残せる会社を実現するため、マラソンを完走する気持ちで、経営改善に取り組む必要があるのです。