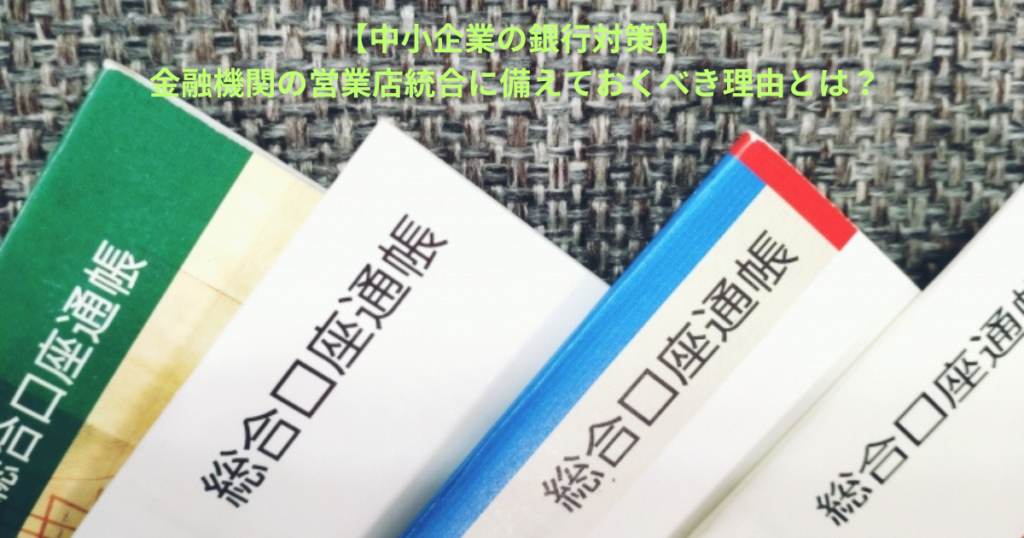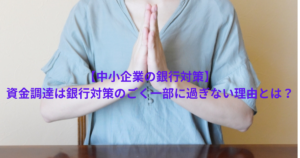【中小建設業の銀行対策】元請建設業に長期運転資金が不要な理由とは?
今日は、中小建設業の銀行対策として、元請建設業に長期運転資金が不要な理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点。
1 原価管理が徹底されていれば長期運転資金は不要
2 引当融資の決め手は精緻な資金繰り表と受注明細に尽きる
どうぞ、ご一読下さい。
1 原価管理が徹底されていれば長期運転資金は不要
建設業、中でも、役所や一般施主から元請で工事を受注する元請建設業は、いざ工事が動き出すと、動くおカネが大きくなるので、銀行対策は必須です。
そもそも、元請建設業は、工事を受注する際、工程毎に積算を弾いて原価を算出して、工事粗利益を乗っけた施工金額で受注をします。
謂わば、工程毎に原価を弾いているワケなので、各工程の原価が当初の想定どおりの金額で収まれば、見込んだ工事粗利益を確保することができます。
他方、実際の工事代金の受領は、完工検査後なので、工事の進捗に従って材料費、外注費、労務並びに現場経費の支払いが先行して出ていくので、その支払を賄うため、金融機関から引当融資(繋ぎ資金)を調達するのが普通です。
各工程の原価が当初の想定どおりの金額で収まれば、厳密にいうと、工事粗利益から引当融資の支払利息を引き算した金額が残ります。
他方、引当融資の支払利息の金額はたかだかしれたものです。
仮に、年度末完工の工事を受注して、12月25日に引当融資を実行してもらって、完工後40日後となる5月10日に最終工事代金を受領、手貸の期日を同日とした場合、引当融資の金額1億円、レート2.000%とした場合の支払利息はざっと740千円程です。
施工代金が1億50百万円とすれば、740千円の支払利息は大した金額にはならないのです。
このように、公共や民間物件でも、元請工事を受注している建設業であれば、現場ベースでの原価管理が徹底されていて、メインバンクとしっかりと握って引当融資をタイムリーに調達できていれば、コロナ禍のような非常時を除けば、長期運転資金の借入金は本来不必要なのです。
銀行員がついつい口に出してしまう「長期安定した資金も必要です」に乗っかってしまうと、不必要なはずの長期運転資金を借入れてしまい、利払負担に加えて、過剰債務の温床にもなりかねないのです。
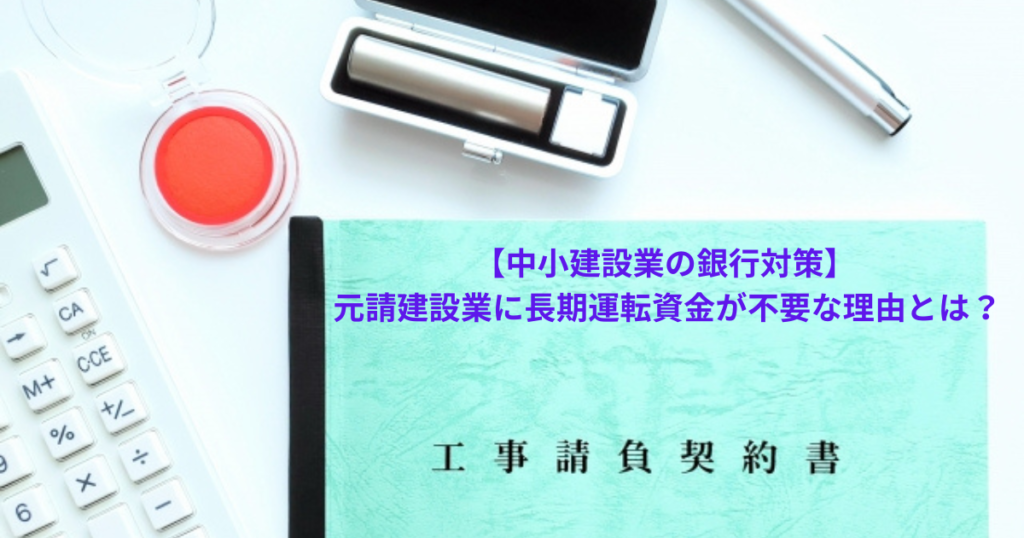
2 引当融資の決め手は精緻な資金繰り表と受注明細に尽きる
このように、引当融資(繋ぎ資金)は、元請建設業にとって、必要不可欠な資金ですが、金融機関側からすると、一筋縄では行きません。
基本的に、引当融資は、保全の上で「信用扱い」です。
融資を受ける側の中小建設業にとってみれば、実質的には、工事代金の最終受領予定金額を担保に出すのと同様に見えますが、金融機関側からすると担保権や質権を設定するわけではありません。
なので、最終代金は融資を出す金融機関に振り込まれてくる(はず)ですし、間違っても、そもそも工事が架空であったり、同じ工事代金を他行にも紐付けられているわけではない(はず)という性善説に基づきます。
とはいえ、金融機関の長い歴史の中では、架空の工事がでっち上げられたり、他行に同じ工事代金を紐づけられたりという苦い経験則が歴然とあります。
このため、工事請負契約書に記載されている場所で間違いなく現場が進んでいることを金融機関の担当者は確認しますし、写真も撮ってエビデンスを残すようにしています。
さらには、工事が完工して最終工事代金が振り込まれてきたら確実に引当融資が完済されることが明確になるような資金繰り表と受注明細が必須です。
資金繰り表と受注明細の精緻さが、引当融資の調達の可否に直結すると言っても過言ではないのです。
中小建設業経営者は、引当融資をタイムリーに調達できるよう、誠心誠意、メインバンク等取引金融機関とコミュニケーションを日頃からとっておくことが重要なのです。
建設ラッシュで-大型工事受注のチャンスを活かすために-絶対に必要なこととは?-1024x538.png)