【中小企業の銀行対策】年度末を口実にして未収入金を回収すべき理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、年度末を口実にして未収入金を回収すべき理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 債権回収は営業担当者の必須業務である
2 未収入金回収によってキャッシュフローを改善する
どうぞ、ご一読下さい。
1 債権回収は営業担当者の必須業務である
日本の中小企業は、小売業や飲食業などのB to Cの商いを除けば、基本的に「信用取引」です。
大手企業のように、取引基本約定書を双方が締結できれば良いのですが、中小企業のほとんどの取引は、口頭での合意に基づきます。
もちろん、契約は口頭でも十分有効ですが、口頭での契約の場合、万が一、お客様とトラブルになってしまった際には、「言った、言わない」の泥試合になってしまいかねません。
得意先が破産手続き等、客観的に見て支払不能の状況に陥れば、大手を振って、貸倒損失として損切りができますが、お客様とのトラブルが原因となった未収入金の債権回収は容易なことではありません。
また、ほとんどの中小企業の営業従事者は、新規開拓がままならないため、既存のお客様を大事にするあまり、得意先の資金繰りが厳しくなって、納品すれど支払がないと、納品すればするほど、未収入金が増加します。
メインバンク等取引金融機関は、決算書を比較する際、勘定科目明細の売掛金や未収入金の中身をよく見ています。
売掛金の「その他」の金額が従前から同額のまま計上されていると、「さては不良化しているな」と疑いの目で見てしまいます。
下手をすると、金融機関は自己査定で、当該未収入金相当を資産性が認められないとして、実態BSで未収入金相当額を資産から差っ引いて査定するかもしれません。
その金額が大きければ大きいほど、実態BSは痛み、場合によっては、実質債務超過に転落するとみなされかねません。
このように、未収入金の健全性は、取引金融機関が注目する重要な点なのです。
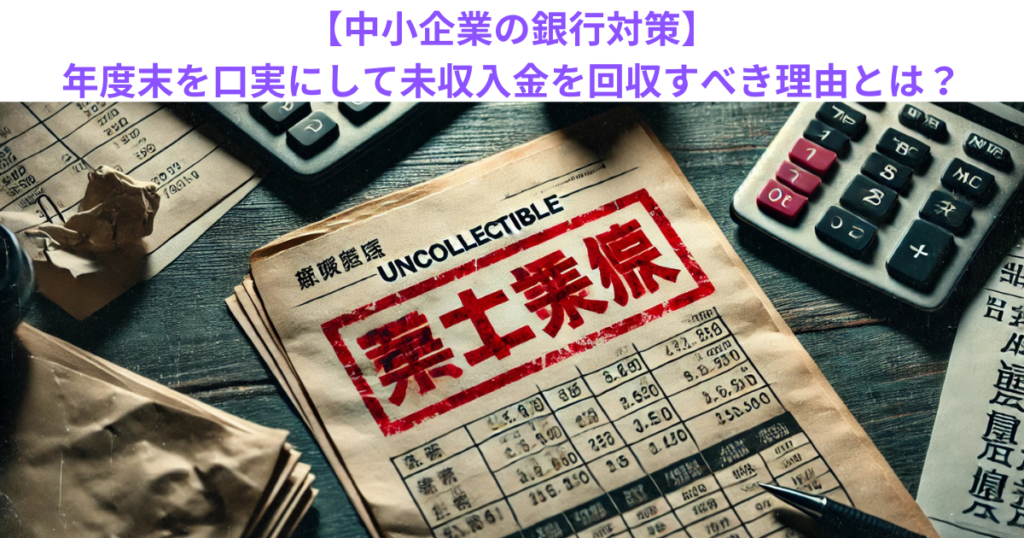
2 未収入金回収によってキャッシュフローを改善する
一営業担当者からすると、「未収入金なんてガミガミ言うけど、お客さん、怒らせるわけにはいかへんから、未収入金はしばらく放っておこ」となってしまいがちです。
しかしながら、経営者は、「未収入金はあかん、なんとしてもでも今月末、集金してこいや」と命じるのですが、両者の認識には大きな差があります。
この認識の差はなぜ生まれてしまうのでしょう?
経営者が会社をマネージメントする中で、最もフラストレーションが溜まるのが資金繰りがタイトになることです。
北出は、そのような会社を多々見てきているので、よくわかるのですが、資金繰りがタイトになると、経営者は余裕を失います。
資金繰りがタイトになる原因は、ひとえに、余計な資産が増えて、負債が圧縮されることによります。
当たり前の話なのですが、未収入金を営業担当者が集金してくると、おカネに変わるわけですから、資金繰りの良化に直結します。
カッコつけて言うと、フリーキャッシュフロー(FCF)が増加します。
また、負債を圧縮する典型例が、金融機関への返済を進めてしまうことで、現預金から借入金の返済に充当するので、フリーキャッシュフローは減少します。
売掛金を先方との約束通り回収して、未収入金にさせないことと、在庫の適正化によって、概ねフリーキャッシュフローは安定化します。
ところが、従業員からすれば、極端な話、ちゃんとお給料が出ていればどうってことはないわけで、積極的に未収入金を削減しようというモチベーションにはつながらないのは至極当然なのです。
中小企業経営者は、未収入金を削減することによって、キャッシュフローの安定化だけではなく、金融機関の心証も良くなることを改めて認識して、自社の決算が3月かどうかはさておいて、3月年度末を口実にして、全社を挙げて、未収入金の集金、債権回収に取り組む必要があるのです。

