【中小企業の銀行対策】安易にリスケジュールに踏み切ってはいけない理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、安易にリスケジュールに踏み切ってはいけない理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 リスケジュールは緊急避難的措置である
2 リスケジュールによって会社の成長スピードが著しく低下する
どうぞ、ご一読下さい。
1 リスケジュールは緊急避難的措置である
リスケジュール(返済の条件変更)が市民権を得たのが今から遡ること15年以上前、2009年に施行された中小企業金融円滑化法以降です。
政権交代によって新たに誕生した民主党政権の下、当時の亀井静香金融担当大臣の鶴の一声で、リスケジュールが金融機関の現場で当たり前のように運用されるようになりました。
円滑化法前の金融機関は、リスケジュールに応じることで、即、債務者区分を不良債権(債務者区分が要管理先以下であること)に引き下げ、取組スタンスを撤退・回収としていましたが、円滑化法以降は、金融機関は債務者からの条件変更の要請に柔軟に対応する一方、債務者区分をその他要注意先に止めることが認められました。
リスケジュールに応じる、即、不良債権とならないのであれば、金融機関としては、リスケジュールに応じやすくなるというアメが与えられたのです。
円滑化法という法律自体は、期限切れとなりましたが、以降も行政庁が金融機関に円滑化法時代と同じような行政指導を行なってきています。
中小企業向け融資の中で、リスケジュールは珍しくなくなったのです。
そもそも、リスケジュール自体の目的が「事業継続」のためであることは疑いがありません。
いわば、リスケジュールは緊急避難的なもので、一定期間、債務者が収益改善を進めることで、返済を元に戻す(あるいは期間10年で借り換える)リファイナンスを実現することが建前でした。
しかしながら、北出が実感しているのが、リスケジュールを受けた債務者にリスケジュールが常態化し、10年以上もの時間が経過しても、リファイナンスを実現できていない中小企業、小規模事業者が少なからず存在することです。
確かに、リスケジュールを受けると、返済がなくなる(あるいは減額される)ことによって、資金繰りは相当に楽になります。
事業の承継者がいないような中小企業、小規模事業者で、リスケジュールが常態化している経営者は、「もう今のままでええかな」と感じていないとも限りません。
ところが、金融機関からの借入金は、助成金や補助金と違って、返済義務があります。
その昔、「借りたカネは返すな」という本がベストセラーになりましたが、道義的な観点からも「借りたカネはきっちりと返す」というのが当たり前です。
リスケジュール中の中小企業経営者、小規模事業者事業主は、リスケジュールがあくまでも緊急避難的な措置にしか過ぎず、収益をしっかりと改善して、「借りたカネはきっちりと返す」という道義的責任を果たす必要があるのです。
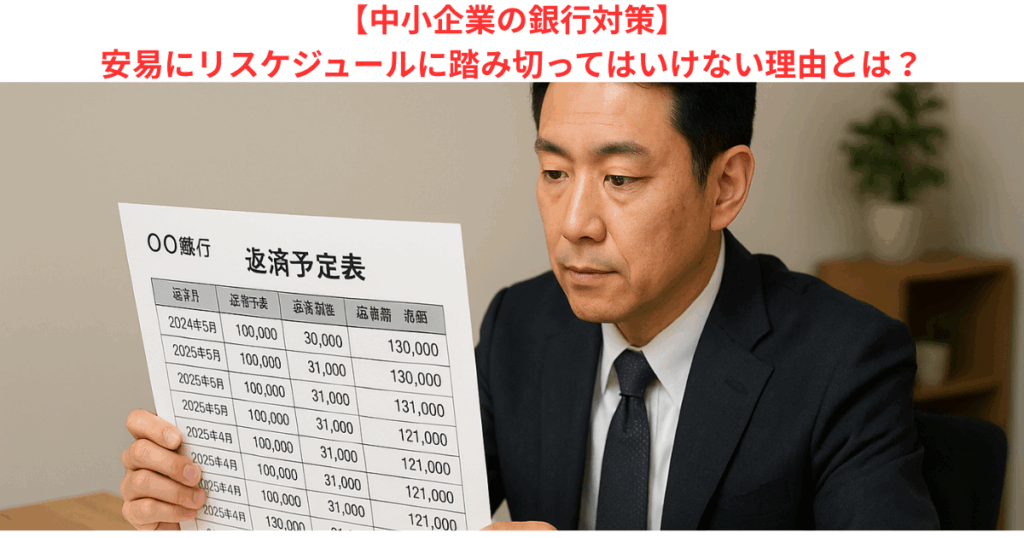
2 リスケジュールによって会社の成長スピードが著しく低下する
実際、資金繰り余力が低下してきて、内心、リスケジュールを検討している中小企業経営者としても、「ホンマに、リスケしてもええんかいな?」と疑問を感じていても不思議ではありません。
リスケジュールが妥当であるケースとして考えられるのが、返済を止めないと、商売上の支払が遅れてしまうことです。
もちろん、材料問屋、外注業者、仕入先への支払が滞ってしまうことは商い上、信用を失墜してしまいます。
それ以上に問題なのが、給料、税金、社会保険料といった優先債権に支払遅延が生じてしまうことです。
給与遅配は、労基法にかかりますし、税金、社保といった租税公課の滞納は、会社の財産の差押のリスクが生じます。
租税公課の払わずに、銀行返済を通常に行なっているのは、明確に、支払の優先順位の間違いです。
他方、建設業等の引当融資等例外を除けば、リスケジュールによって、ニューマネーの調達ができなくなってしまいます。
ニューマネーの調達難となれば、増加運転資金の他、設備資金といった前向きな資金が調達できなくなります。
前向きな資金調達ができなくなるということは、会社の成長スピードを著しく低下させてしまうことになり、同業他社との競合上ネガティブに働いてしまいます。
リスケジュールの弊害として挙げられるのが、いったん、リスケジュールしてしまうと、会社自体リスケジュールが当たり前になってしまって、仮に、1年間限定でリスケジュールして、1年後に返済を元に戻すという方針であったとしても、実際問題、1年後に返済を元に戻すというのは極めて難しいのです。
このように、リスケジュールに踏み切るか否かは、経営者としては、重大な経営判断を強いられます。
リスケジュールに踏み切るかどうかを検討する際には、保守的なスタンスで、向こう1年間の資金繰り表を策定することで、資金繰りのシミュレーションを行なって、リスケジュールの妥当性について、合理的な経営判断を行う必要があるのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。

