【中小企業の銀行対策】取引金融機関と揉めてはいけない理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、取引金融機関と揉めてはいけない理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 中小企業と金融機関との情報格差は余りに大きい
2 金融機関は詐害行為に対して毅然とした態度をとる
どうぞ、ご一読下さい。
1 中小企業と金融機関との情報格差は余りに大きい
中小企業経営者の中には、「なんでうちのメインバンクは親身になってくれないのか」というモヤモヤした不満を感じている方がいらっしゃるかもしれません。
もちろん、業況が厳しくなって、利益が出なくなり、場合によっては、返済原資を産み出すことができず、リスケジュールに踏み切らざるを得なくなってしまうと、追加のニューマネーの調達は難しくなりますし、業績改善に向けて、金融機関担当者が厳しい言葉を吐くことも往々にして起こります。
北出がかつてお会いした経営者の方でも、「あの銀行は許さん。裁判やって、最高裁まで闘ってやる」と息巻いていた方にお会いしたことがあります。
ところが、北出はそのような経営者の方には、「時間とおカネの無駄なので、金融機関とことを構えるのはやめた方が良いです」と諭すようにしています。
そもそも、中小企業と金融機関との間では、情報格差が余りにも大きいと言えます。
仮に規模の小さな金融機関であっても、法務部門が存在していて、しっかりとした顧問弁護士さんもいらっしゃいます。
ヒト、モノ、カネ、情報のいずれも限界のある中小企業が金融機関と争っても、残念ながら、中小企業に勝ち目がないというのが実際のところです。
そのような訴訟でおカネを使うのであれば、専門家を入れて、経営改善に取り組んで、その進捗ぶりを金融機関にモニタリング(業況報告)を通じて共有することで、特にメインバンクであれば、本部の経営改善所管部署(企業支援部等)の調査役が一緒になって経営改善に取り組んでくれる可能性が高まります。
金融機関とことを構えるのではなく、金融機関を巻き込んで、新規取引先を開拓するためのビジネスマッチング等、金融機関が持っている情報をフル活用する方がずっと建設的なのです。
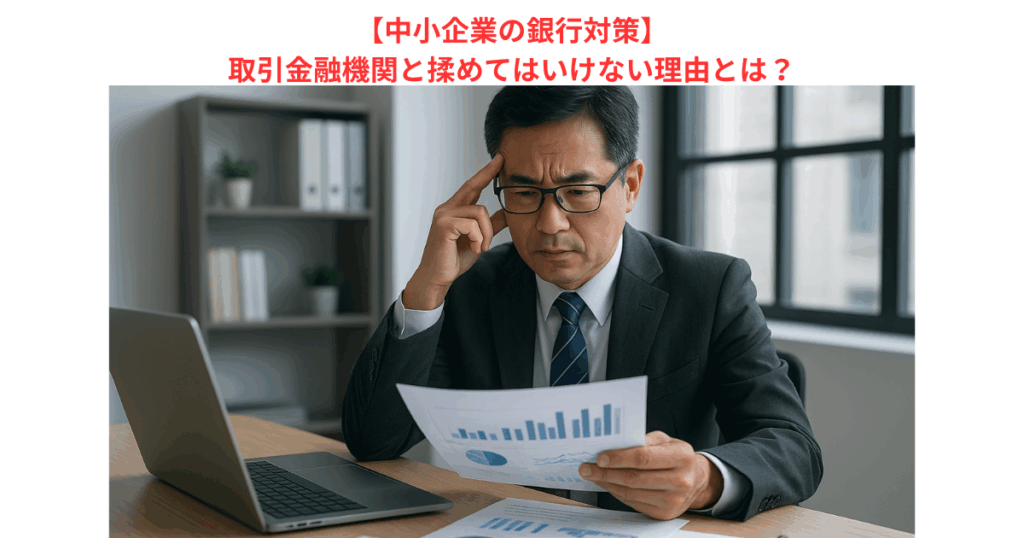
2 金融機関は詐害行為に対して毅然とした態度をとる
かつて、業況が切迫した中小企業が、その手のコンサルにアドバイスを受けて、債権者に告げないまま、勝手に新会社を設立して、事業を移してしまう第二会社方式で債務を踏み倒そうとしたケースがありました。
債権者に黙ったまま、個別催告も行わないまま、事業を別会社に移してしまうことは、典型的な詐害行為としか言いようがありません。
しかしながら、そのような詐害行為に対して、債権者である金融機関は毅然とした態度で、民事訴訟を起こして、詐害的な債務者は法廷で糾弾されました。
もちろん、事業再生のスキームの中で、債権者(特に金融機関)の間で債権カットを伴うような経営再建計画が同意された第二会社方式は当然に有効です。
ただし、債権者である金融機関を騙し討ちにするような行為は許されないことです。
繰り返しますが、金融機関は、詐害的な行為については、徹底的に闘います。
詐害的行為に対して、金融機関が徹底的に闘う理由は、逃げ得は許してはならないという金融機関のスタンスに基づくものです。
詐害的な行為を働く債務者は極めて少数派で、大多数の債務者中小企業は、真面目に金融機関に債務を償還しています。
リスケジュールに追い込まれたとしても、まともな経営者は、収益を改善し、返済原資を創出、増加させ、リファイナンスを目指しています。
このように、大多数の債務者は、真面目で、まともな中小企業です。
中小企業経営者は、取引金融機関と間違ってもことを構えるようなことは差し控えて、真摯に経営改善に邁進していくことが必要なのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご覧下さい。

