【中小企業の銀行対策】地方銀行の融資先選別が進んでいく理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、地方銀行の融資先選別が進んでいく理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 地方銀行の業績は好調である
2 融資先選別が地方銀行の業績を更に押し上げる
どうぞ、ご一読下さい。
1 地方銀行の業績は好調である
3月決算の上場企業の株主総会までちょうど1ヶ月です。
地方銀行(銀行持ち株会社を含む)の決算発表、業績予想が相次いでいますが、総じて、銀行持ち株会社を含めて地方銀行の業績は軒並み好調です。
それもそのはずで、地方銀行各行は、こぞって昨秋から2度の短期プライムレートの引き上げに踏み切りました.
2度にわたる短プラ引き上げによって、文字通り、長らく続いたゼロ金利、マイナス金利の終わりを告げました。
2度にわたる短期プライムレートの引き上げ幅は実に年率0.400%に達します。
金融機関の売上に当たる貸出金利息収入は、融資残高が同額であっても、黙って0.400%増加しているのですから、銀行経営者は高笑いが止まりません。
2025年3月期の地方銀行の業績は、史上空前とは言わないまでも、相当の高水準となりました.
北出では、お客様の中小企業のモニタリング(業績報告)で日々金融機関を訪問して、お客様の中小企業の担当者と打ち合わせをしていますが、時折は雑談もするので、担当の銀行員に「今年の夏のボーナスは楽しみなんと違いますん?」を水を向けてみると、満更でもない様子です。
彼ら彼女ら、銀行員は、今年の連続休暇は軒並み海外旅行となるのかもしれません。
このように、中小企業経営者にとっては重要なステークホルダーの一つである金融機関の足元の業績はなかなかの好調ぶりなのです。
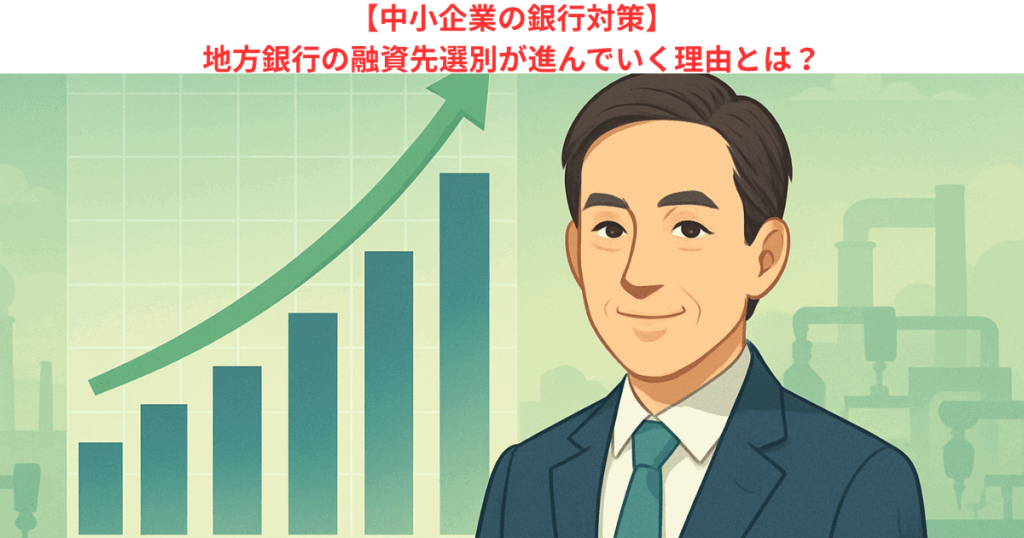
2 融資先選別が地方銀行の業績を更に押し上げる
地方銀行は総じて好業績で推移しています。
ただし、銀行経営者は、好業績によって産み出された利益を放置しておくわけはなく、次の儲けられる一手をどんどん進めていきます。
地方銀行が儲けられる一手の一つが、「融資先の選別」です。
債務者からの要請を受ける形で、リスケジュールに応じてきた融資先について、リスケジュールしているにも関わらず、目立った収益改善が見られなかったり、旧中小企業金融円滑化法時代以来、10年超もリスケジュール状態が継続されているような融資先に対しては、個別に引当を積んで、損失を顕在化させていきます。
例えば、極めて単純化したモデルとして仮定すると、
プロパーで実質信用扱い(保全がない、あるいは足りないこと)の融資残高1億円、適用レート3.500%の融資先X社の場合、銀行が受け取る貸出利息は年間3.5百万円です。
X社の実質信用扱いの融資残高の内、前期稼ぎ出した利益を原資にして50百万円分について、引当を積むとします。
この場合、一時的には、銀行には50百万円もの損失が発生しますが、好業績によって稼ぎ出した利益でカバーします。
一方、現進行年度は、引当済みの実質融資残高は50百万円に減少しますが、X社から受領する貸出利息3.5百万円には変わりがありません。
前年度の実質利回りは年率3.500%(=3.5百万円÷100百万円×100%)ですが、現進行年度以降の実質利回りは年率7.000%(3.5百万円÷50百万円×100%)となって、実質利回りは前期比2倍となります。
つまり、前期に稼ぎ出した利益を原資にして、現進行年度で引当を積んで損失計上する一方、実質利回りを大きく引き上げることで、銀行はより儲かる収益体質を実現することができるのです。
このように、引当を積まれた融資先の中小企業は、銀行から選別され、経営改善さえ銀行から求められなくなってしまいます。
これでは、銀行、メインバンクでさえ、支援継続が難しくなってしまいます。
このように、金融機関は好業績を背景に、融資先の選別を進めていくことは避けられません。
ゼロ金利、マイナス金利の時代には、融資先の選別といったドラスティックな対応には金融機関は距離を取っていましたが、明らかに潮目が変わっています。
中小企業経営者は、金融機関の好業績によって融資先の選別が進むことを認識し、自社の生き残りをかけて、経営改善に不退転の決意で経営改善に取り組む必要があるのです。

