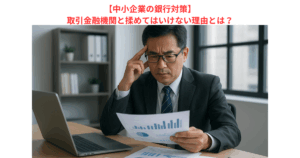【中小企業の銀行対策】長期借入金の返済負担が価格設定に不利に働く理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、長期借入金の返済負担が価格設定に不利に働く理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 長期借入金の返済はPLには反映されない
2 長期借入金の元本返済分を売価に上乗せする
どうぞ、ご一読下さい。
1 長期借入金の返済はPLには反映されない
原価高と人件費の高騰によって、中小企業の収益環境は厳しくなるばかりです。
特に、来月からは、全国で最低賃金が引き上げられることから、労務費、給与手当は益々増加することは避けられません。
原価高と人件費高騰によって、中小企業では、同業他社との価格競争が激化しています。
原価と人件費の上昇分をそのまま転嫁してしまうと、これまでお付き合いのあった既存のお客様を横取りされてしまう懸念が高まります。
同業他社との価格競争の中で、ネックになるのが長期借入金の返済負担です。
誤解しがちなのですが、支払利息は営業外費用としてPLに費用計上されますが、元本返済額は、PLには反映されず、あくまでもBSの中での会計処理です。
損益分岐点をKPIにしていると、無借金経営もしくは短期借入金のみで手貸を書き換えている分であれば良いのですが、損益分岐点で収益を設定してしまうと、長期借入金の元本返済分のキャッシュアウトが発生してしまいます。
元本返済分のキャッシュアウトが続いてしまうと、返済原資がないため、いずれ、リスケジュールを強いられてしまいます。
泣く泣くリスケジュールに追い込まれることのないよう、長期借入金の返済分を加味した売価の設定が必須なのです。

2 長期借入金の元本返済分を売価に上乗せする
「それじゃ、リスケをしてしまって、返済負担をなくしてしまえば価格競争力が上がるんと違うか」という声が出るかもしれません。
しかしながら、リスケジュールに踏み切るということは、長期借入金が減らずに、予想される更なる利上げによって支払利息負担が重くなってしまうので、価格競争力を上げるためにリスケジュールをしてしまえというのはあまりにも乱暴で避けなければならない経営判断です。
長期借入金の返済を進めていくためには、単に安売り競争に巻き込まれるのではなく、より高品質なサービスを提供するなどして、価格を維持、上乗せできるような経営努力が必要不可欠です。
物価上昇と人件費の高騰はまだまだ続くことを想定しながら、長期借入金の返済原始を確保するための経営努力が必要なのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。