【中小企業経営者の心得】資金繰り表のキモが消費税納付にある理由とは?
今日は、中小企業経営者の心得として、資金繰り表のキモが消費税納付にある理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 消費税は預かり金である
2 中間納税と確定分納付が資金繰り表のキモである
どうぞ、ご一読下さい。
1 消費税は預かり金である
中小企業経営者の方から頂く質問の中で、「消費税の納付額てどうやって決まるのか、教えてくれ」という質問を受けることがままあります。
確かに、消費税というやつはなかなか厄介なもので、決算申告時に確定分の消費税を納める他、中間納税もあって、外回りや融資係の銀行員も的確に把握していないケースが散見されます。
中小企業にとっての消費税は、簡単にいってしまえば、期中にお客様からお預かりした消費税(請求書に本体価格に10%を乗じた額)から、同じく期中、日々の原材料費、外注費や諸経費の支払いの際、10%の消費税を支払った差額を税務署にお納めするということになります。
試算表上のBSの流動負債の「仮受消費税」がお客様からお預かりした消費税の累計額であり、BSの流動資産の「仮払消費税」が外注費や諸経費の支払いの際に支払った消費税の累計額です。
ざっくりいってしまえば、決算申告時に仮受消費税と仮払消費税の差額を税務署に納付するというのが消費税の大雑把なイメージとなります。
このため、税務当局からすれば、当たり前のことなのですが、「消費税を滞納するとは何事か! 預かり金的な性格の強い消費税を運転資金に充当しているのではないか」というロジックなので、消費税の滞納には税務当局は厳しい姿勢です。
確かに、お客様からお預かりした消費税を納めないというのは、税務署的にはけしからんということになるのでしょう。
改めていうまでもありませんが、消費税の滞納は絶対やってはいけません。
国税徴収法で税務当局は資産等を差押えることができるので、資金繰りが厳しくて消費税が納められない状況に陥る前に、銀行への返済をリスケジュールすることも十分検討に値するのです。
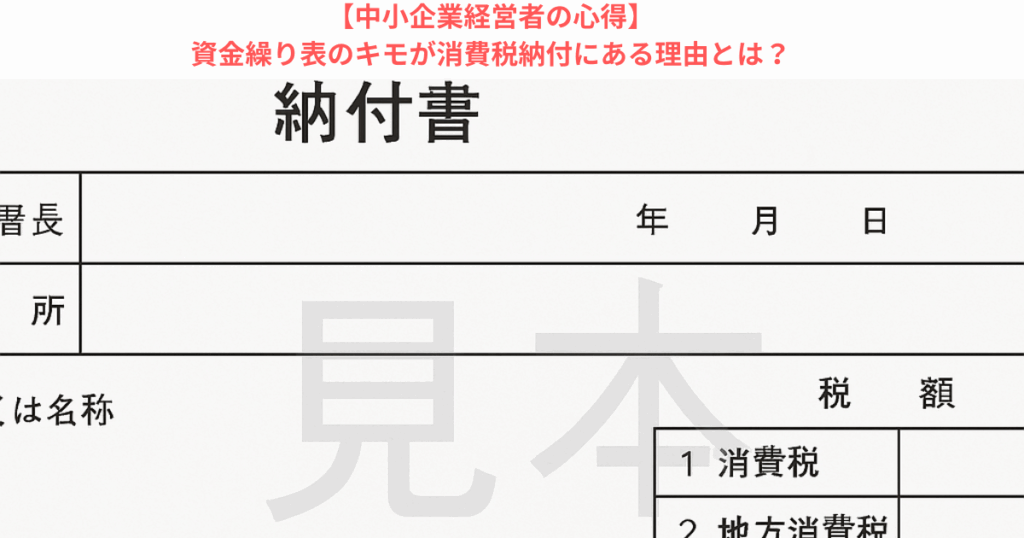
2 中間納税と確定分納付が資金繰り表のキモである
では、中小企業で中間納税の仕組みはどうなっているのか、詳細は会計事務所にお任せすることになりますが、ザクっとですが、前年度の消費税の国税分の納付額が400万円以下の場合、中間納税は1回となります。
仮に、3月決算の会社の場合の納付期限は、確定分が5月末、中間納税が11月末となります。
前年度の消費税の国税分の納付額が400万円調の場合は、確定分5月末、中間納税が8月末、11月末そして翌年2月末の3回となります。
弊所では、お客様の中小企業の資金繰りを資金繰り表で向こう1年間シミュレートしますが、この中間納税と確定納税分をしっかりと盛り込んでおかないと、資金繰りを大きく見誤ることになりかねません。
中間納税は前期の実績で決まるため、売上高が前年同月実績を上回っている場合、実態よりも中間納税額が少なくなってしまって資金繰り表を一見するとキャッシュリッチになってしまった気になってしまいます。
しかしながら、次回の確定分納付時に上振れた仮受消費税分を納めなければならなくなるため、次回確定分納付時の納税額が想定よりも大きくなってしまう公算が大きいのです。
このように、消費税の確定分と中間納税分をしっかりと資金繰りの中で盛り込んでおかないと、想定外の資金ショートさえ起こり得ます。
中小企業経営者は、消費税を甘くみることなく、消費税を納付期日に間違いなく納付できるよう、しっかりと資金繰りをシミュレートする必要があるのです。

