【中小企業の銀行対策】銀行担当者に出来ない約束をしてはならない理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、銀行担当者にできない約束をしてはならない理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 Yes or Noを明確化する
2 銀行担当者に出来ない約束をしてはいけない
どうぞ、ご一読下さい。
1 Yes or Noを明確化する
自社の銀行担当者と面談する際に、最も話題となるネタが2つあります。
1つ目は、会社業績のお話で、期初から現在までの業況推移についてで、試算表がその基本情報で、期末にかけての業績予想についてで、試算表をもとに期末の着地を予想します。
2つ目が、資金繰りのお話で、たとえば、季節変動要因があるような業種で、繁忙期に資金が必要な場合、資金調達が必要となります。
業績が順調でキャッシュリッチな状態であれば、銀行担当者も安心します。
逆に業績が厳しく、キャッシュアウトの可能性があれば、後ろ向きの資金手当の話になりますし、場合によっては、リスケジュールやむなしというお話になることもありえます。
いずれについても、銀行担当者に対して、曖昧な受け答えはNGです。
基本的にYes or Noを明確にすることが、銀行交渉に基本中の基本です。
これらについて、明確に受け答えができれば、銀行員は納得しますし、安心して上席に報告することができます。
銀行という組織は、典型的なピラミッド型組織なので、融資先の経営者がYes or Noを明確にすれば、担当者から役席、役席から次席へ、次席から支店長(部店長)へと話が通りやすいのです。
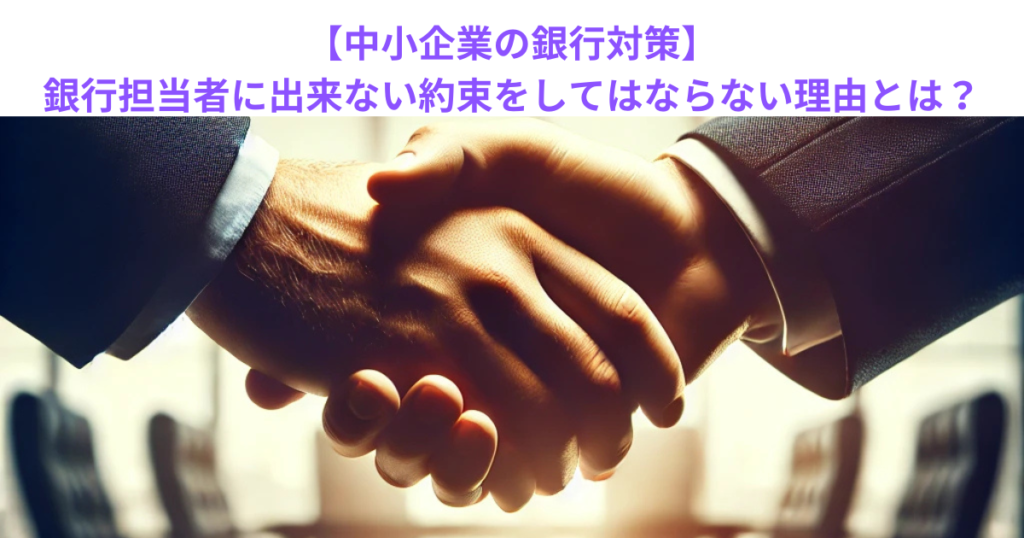
2 銀行担当者に出来ない約束をしてはいけない
銀行担当者との打ち合わせ時のお話に戻ります。
中小企業であっても、経営者たるもの、プライドがあります。
なかなか弱音は吐けませんし、吐くべきではありません。
しかしながら、前月の試算表が期初からの経常損益でマイナスになっている場合で、通期の業績予想の話になった時、内心(黒字化はむずかしいなあ)と思っていても、「いやいや、期末にかけて、大きな受注の目処が立っていて、通期ではちゃんと利益が出ますから、安心して下さい」などと出まかせを言ってはなりません。
銀行員との打ち合わせの中で、原則「ハッタリ」は御法度です。
銀行員は、打ち合わせ内容を上席に報告するだけではなく、記録に残しています。
経営者が記憶の彼方に忘れていることでも、銀行員は過去の打ち合わせ履歴を見るので、「ハッタリ」はかましてはいけないのです。
実際、期が明けて、決算書ができて、決算書を銀行に提出した時、黒字転換できなかったとなれば、(この社長、嘘ついてたんと違うか)と銀行員は勘繰ることにもなりかねません。
こういうケースは、取引銀行の心証をとても悪くするので、出まかせやハッタリは控えなければならないのです。
このように、銀行員に、できない約束を安易にすることは絶対に避けなければなりません。
中小企業経営者は、取引銀行の担当者に対して、下手に出る必要はありませんが、できない約束や、嘘ハッタリは御法度であることを認識する必要があるのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご覧下さい

