【中小企業の銀行対策】経営改善を軌道に乗せるために経営者が実践すべきこととは?
今日は、中小企業の銀行対策として、経営改善を軌道に乗せるために経営者が実践すべきことについて考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 経営改善計画を絵に描いた餅にしてはいけない
2 経営改善を成功に導くためには従業員の士気向上が必須である
どうぞ、ご一読下さい。
1 経営改善計画を絵に描いた餅にしてはいけない
リスケジュール(返済条件を緩和すること)の状態にあったり、財務体質が脆弱(BSが傷んでいること)である場合には、取引金融機関や信用保証協会等の債権者から経営改善計画の策定が経営者に要請されます。
経営改善計画の策定には、自社で策定できればそれに越したことはありませんが、専門家が関与して経営改善計画を策定したり、策定の助言を行ったりします。
最近の経営改善計画は、より実現性を高めるために、必要以上にテールヘビー(計画期間の後半に収益をV字型に回復させたりすること)にするようなことは避けるのが一般的です。
ただし、中小企業活性化協議会や信用保証協会から専門家を紹介される場合、経営改善計画の策定時には、専門家と経営者との間で十分な意思疎通ができないことも珍しくないと言うのが現実です。
経営者からすると、場合によっては、「専門家が作ったもので、実感が薄い」といったことになりかねず、そのようなケースでは、経営改善計画自体が経営者にとってリアル感が薄く、結果として絵に描いた餅になってしまいかねません。
このため、経営者は関与する専門家を信頼して、会社の実情や業界環境を共有して、専門家との信頼関係を短期間で構築する必要があります。
わたくし自身も、経営改善計画の策定に当たっては、経営者とのコミュニケーションをしっかりと取って、経営者のお人柄への理解を深めるよう、努力をしています。
実際、経営改善計画はいざ、債権者から賛同や同意を得る以上、非常に重たいものになります。
経営者は、経営改善計画を重たく受け止め、計画の実効性を上げていく必要があるのです。
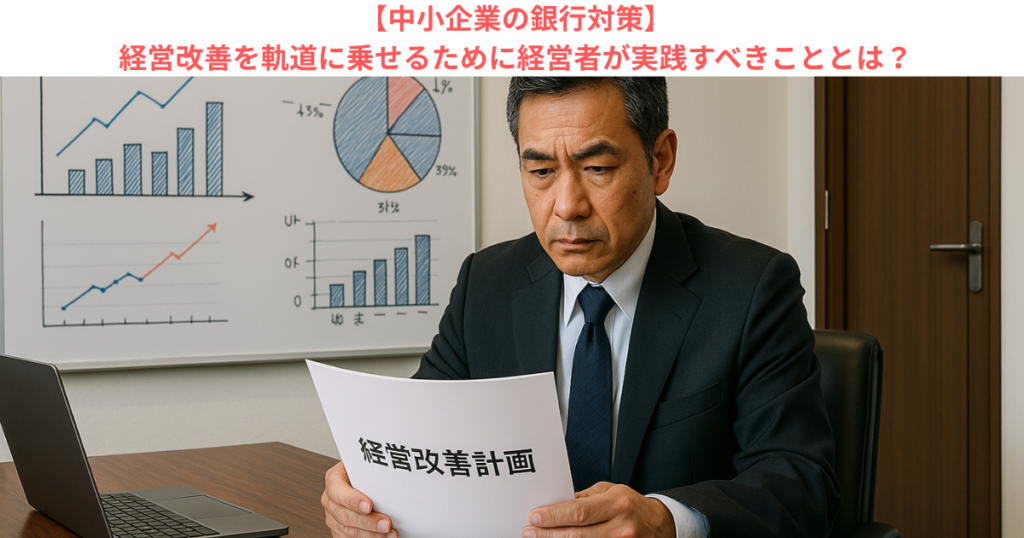
2 経営改善を成功に導くためには従業員の士気向上が必須である
いざ、経営改善計画が、債権者等から賛同されると、経営改善計画は重たいものとなります。
経営者が後々「そういうつもりではありませんでした」といっても、それは通らないお話しです。
経営改善計画を軌道に乗せていくのに第一義的に必要なことは、経営改善計画の中で明文化されているアクションプラン(経営改善への具体的な施策とその効果)を粛々と実行に移していくことです。
例えば、原価上昇分を吸収するため、202X年XX月に平均で10%値上げを実施することで、売上総利益率を4%改善するというようなアクションプランであれば、202X年XX月に平均で10%の値上げを実際に実施しなければなりません。
さらに重要なことは、値上げを実施して以降、試算表上で売上総利益率が本当に4%改善したのか否かについて、効果測定を行うことが何より重要です。
加えて、経営改善は経営者一人だけでできるものでは決してありません。
製造業でも、建設業でも、飲食業でも、従業員の頑張りがあってこそ、初めて、経営改善を実現することができます。
経営改善の実現には、従業員の士気向上が必要不可欠なのです。
なので、北出が経営改善計画を策定する際には、毎年一定の賃上げを見込んで、労務費と給与手当の増加を盛り込むようにしています。
実際、かつてのデフレ時代とは違って、人材確保の観点からも、一定の賃上げを継続することに金融機関等債権者も異議を唱えることはありません。
トランプ関税とインフレ、人手不足と、業種を問わず中小企業を巡る外部環境は決して楽観視できるものではありませんが、経営改善を軌道に乗せるためにも、経営者の覚悟のみならず、従業員の士気向上が必要不可欠なのです。

