【中小企業の銀行対策】経営者が認識すべき資金繰り表の真の重要性とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、経営者が認識すべき資金繰り表の真の重要性について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 資金繰り表は取引金融機関への有効なモニタリングツールである
2 資金繰り表の本質を知る
どうぞ、ご一読下さい。
1 資金繰り表は取引金融機関への有効なモニタリングツールである
弊所が新規のお客様である中小企業にお邪魔させて頂いた時、最初に経営者にお尋ねするのが、「資金繰り表は自社で作成されていますか?」です。
実際、資金繰り表を自社で主体的に作成している中小企業は非常に少なく、資金繰り表が作成されているケースとして、リスケジュール中であったり建設業で工事見合いの短期繋ぎ資金(引当融資)を調達していて、金融機関から資金繰り表の作成を要請されているか、よほど資金繰り余力が厳しいのかが挙げられます。
いずれにしても、「当社は資金繰り表を作成しています」という中小企業は少数派であることは間違いなさそうです。
弊所では、お客様の中小企業の取引金融機関へのモニタリング(業況報告)を月次で行えるよう、全面的にお手伝いをしていますが、資金繰り表を金融機関に提出すると、取引金融機関担当者は、こぞって、「本当に助かります」と声を揃えます。
このように、試算表と共に、金融機関への開示資料として資金繰り表は極めて有効で、絶好のモニタリングツールなのです。
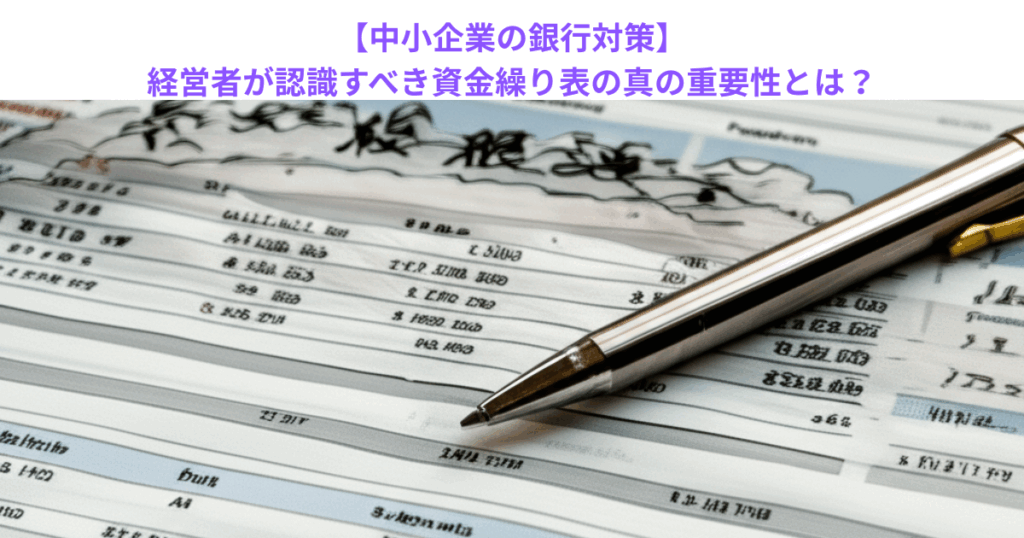
2 資金繰り表の本質を知る
先ほども、申し上げましたが、資金繰り表というと、どちらかというと、銀行対策用として用いられていることが多く、取引金融機関に提出するためにやむなく資金繰り表を作成するというネガティブなイメージがあることも否定できません。
ところが、資金繰り表自体、北出からすると、攻めの経営に有効なツールであると信じています。
そもそも、資金繰り表とはなんでしょうか?
よく資金繰り表と試算表との違いが認識されていないことがあるのですが、試算表は過去の業績の推移で、損益のフローと貸借のストックを示したものです。
一方、試算表はあくまでも発生ベースが基本なので、いくら利益が出ていたとしても、おカネが増えるのかあるいは減るのかが試算表だけでは分かりません。
資金繰り表とは、敢えて北出が定義するとすれば、「ビジネスモデルをおカネの流れで表現したもの」ということができます。
資金繰り表で、向こう半年間、1年間のキャッシュの推移をシミュレートするというのが資金繰り表の究極的な役割です。
端的に言えば、キャッシュが減っていく、あるいは「資金ショート」してしまう懸念があれば、そのビジネスモデルは欠陥そのものであって、大至急、ビジネスモデルを作り直さねばなりません。
会社が倒産に至る根本的な原因が、「資金ショート」です。
フローで利益が出ていたとしても、おカネが尽きたら、会社は材料費や外注費、給与労務費が支払えず、果ては電気も止まってしまって、事業を継続することができなくなります。
このような資金ショートを回避するためのツールが資金繰り表です。
中小企業で売上高が3億円であるのに対して、流動性預金の平残が2億円を常に維持しているといった具合に、資金が潤沢な会社でない限り、資金繰り表を作成せずに経営をしていくこと自体、経営者が目隠しをして会社の舵取りをすることと同義なのです。
このように、借入金の依存度が極端に高くない会社であっても、中小企業にとって、資金繰り表はなくてはならない存在です。
資金繰り表作成に関心を持たれた中小企業経営者がいらっしゃれば弊所までお気軽にお声がけ下さい。

